交通事故の慰謝料を弁護士基準表で自分で計算!弁護士基準にするには
弁護士基準について解説します。日額いくらか、通院日数との関係、自分で弁護士基準にできるか?を後遺障害14級慰謝料、追…[続きを読む]
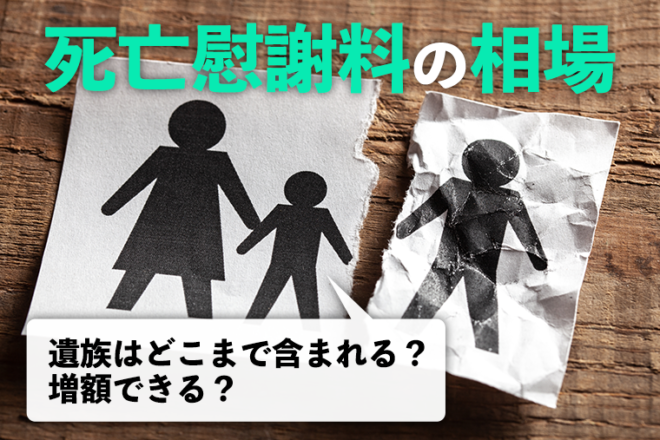
突然、旦那や妻が交通死亡事故に巻き込まれ、保険金や慰謝料について気になる方もいることでしょう。
賠償金が多額となる死亡事故では、少しでも慰謝料を安くしようとする保険会社の提示額と本来の適正な慰謝料との差も大きくなります。
保険会社が提示される、不利な示談を受け入れてしまわないように、死亡事故の慰謝料の正しい金額を知ることが必要です。
この記事では、旦那や妻がなくなった場合の、弁護士基準での死亡慰謝料の金額、死亡慰謝料を請求できる者は誰か、各人の請求できる金額、自賠責保険から支払われる金額、70歳、80歳、90歳などの交通事故死亡慰謝料の注意点などについて説明します。
目次
慰謝料には、算定に使用する基準が高額なものから弁護士責基準、任意保険基準、自賠責基準の3つ存在します。死亡慰謝料も例外ではありません。
弁護士基準は、弁護士が示談交渉する際や裁判でも使用される裁判例に基づいた基準であり、唯一妥当な基準でもあります。
そこで、まずは、弁護士基準での死亡慰謝料相場について解説します。
交通事故の死亡慰謝料の相場を見てみましょう。
弁護士基準における死亡慰謝料の額は次のとおりです(※)。
| 死亡した人 | 金額相場 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2,800万円 |
| 母親・配偶者 | 2,500万円 |
| その他(独身の男女、子ども、幼児、高齢者等) | 2,000~2,500万円 |
※「赤い本」正式名「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部)による。
「一家の支柱」「母親・配偶者」「その他」という区分は、昭和時代にポピュラーだった、働く父親、主婦、子ども達、祖父母で構成する家族をイメージしていただければ理解が容易です。
実際、この基準は、そのような家族像を前提としたものです。
一家の支柱とは、被害者の世帯が主として被害者の収入によって生計を維持している場合を言います。
一家の支柱の慰謝料が高額な理由は次のとおりです。
なお「夫婦共働き」で同程度の収入がある場合、「どちらも一家の支柱である」とは言えません。
また「年金生活者」は、その年金収入で夫婦が生計を立てていても、その働きで子どもらを扶養する立場にないので、一家の支柱とは言えません。
家事の中心をになう主婦、子どもを持つ母親、また独身の男女であっても高齢の父母や幼い兄弟姉妹を扶養したり、仕送りをしたりしている方などは「母親・配偶者」に含まれます。
また、男性が家事育児の中心的役割をしている、いわゆる「主夫」も含まれます。
「その他」には、独身の男女、子ども、幼児、70歳、80歳、90歳近くの高齢者が含まれます。
またその他の「2,000~2,500万円」という金額の幅は、上限下限を示しているものではありません。幅のある数字が示されているのは、幅広い年齢層が含まれるからです。
他方、一家の支柱、母親・配偶者の数字が幅のある金額ではなく、単一の数字になっているのも、幅のある数字を示すと上限と下限であると「誤解」される危険があるからです。
ほぼ人生を全うした70歳、80歳、90歳近くの高齢者と、人生の多くを享受できないで終わった若年者を同列にはできませんし、少子・核家族化した社会では子どもを亡くした家族の苦痛が極めて大きいことから、幅のある金額となっているのです。
交通事故死亡慰謝料の傾向として、30歳未満の若年層には特段の増額理由がなくとも2,400万円以上の裁判例が多いです。
一方、会社を退職し収入が落ちる65歳くらいから、一家の支柱よりも「その他」に分類されることが多くなりますが、それも家族の収入による相対的なものです。
ただ、70歳、80歳、90歳と年齢を重ねても2,000万円を下回った近時の裁判例はないと報告されています(*)。
※「交通賠償のチェックポイント」弁護士高中正彦他編著・弘文堂148頁
つまり被害者が、高齢者だからといって、直ちに慰謝料額が大きく減額されてしまうわけではありません。
なお、高齢者の場合に注意しなければならないのは、死亡慰謝料よりも「死亡逸失利益」です。
事故当時、働いていない場合などは、請求が認められにくいのです。詳しくは、以下の関連記事をお読みください。
交通死亡事故の弁護士基準の死亡慰謝料を解説した次に、3つの基準のうち、最も低額である自賠責基準における死亡慰謝料の相場を解説します。
自賠責基準は、全ドライバーが加入を義務付けられている自賠責保険による支払いの基準です。
自賠責保険から支払われる金額は、法令によって定められています。
通常、加害者が任意保険に加入していれば、任意保険から支払われる慰謝料のうち、自賠責が負担すべき部分は、自賠責保険から支払われます。
加害者が自賠責保険にしか加入していない、任意保険会社の対応が悪い場合は、被害者が自分で自賠責保険に請求することができます。
※ 2020年3月31日以前に発生した事故については、350万円
| 請求者1名のとき | 550万円 |
|---|---|
| 請求者2名のとき | 650万円 |
| 請求者3名以上のとき | 750万円 |
※ 被害者に被扶養者がいる場合は、200万円を加算
※「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」平成13年金融庁・国土交通省告示第1号
では次に、死亡慰謝料を請求できる者について説明します。
死亡慰謝料を分類すると下記3種類に分けることが出来ます。
1の「死亡した本人自身の慰謝料」は、本人が受け取る代わりに「相続人」つまり通常は配偶者と子供が受け取り、子がいない場合は配偶者と親(直系尊属)が受け取ることになる慰謝料です。
また死亡慰謝料は本人自身の慰謝料だけではなく「近親者固有の慰謝料」「近親者に準ずる者の固有の慰謝料」もあります。
なお「相続人が多数いる」「近親者が多数いる」「近親者に準ずる者が多数いる」等で、慰謝料を請求できる権利者が多いからといって、死亡慰謝料額が高くなるわけではありません(※)。
弁護士基準の金額は、この3種類の慰謝料の「総額」を示しているからです。
※「被害者死亡の場合における近親者固有の慰謝料」東京地裁民事交通部・磯尾俊明裁判官講演録(前出「赤い本」2017年版下巻14頁)
通常、死亡した被害者の法定相続人が、被害者本人の「慰謝料請求権を相続して行使」することになります。
例えば、遺族が妻と長男、次男の場合は、妻が2分の1、長男及び次男はそれぞれ4分の1の慰謝料請求権を相続することになります。
ただし被害者が「遺言」を残していれば、その内容に従うことになります。
例えば、事故被害者が、入院中に死期を悟って慰謝料を含む損害賠償請求権を相続する者、その割合を指定する遺言を残した場合が考えられます。
また被害者が従前から「遺産はすべて長男に相続させる」などの包括的な内容の遺言を残していた場合は、損害賠償請求はその長男が相続することになります。
死亡した被害者の「父母・配偶者・子ども」は、本人の慰謝料とは別に、独自の慰謝料を請求することが認められています。
これを近親者固有の慰謝料請求権といいます(民法711条)。
民法711条が定めている「父母・配偶者・子ども」ではなくとも、下記のような場合、民法711条所定の者と同様に固有の慰謝料請求権が認められるという裁判例があります(※)。
この最高裁の事案は、被害者女性の夫の妹、つまり義妹に固有の慰謝料請求権を認めたものです。
義妹は身体障害者で、長年にわたり被害者が同居して庇護しており、将来的にもそれが期待されていたという関係にあり、まさに上記1及び2の条件を満たすものでした。
ただ、これらの条件を厳格に要求すると、この最高裁の事案のような特別なケースしか慰謝料を認めてもらえなくなります。
しかし、今日の裁判実務では、これら条件をあまり厳しく求めることはせず、比較的緩やかに慰謝料請求を認めています。
この点、裁判所は慰謝料請求権者を広く認める代わりに、「人数が増えても慰謝料の総額を変えない扱いをしている」とも指摘されています(※)。
「総額が同じ」なら、何人に権利を認めても差し支えがないうえ、被告となる加害者側の関心は総額がいくらとなるかに向いており、誰が慰謝料請求権者かについては強く争わないためです。
※前出の磯尾俊明裁判官講演録15頁
では、以下では、この「民法711条所定の近親者に準ずる者」として、慰謝料請求が認められるケースについて個別に見てゆきます。
「内縁の配偶者」が異論なく慰謝料請求権が認められます。
片方に戸籍上の配偶者が存在する場合(重婚的内縁)でも同じです。
内縁の配偶者は、本人分の慰謝料や逸失利益の請求権を相続できないため、生活保障の趣旨から、固有の慰謝料として認められる金額が比較的高くなる傾向にあると指摘されています。以下、裁判例です。
神戸地裁平成14年8月29日判決
被害者は61歳男性です。裁判所は、前妻との子ども2名に本人の慰謝料相続分と子ども固有の近親者慰謝料として合計1600万円を認める一方、内縁配偶者の固有の慰謝料として1000万円を認めました。
(交通事故民事裁判例集35巻4号1189頁)
なお、同性カップルでも、結婚と同視できる生活実態があれば、同様に慰謝料請求権が認められるであろうという意見もあります。
単に婚約したというだけでは慰謝料請求権は認められません。
事故前にすでに同居するなどして「内縁関係」となっている場合は慰謝料請求権が認められます。
被害者が未認知の父親だった場合、法的に認知していなくとも、実際に同居をし、扶養されている関係にあれば慰謝料請求権を認められます。
兄弟姉妹の場合、事故時に同居していると、通常、慰謝料請求権を認められます。
事故時点では別居していても、長年同居して育ち、進学や就職のために別居して間もない場合は慰謝料請求権を認められやすいと言えます。
祖父母・孫の場合、事故時に同居していると「養育」や「介護」の生活実態を踏まえて判断されます。
他方、事故時に同居していない場合は、基本的に認められていません。
その他、義父母・叔父叔母・連れ子なども、生活実態(同居、扶養の有無など)に応じて判断され認められる場合もあります。
複数の親族から慰謝料が請求されたときは、総額をどう配分するかが課題となります。
これについては「目安になるようなものは現状では見いだせない」(※1)と報告されており、裁判所がその裁量で適宜金額を認定していると思われます。
実際、前出の「赤い本」でも、親族間の慰謝料の配分については「遺族間の内部の事情を斟酌して決められるが、ここでは基準化をしない」(2020年版上巻185頁)とされています。
※1:「交通事故損害額算定基準26訂版」183頁(日弁連交通事故相談センター本部)
ただ、裁判例の金額の傾向としては、次のような傾向があると報告されています(※2)
※2:前出「交通賠償のチェックポイント」152頁
| 民法711条所定の近親者 | 100万円から300万円 |
|---|---|
| 民法711条所定の近親者に準ずる者(※) | 100万円未満 |
| 内縁の配偶者 | 比較的高額となり1,000万円を超える例も多い |
※ ただし、祖父母に比べれば、兄弟姉妹の方が100万円以上を認められやすい
最後に、任意保険会社と示談交渉する際の注意点を解説致します。
任意保険会社が提示する慰謝料額は「弁護士基準で計算した慰謝料相場を下回る」ことが通常です。
また民法711条所定の「父母・配偶者・子ども」全員に固有の慰謝料請求権があることなどを教えてくれない場合があります。
まして、これらに準ずる関係がある者にも権利があることなど伝えようとはしませんし、これらの者が権利を主張しても、逆に否定されてしまう場合もあります。
死亡事故では保険会社の担当者も神妙な態度で接してきます。しかし正当な賠償金額を被害者側に支払うために尽くしてくれるとは限らないのです。
ことに死亡事故では慰謝料も含めた全体の賠償額が巨額になりますので、適正な賠償額と保険会社の提示金額の差は著しくなりがちで、時には数千万円から1億円近い金額の隔たりがあります。
実際に、最初遺族だけで示談交渉をしていて、途中から弁護士に依頼をして交渉してもらったところ、数千万円も増額されたというケースは決して珍しいことではないのです。
交通事故死亡慰謝料の請求金額が増えるケースがあります。
例えば、加害者が飲酒運転やひき逃げをした場合、また裁判での虚偽の主張など加害者が不誠実な態度をとった場合、慰謝料を増額する事情として考慮されます。
また、被害者の近親者が、被害者の死亡によってショックを受けてPTSDなど精神症状を発症した場合も慰謝料を増額する事情となります。
以下、裁判例となります。
名古屋地裁平成14年12月3日
生後6ヶ月の乳児が被害者の死亡事故です。加害者は無免許運転で、母親は2年間の不妊治療のすえに授かった子を目の前で乳母車ごと跳ね飛ばされ、PTSDに罹患しました。
裁判所は、これらの事情等を考慮して、本人分2,100万円、父親300万円、母親600万円の総額3,000万円の慰謝料を認めました。」
(交通事故民事裁判例集35巻6号1604頁)
以上のことから、正しい賠償額を受け取るには、増額すべき事情をしっかりと主張・立証する必要があります。
今回は、旦那や妻が交通事故死に巻き込まれた場合の、保険金、交通事故死亡慰謝料の計算方法、金額相場、注意点などを解説して参りました。
最近は60歳、70歳、80歳など高齢者の方が引き起こす死亡事故も増えています。何の落ち度もない人が自己に巻き込まれ、命を落とすこともあります。
その際、死亡事故の損害賠償について、相手の保険会社の言うままに任せてしまうと、適正な補償を受けることができない場合もあります。
保険会社との示談交渉について不安なことがある方は、ぜひ交通事故に強い弁護士に相談し依頼することをおすすめ致します。