交通事故の逸失利益の自動計算ツール・計算式や方法を解説!
交通事故の逸失利益の自動計算ツールと実際の計算方法を知りたい方がいらっしゃることでしょう。 事故によって受けたけがや…[続きを読む]
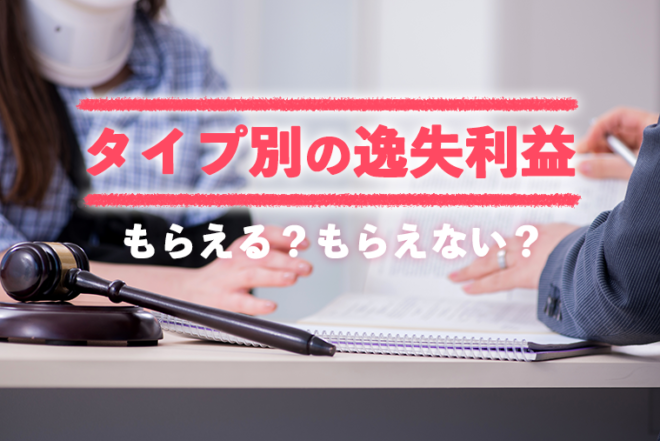
交通事故によってむち打ちなどの神経障害など後遺症が残った場合に、加害者に対して「逸失利益の請求」ができるケースがあります。
逸失利益とは「本来交通事故に遭わなければ得る事ができたであろう収入に対する損害賠償」のことを言います。
逸失利益は計算が少し複雑で、また職業や属性によって、対応方法が異なります。
そこで今回は、会社員や主婦、無職者などタイプ別の早見表について解説したいと思います。
目次
まず交通事故の逸失利益の基本的な計算方法を示します。
すべてのタイプを通じて、逸失利益の基本的な計算方法は以下の通りです。
たとえば、以下のような条件で逸失利益を計算すると、次のようになります。
【参考外部サイト】就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省
上述した計算方法で逸失利益の算出できます。しかし、現実はそう単純ではなく、この金額をそのまま受け取れるとは限りません。
「基礎収入」と「労働能力喪失率」が示談交渉や裁判において争いになるからです。
基礎収入と労働能力喪失率は、以下2つの要素に大きく関係しています。
1:後遺症が「仕事」にどのような影響を与えているのか
2:それによって実際にどの程度の「減収」が発生しているのか
逸失利益は、職業や属性によって対応方法が異なります。下記の早見表から、ご自身とマッチする記事を御覧ください。
| 属性 | 記事名 |
|---|---|
| 主婦 | |
| 子供・学生 | |
|
自営業・個人事業主
|
|
| 公務員 | |
| 無職・ニート | |
| 会社員 | *会社員の場合は以下、簡単に解説。または、交通事故と逸失利益|もらえる場合・もらえない原因等わかりやすく解説! |
会社員・サラリーマンの場合は、事故前の「基本給」「歩合給」「各種手当」「賞与」などが基礎収入の対象となります。
そして、会社員・サラリーマンの逸失利益は、後遺障害の内容によっては大きく仕事に影響するため、労働能力喪失率が基準よりも高く判定されることがあります。
また、後遺障害を原因として下記のような事が生じたことを主張するのが逸失利益の増額を要求するポイントといえます。
また、会社員でも実際の給与が「賃金センサスの平均賃金よりも低い場合」は、賃金センサスの平均賃金を基礎として算定できる場合があります。
賃金センサスは逸失利益を計算する際に、利用することが多いので、下記記事などを参考にしてください。
自営業者の場合も、後遺障害が実際の仕事にどれだけ影響しているのかを適切に主張することが、逸失利益を算定するうえでとても重要になります。
例えば、店舗を経営している方などは、事故が原因で「店を閉める」ことになれば、多額の逸失利益が認められる可能性があります。
なお、自営業者の基礎収入は、前年度の「確定申告書に記載がある所得額」を基に計算します。
そのため、確定申告をしていなければ、仮に多くの収入があったとしても、公に証明することができないので、基礎収入を「賃金センサス」を参考に計算するケースもあります。
公務員の場合も基本的な考え方は会社員と同じで前年の給与収入がベースとなります。
ただ、公務員の場合は民間企業よりも事故の影響で減収を招くような配置転換は起りにくく、職場からの配慮が受けやすい環境にあるため、「実質的な減収が発生しにくい」という特徴があります。
そのため、実際の労働能力喪失率よりも「制限」されるケースがあります。
ただし、近年では、被害者保護から公務員にも逸失利益を認めた裁判例が多くみられるようになってきています。
被害者が無職であっても「労働意欲があり、就労する蓋然性」が高ければ、逸失利益が認められる可能性があります。
裏を返せば、ニート・引きこもり等の状況にあり、全く求職していなければ、逸失利益が認められない可能性が高いです。
特に、被害者が高齢者であれば、就労可能性が相対的に低いため、逸失利益の請求は難しくなります。
なお、無職者の基礎収入は、「賃金センサス」「失業前の収入」を基準に計算することが一般的です。
事故前に、就職が決まっていた場合などは「内定先の給与」なども考慮されます。
社長や会社役員の場合は、現場で直接仕事をするというよりは、デスクに座って指示を出すことが多いため、むち打ち症程度の後遺障害では仕事にほとんど影響はないでしょう。
したがって、実質的に減収が生じていなければ、後遺障害逸失利益が認められないことになります。
なお、会社役員の基礎収入は、原則として「労務対価部分」のみを指しています。
主婦自体は金銭を稼ぎ出す労働ではないため、一見すると逸失利益はないようにも感じますが、たとえ専業主婦の場合でも家事労働を労働力と考えて逸失利益を請求する事ができます。
この際の基礎収入は「賃金センサス女子労働者全年齢」または「年齢別平均」の金額をベースにして計算をします。
なお、パート収入のある主婦の場合については、パート収入を基礎収入として計算することもあります。
ただ、パート収入が「賃金センサス女子労働者」の金額より低い場合は、「賃金センサス女子労働者」の金額をベースに計算します。
18歳未満の子供や学生の場合は、就業可能年数を18〜67歳までを就労可能とみなして「49年間を就労可能年数」として計算することがポイントです。
基礎収入は原則として「賃金センサス男女別全年齢平均賃金」をベースに計算し、進学が確実な高校生や18歳以上の大学生の場合は「賃金センサス男女別学歴別平均賃金」をベースに計算します。
後遺障害の逸失利益の計算式や計算方法、職業別の早見表、逸失利益の自動計算機などを解説致しました。
交通事故に遭うと「慰謝料」という損害賠償の一部に目が行きがちですが、後遺障害が認定されるような怪我をした場合、逸失利益も加害者側に請求する必要があります。
適切な逸失利益を請求するには、交通事故に強い弁護士に相談するのが一番です。
特に「減収が発生はしていないが、特段の事情で仕事に悪影響」が出ている方は、交通事故の逸失利益に強い弁護士に一度相談してみるといいでしょう。
本サイトには全国の交通事故に強い弁護士を掲載しております。お近くの弁護士を探して、無料相談してみましょう。