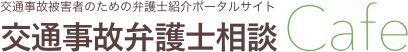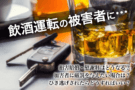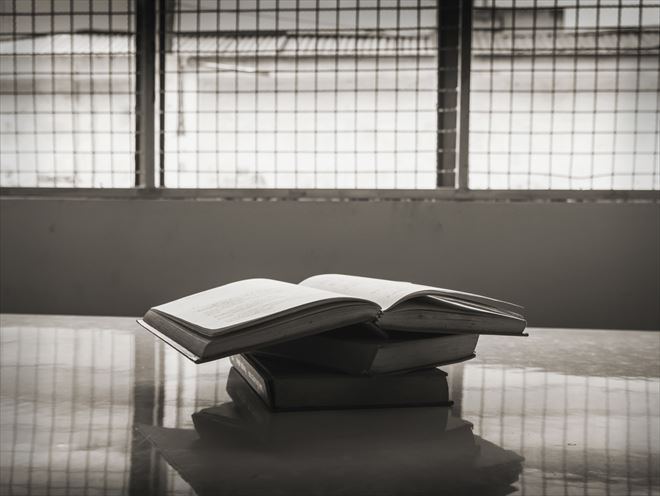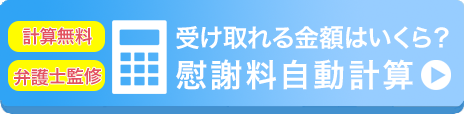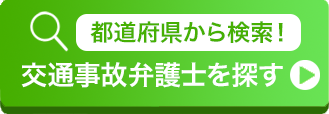目の前で交通事故!現場に居合わせた人に法律上の責任はある?
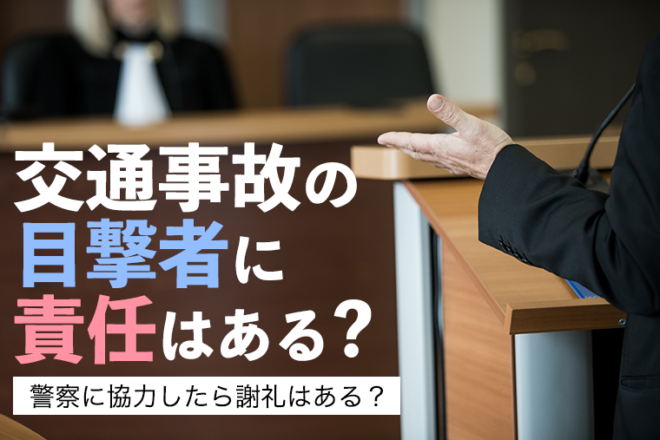
たまたま交通事故の現場に遭遇してしまった場合、倒れている被害者を助けたり、警察の捜査に協力したりするべきか、それとも見なかったことにしてスルーしてしまおうか、決断がつかないことがあります。
誰しも、わずらわしいことに関わりたくない気持ちがありますから、目の前で交通事故があっても、スルーすること自体、一概に責められるべきことではありません。
ただ、次のような疑問を持つ方は多いと思います。
- 目の前でおきた事故である以上、被害者を助けなくてはいけない法的な義務があるのではないか?
- 目撃者である以上、警察の捜査に協力する法的な義務があるのではないか?
- 素通り・スルーしてしまうと義務違反として、処罰されるのではないか?
そこで、この記事では、交通事故の現場に居合わせた第三者に法的な責任が発生するのかどうか、仮に進んで警察の捜査に協力する場合には、どのような流れになるのか?などについて解説いたします。
目次
交通事故が起きた際に「運転者」に課される義務とは?
まず、交通事故現場において、事故車両の「運転者」に課されている法律上の義務について確認しておきましょう。
事故車両の運転者には、以下の義務があります。
- 救護・危険防止措置義務(道路交通法第72条1項前段)
①直ちに運転を停止し、②負傷者を救護し、③道路における危険を防止する等必要な措置を講じる義務がある - 報告義務(同法第72条1項後段)
直ちに警察官または警察署に交通事故を報告する義務がある - 警察官からの滞留命令に従う義務(同法第72条2項)
報告を受けた警察官は、負傷者の救護と危険防止にために必要なときは、報告をした運転者に対して、警察官が現場に到着するまで、事故現場を立ち去ってはならないと命令することができ、運転者はその命令に従う義務がある
上に説明した各義務は、事故車両の「運転者」に課された義務です。
交通事故に居合わせた目撃者など「第三者」に課される義務があるの?
事故を「目撃した人」や、たまたま通りすがった「通行人」などの第三者には何らの義務も課されていません。
目の前で事故が起き、人が怪我をして倒れていれば、助けてあげるのが人として当然の行動でしょうが、それは法律で強制される義務ではないのです。
したがって、何もせずに事故現場を立ち去ったからといって、何らかの罰則を受けることはありません。
警察の捜査に協力する義務はないのか?
警察・検察は、交通事故の当事者以外の者についても、参考人として、事情聴取を行うことができますが、それはあくまでも任意の捜査であって強制力はありません(刑事訴訟法197条1項、223条)。
したがって、目撃者など第三者には、警察・検察の捜査に協力する義務は一切ありません。協力を求められても、これに応じるか否かは自由に決めることができます。協力しないからといって、処罰されることはありません。
警察の捜査に進んで協力した場合はどうなるのか?
目撃者は、捜査に協力する義務はありませんが、要請に応じて協力することも自由です。
例えば、目撃者の場合、具体的には、次のような協力をすることになります。
① 事故現場での事情聴取
まず、事故状況の概要を警官に説明するよう求められます。多くの場合、現場のパトカー内で話しをすることになるでしょう。
② 事故現場での実況見分で立会人として指示説明
次に、通常、事故現場において事故状況を記録する実況見分が行われます。
例えば、「車が衝突した地点はここ」、「人が倒れていた場所はここ」などと記録するわけですが、それは当事者や目撃者の説明に基づいて記録されてゆきます。これを立会人の指示説明と呼び、交通事故事件においては刑事責任、民事責任を左右する重要な証拠となります。
③ 後日、警察署、検察庁での事情聴取と供述調書の作成
後日には、改めて警察署から要請があり、警察署において再度、事情聴取をされ、目撃した状況を説明する供述調書へのサインと指印を求められます。
通常は警察署への出頭は1度ですが、当事者が事故態様を争っているような事案では、複数回の出頭が必要なときもあります。
また、警察署の後に、それとは別に検察庁からも要請があり、検察庁において検察官から事情聴取をうけ、同様に供述調書へのサインと指印を求められます。
検察庁への出頭も通常は一度きりですが、警察署と同様に、事件の内容によっては複数回呼ばれるケースもあります。
④ 公判廷で証人として証言
交通事故の加害者が起訴され、公開の法廷における正式な刑事裁判が開かれることになった場合に、検察側が目撃者の供述調書を証拠として申請したところ、弁護側が、これを証拠とすることに同意しなかったときには、検察官から証人として公判廷で証言してほしいと要請される可能性があります。
これに応じる場合、通常は、裁判前に1~2度、その交通事故事件の公判担当検事のもとに出頭して、証言する内容の打ち合わせが行われます(「証人テスト」と呼ばれます)。
そして公判廷で検察官からの主尋問、弁護人からの反対尋問、裁判官からの尋問に答えて証言することになります。
検察官に要請されただけの段階なら、証人となることを拒否できる場合もあります。非協力的な者を証人としても、有利な証言をしてもらうことは難しいと考えて、検察官が事実上あきらめてくれることも多いからです。
裁判所への出頭を拒否できないことも
しかし、目撃者が拒否をしても、検察官がどうしても必要な証人と判断して裁判所に証人申請し、裁判所が採用を決定すれば、もはや出廷を拒否することはできません。
出頭を拒む恐れがあると判断されると、裁判所は出頭を命ずることができます。これを「召喚」といいます(刑訴法143条の2)。
召喚したのに正当な理由なく出頭しないときは、10万円以下の過料や、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(刑事訴訟法150条、151条)。
さらには、必要があれば、裁判所に勾引状を発せられて、強制的に身柄を拘束されて出頭させられてしまいます(刑訴法152条)。
宣誓・証言を拒んだ・虚偽の証言をしたときには刑罰がある
そして証人として出廷した以上は、虚偽を述べないという宣誓を強制されます(刑訴法154条)。宣誓や証言を拒んだときは正当な理由がない限り、10万円以下の過料や、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(刑訴法160条、161条)。
さらに宣誓したにもかかわらず、自身の記憶に反する虚偽の事実を証言したときは、偽証罪として3月以上10年以下の懲役刑となる危険があります(刑法169条)。
以上のとおり、事件の内容によっては、捜査機関や裁判所に何度も足を運ばざる得ないことになり、一定の法的義務も負うことになります。
したがって、捜査に協力することは望ましいこととはいえ、あまり安易な気持ちで捜査に協力することはお勧めできません。
交通事故の目撃情報を警察に提供した場合、謝礼はもらえるのか?
目撃情報を警察に提供すると、数千円程度の謝礼をもらえる場合があります。
警察には、「捜査費」と呼ばれる捜査のための諸雑費、諸経費として使える金銭があり、捜査協力者・情報提供者に対する謝礼を支払うことができるとされています。
もちろん、現場の捜査官が勝手に支払うものではなく、事前または事後に責任者の決裁を受けるもので、やましいお金ではありません。
どのような場合に、幾らが支払われるのか、基準が公表されているわけではありませんから、詳細は不明ですが、交通事故の目撃者が警察の要請に応じて事情聴取を受け、供述調書の作成にも応じた場合に、数千円程度の謝礼を提供されたという報告が散見されています。
ただし、捜査機関の裁量で支払われるものですから、捜査に協力したからといって請求する権利があるというものではありません。したがって、謝礼を目当てに協力するのは、お勧めできません。
まとめ
交通事故の現場に居合わせたとき、救助や捜査に協力するべきかどうか、とっさに判断しなくてはなりません。その際は、上の記事を思い出して決断してください。
また、捜査に協力して、警察署や検察庁、さらには裁判所への出頭を要請されて不安を感じる方は、裁判の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。