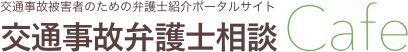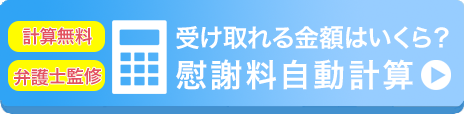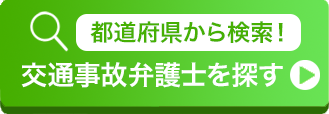交通事故の慰謝料は1000万を超えることはあるのか?

交通事故で怪我をした被害者に対しては、加害者や保険会社から慰謝料というお金が支払われます。慰謝料は、被害者が被った精神的苦痛に対して支払われるお金ですが、事案によっては、1000万円を超える慰謝料が支払われることもあります。
このような高額な慰謝料が支払われるのはどのような事案なのでしょうか。また、1000万円を超える慰謝料が生じる事案ではどのような点に注意すればよいのでしょうか。
この記事では、交通事故の慰謝料が1000万円を超えるケースや1000万円を超える慰謝料を請求する場合の注意点などについて解説します。
目次
1.交通事故の慰謝料には3つの種類がある
交通事故の慰謝料には、主に以下の3種類の慰謝料があります。
(1)傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料とは、交通事故で怪我をした被害者に対して支払われる慰謝料です。人身事故であれば必ず発生する慰謝料です。
傷害慰謝料は、入通院期間や入通院実日数などに応じて計算をすることになりますので、「入通院慰謝料」と呼ばれることもあります。
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ってしまった被害者に対して支払われる慰謝料です。
交通事故で怪我をした場合には、怪我の治療のために通院をしますが、怪我の内容や程度によっては、通院を継続しても症状の改善が見込めないものもあります。これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことを「症状固定」といい、症状固定時に残存している障害については、後遺障害等級認定を受けることができます。
後遺障害等級認定の手続きでは、第1級から14級までの等級が定められており、具体的な症状に応じて等級が認定されます。
(3)死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で死亡した被害者が被った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。死亡慰謝料には、死亡した被害者本人に認められる慰謝料と被害者の遺族に認められる慰謝料の2種類があります。
交通事故によって被害者は死亡していますので、被害者本人に認められる慰謝料については、相続人である遺族が代わりに請求していくことになります。
2. 交通事故の慰謝料の計算方法
(1)慰謝料の3つの算定基準
実際に慰謝料の金額を計算する前に、慰謝料の算定方法には3種類あることを知っておく必要があります。
- 自賠責保険基準とは、自賠責保険会社が慰謝料を支払う際の基準です。
- 任意保険基準とは、任意保険会社が慰謝料を支払う際の基準です。
- 裁判基準とは、弁護士の示談交渉または裁判で慰謝料を計算する際に利用される基準です。
任意保険基準は一般には公表されていないため、以下では、自賠責保険基準および裁判基準に基づいた慰謝料の計算方法について説明します。
(2)各慰謝料の計算方法
交通事故の各慰謝料は、以下のような方法で計算をします。
①傷害慰謝料(自賠責基準の計算法)
自賠責保険基準では、以下の2つの計算方法のうち、いずれか少ない方を採用します。
- 4300円×実通院日数の2倍
- 4300円×通院期間
例えば、実通院日数の2倍のほうが少ないとして、360日とします。
そうすると、単純計算で360*2*4300=309万6000円となり、1000万円には程遠いことがわかります。
②傷害慰謝料(裁判基準の計算法)
次に裁判基準の計算方法です。
こちらは、入通院期間を基準に、以下の「表」に基づいて計算をします。
裁判基準での傷害慰謝料は、基本的には別表Ⅰを利用し、むちうち症で他覚所見がない場合などは別表Ⅱを利用します。
(別表Ⅰ)
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 |
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | |
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | ||
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | |||
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | ||||
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
(単位:万円)
(別表Ⅱ)
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | |
| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | ||
| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | |||
| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | ||||
| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
(単位:万円)
上表を見ても分かる通り、入通院慰謝料では1000万円を超えることは原則ないことがひと目でわかります。
③後遺障害慰謝料の計算法
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて、以下のように算定されます。
| 等級 | 後遺障害慰謝料の金額 | |||
| 自賠責保険基準 | 裁判所(弁護士)基準 | |||
| 別表第1 | 1級 | 1650万円 | 2800万円 | |
| 2級 | 1203万円 | 2370万円 | ||
| 別表第2 | 1級 | 1150万円 | 2800万円 | |
| 2級 | 998万円 | 2370万円 | ||
| 3級 | 861万円 | 1990万円 | ||
| 4級 | 737万円 | 1670万円 | ||
| 5級 | 618万円 | 1400万円 | ||
| 6級 | 512万円 | 1180万円 | ||
| 7級 | 419万円 | 1000万円 | ||
| 8級 | 331万円 | 830万円 | ||
| 9級 | 249万円 | 690万円 | ||
| 10級 | 190万円 | 550万円 | ||
| 11級 | 136万円 | 420万円 | ||
| 12級 | 94万円 | 290万円 | ||
| 13級 | 57万円 | 180万円 | ||
| 14級 | 32万円 | 110万円 | ||
ここで、ようやく1000万円を超える金額が出てきたこと分かります。
例えば後遺障害7級に認定され慰謝料を裁判基準で計算した場合は1000万円の慰謝料となります。
④死亡慰謝料の自賠責基準の計算法
死亡慰謝料の場合、以下のとおりとなります。
(被害者本人の死亡慰謝料)
| 被害者本人の死亡慰謝料 | 400万円 |
(被害者の遺族への死亡慰謝料)
| 慰謝料請求権者が1人 | 550万円 |
| 慰謝料請求権者が2人 | 650万円 |
| 慰謝料請求権者が3人以上 | 750万円 |
| 被害者に被扶養者がいるとき | 上記に加えて200万円 |
⑤死亡慰謝料の裁判基準の計算法
| 被害者が一家の支柱である場合 | 2800万円 |
| 被害者が母親、配偶者である場合 | 2500万円 |
| その他 | 2000~2500万円 |
ちなみに、裁判基準では、被害者本人の死亡慰謝料と遺族への死亡慰謝料を合計した金額となっています。
3. 交通事故の慰謝料が1000万円を超えることはあるの?
交通事故の慰謝料が1000万円を超えることはあるのでしょうか。
(1)傷害慰謝料だけでは1000万円を超えるのは難しい
自賠責保険基準では、実通院日数や通院期間に応じて、傷害慰謝料の金額が算定されますが、治療費、休業損害、傷害慰謝料などを含む傷害に対する支払限度額は、被害者1人につき120万円とされています。
また、裁判基準では、自賠責のような上限はありませんが、上記の別表Ⅰおよび別表Ⅱからもわかるように1000万円を超えるような傷害慰謝料が生じるケースはほとんど存在しません。
そのため、傷害慰謝料だけで1000万円を超えるのは難しいといえるでしょう。
(2)慰謝料が1000万円を超える可能性のあるケース
慰謝料が1000万円を超える可能性のあるケースとしては、以下のケースが挙げられます。
①重度の後遺障害が残ったケース
裁判基準では、後遺障害等級が7級で1000万円の後遺障害慰謝料となります。そのため、7級よりも重い後遺障害が残ったケースでは、慰謝料が1000万円を超える可能性があります。
後遺障害等級が7級よりも重いものの例としては、以下のものが挙げられます。
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(第1級)
- 両手の手指の全部を失ったもの(第3級)
- 1上肢を手関節以上で失ったもの(第5級)
- 外貌に著しい醜状を残すもの(第7級)
②被害者が事故によって死亡したケース
被害者が事故で死亡したケースでは、裁判基準によれば、被害者本人の死亡慰謝料と遺族への死亡慰謝料を合わせて、最低でも2000万円の慰謝料が支払われます。
そのため、被害者が事故によって死亡したような事案では、1000万円以上の慰謝料が支払われる可能性が高いといえます。
4. 1000万円を超える慰謝料を請求する場合の注意点
慰謝料だけで1000万円を超える事案については、以下の点に注意が必要です。
(1)弁護士に示談交渉を依頼する
交通事故の慰謝料には、3つの算定基準があり、どの基準を利用するかによって、慰謝料の金額は大きく変わってきます。被害者にとって最も有利になる基準は、裁判基準ですが、裁判基準と利用することができるのは、弁護士に示談交渉を依頼した場合に限られます。
1000万円を超える慰謝料を請求する場合、弁護士に依頼するかどうかによって、最終的に支払われる慰謝料額は2倍以上の差が生じることもあります。少しでも有利な条件で示談するためにも、示談交渉は弁護士に依頼して行うべきでしょう。
(2)適切な後遺障害等級認定を受ける
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて算定されます。
後遺障害等級認定は、適切な検査を行い、適切な資料を提出できたかどうかによって、認定される等級が異なってくることがあります。後遺障害等級認定の手続きを加害者の保険会社に任せていては適切な後遺障害等級の認定を受けることはできません。
多少面倒でも適切な後遺障害等級認定を受けるためには、被害者請求という方法により、被害者自身が行うべきです。
5. まとめ
交通事故の慰謝料が1000万円を超えるのは、重度の後遺障害が残った事案や被害者が死亡した事案です。
このような事案では、慰謝料以外にも逸失利益や将来介護費などの請求により、賠償額が高額になる傾向にあります。
適切な賠償額を受け取るためにも専門家である弁護士のサポートを受けながら進めていくようにしましょう。