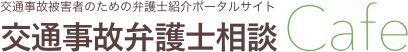子供の事故を防ぐには・起こさないための対策は|子供を交通事故から守る!

ご両親のお考えとして、子供の事故を防ぐにはどうすればよいか、起こさないための対策はなにかないのかと考える方もいらっしゃるでしょう。
4月には、お父さん、お母さんが心待ちにしていたお子さんの小学校入学があり、またそれと同時に、幼稚園や保育園とは違って、小学校の登下校はお子さんのみとなります。
ここでは、子供たちを交通事故から守るために、親ができる対策と注意点、事故から子供を守るために何をすればよいかについて解説していきます。
目次
子供の交通事故は小学1年生の6月~7月が要注意
小学生の交通事故は、4月よりも5月~7月に増える傾向があることをご存知でしょうか?
特に、小学生が一番交通事故に遭うのは6月なのです。また、学年は、小学1年生が一番交通事故被害に遭っています。
友達が増えて活動範囲が増える、無事に小学校に慣れてきて親も油断するなどが原因ともいわれます。
また、入学祝いに自転車を送られるご家庭も多いでしょうから、4月、5月で自転車運転に慣れ、ひとりで自転車に乗れるようになって、6月に交通事故に遭ってしまうことも十分に考えられます。
特に、慣れが生じる頃には、子供に交通事故には気をつけることを教える家庭内教育が重要になると言えます。子供の事故を防ぐには、こういった慣れが生じる手前がタイミングと言えるでしょう。
子供の交通事故の特徴や統計、事例
子供が歩行中の交通事故には、以下のような実態・統計・事例があります。
- 小学1年生が最も多く被害に遭っている。
- 小学1年生の交通事故は6月が最も多く、小学生全体で見ても6月が最も多い。
- 登下校時間帯となる7~8時、14~17時の交通事故が多い。
- 道路横断中の事故が多い(子供の事故全体の79%)。
- 小学生側に違反があることも多く、「飛び出し」が最も多い。
- 自宅から500メートル以内での事故が最も多い(全体の68%)。
小学1年生のお子さんをお持ちのご両親は、特に注意が必要です。子供の事故を防ぐには、こういった点の理解も大事です。
子供は「飛び出し」事故に要注意
次に、子供の交通事故を種類別に見てみましょう。
小学生の歩行中死傷者
平成27年の小学生の歩行中死傷者は、全国で520人にのぼりました。
| 飛び出し | 35% |
|---|---|
| 横断歩道外横断等 | 10% |
| 路上遊戯 | 3% |
| 信号無視 | 2% |
| 車両の直前直後 | 3% |
| 斜め横断 | 2% |
| その他の違反 | 3% |
| 違反なし | 42% |
一番多いのが、急な飛び出しによる交通事故です。
「止まる」「見る」「待つ」という言葉を、親が何度も子供に伝えるのが、子供の事故を防ぐためにも、お子さんを交通事故から守るコツといえます。
「止まる」
『赤信号は、止まる。』
信号は、大人を意識した配置になっており、子供の目線では見え難い場合もあります。
子供の視線に合わせて、どこをどう見て判断して止まるべきなのか、しっかりと教えてあげるのは親の務めです。
「見る」
「信号機」、「歩行者」、「自動車」、「自転車」など、一度に多くのものを見る習慣を持たないといけません。
特に、交差点は四方向から自動車が動いてきます。左右前後を確認することを、親が実践で教える必要があります。
信号機が「青」だから、といって油断もできません。
最近は、赤信号でも平気で横断歩道に飛び込んでくる、暴走自転車が多数います。
信号機→「赤」→「青」に変更時への飛び出しも、非常に危険ですから、「青」になっても、左右前後を確認してから、ゆっくりと横断歩道を渡るように習慣づけをしましょう。
「青」→飛び出しは危険です。
「待つ」
注意点として「信号機がないような交差点」では、車を先に行かせるように待つ習慣を親として教えていくことも重要です。
特に、朝の通勤時間帯は、焦っている車が多いのも事実です。
小学生が不慮の事故に巻き込まれないためにも、「待つ」姿勢はとても重要です。
登校前に子供を事故から守る親としてできること
親が言ってしまいがちなこととは?
親は、朝、慌てて以下の様なことを言いがちです。
- 「急いで学校へ行きなさい!」
- 「遅刻しちゃうよ、走って行きなさい!」
こういった場合、子供が心理的なストレスを受けて、回りを見る余裕がなくなってしまいます。
急がせると、子供が動揺し、交通事故の原因となることがあります。子供の事故を防ぐためにもこの点の理解が重要です。
起床の工夫こそが大事なこととは?
親としてできることとしては、余裕を持った時間に子供を起床させるようにしましょう。
そして、時間にゆとりをもって、笑顔で小学校へ送り出しましょう。
子供を交通事故から守るためには、親の細かな心遣いの積み重ねが大切であることを忘れてはなりません。
事故を起こさないための対策|子供の自転車運転の注意点
また子供の場合、自転車に慣れてくる時点で事故防止のためになんらかの対策が必要です。事故を起こさなないための対策が必要です。
自転車に乗るようになった小学生は、自転車を運転中の事故にも十分に気をつけなければなりません
車道寄りの歩道を走る
平成27年6月1日から、道路交通法の改正が行われ、自転車走行に対する規制がさらに強化されたりしましたが、原則、自転車は車道通行が原則です。
ただ、子ども(13歳未満)が自転車に乗るときは、歩道を走ることが可能です。
歩行者が多いときは、自転車から降りて、押して歩くように教えましょう。
特に、高齢者と小学生との自転車の接触事故が増えています。小学生が加害者となってしまい、高額な慰謝料が発生するおそれもあります。
交通ルールを守る
以下の交通ルールをしっかり教え、守るように指導しましょう。
- 二人乗りは厳禁
- 自転車で並んで走ることはやめる
- 周りが暗くなったら、必ずライトをつける
- 信号を守る
- 一時停止標識/前方優先道路一時停止を守る
ヘルメットの着用
保護責任者は、小学生・幼児に乗車用ヘルメットを被らせるように努めましょう。
万が一の時、ヘルメットがあるかないかでは、怪我の度合いが全く違ってきます。
自転車保険に加入する
自転車に乗ると、たとえ子供であっても交通事故加害者にもなり得ることを忘れてはなりません。
特に、高齢者と子供の乗る自転車が衝突する事故が増えています。高額な賠償請求訴訟が起きるケースもありますので、念の為、自転車保険に入っておくことを強くおすすめします。
自転車運転は、「個人賠償責任保険」に入るケースが多いです。また、個人賠償責任保険は、単独では加入できないため、火災保険や自動車保険、共済や損害保険、自転車保険などの特約で加入します。
示談代行サービスがついているかどうかの確認も必要です。ご自分で示談交渉をするよりは、保険のプロに任せたほうが、相場にあった示談交渉が行えます。
最近は、学校で自転車保険加入の案内がされたり、家族で個人賠償責任保険に加入したりするケースが増えてきています。
まとめ
事故を起こさないための対策と、子供の事故を防ぐにはどうすればよいのかを解説しました。
子供の交通事故は、両親の家庭での教育によって防げるものも少なくありません。
特に、家の500m近くで事故が多く発生していることを考えると、普段から、「この交差点は危ないよ」といった会話をすることで、交通事故はある程度自然に予防できるものだといえます。
また、自転車乗車時は、加害者になる可能性もあることを考え、スピードを出しすぎない安全運転ができるように、両親がよく指導することが、交通事故を起こさないポイントになります。