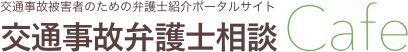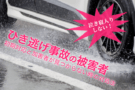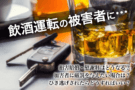居眠り運転事故してしまった!免許取り消し?点数・罰金などを解説

- 居眠り運転してしまったら、免許取り消しになるの?バレるの?
長時間車を運転していると、どうしようもない眠気に襲われることがあります。
特に、直線が長い東名高速道路や東関東自動車道、東北自動車道、関越自動車道などについては、カーブが多い首都高速や中央自動車道よりも眠くなりやすい傾向があります。
では、居眠り運転してしまったら、どのように対処すれば良いのでしょうか。居眠り運転していた相手にはどの程度の過失が認められ、免許取り消し、罰金や違反点数などの罰則はどうなるのでしょうか。
また一方で、居眠り運転をしている車の交通事故に巻き込まれてしまった場合はどうなるのでしょうか。今回はYahoo!知恵袋やTwitterでも話題の居眠り運転事故について解説致します。
目次
居眠り運転とは?
居眠り運転とは、通常、寝ながら運転することは不可能に感じますが、運転している間につい眠くなってしまい、走行しながら眠ってしまう事を言います。
居眠り運転で事故を起こした場合、加害者の側には通常1〜2割程度の過失割合が加重されます。
また、居眠り運転が「過労運転」と判断されれば、罰金・点数のペナルティの他に、刑事罰が科される可能性があります(以下、後述します)。
しかし、居眠り運転により交通事故が起きたとして、それが居眠り運転によるものだったと客観的に指摘できるのか、という疑問があります。バレるの?バレないのでは?ということです。
居眠り運転はバレる?していたか判断が難しい理由とは
運転中に居眠りをしていたかどうかについては、運転していた本人、または同乗者にしか分かりませんので、バレないのではと思う方もいるでしょう。
白バイが不審な車を見つけて、居眠りしているところを横付けして確認でもしない限りは、他人が居眠り運転を指摘することは極めて難しいと言えます。
そのため、例えば居眠り運転をしていて電柱に激突したとしても、現場に来た警察官に「よそ見をしていた」と証言すれば、前方不注意として「安全運転義務違反」となる可能性が高いです。
また、仕事で疲れきった状態で運転していたり、病気や薬などによって運転をするのが危険な状態にある状態で運転していたりした場合は、「過労運転」と判断されます。
発見された当時「客観的に見ても意識が朦朧」としていたり、薬を服用していたなどの証拠が揃ったりすると、過労運転として取り締まられる可能性が高いでしょう。
居眠り運転していたか立証するのが難しい理由はそのためです。
居眠り運転で言い訳・記憶なし・嘘なら、過失割合が変わる?
もし居眠り運転によって交通事故が起きた場合、加害者側の過失割合が100になるかというと、必ずしもそうではありません。
たとえば、居眠り運転によるセンターラインオーバーの衝突事故だった場合はどうでしょうか。
居眠り運転をしていた側が悪いのは当然ですが、先述の通り、居眠り運転の場合は通常1〜2割程度加害者の過失割合が加重されます。
しかし、被害者側にも、衝突を回避するチャンスがあった可能性は否めません。そうなると、被害者側にも一定の過失割合が認定されることがあります。
このように、万が一、事故の相手方が居眠り運転をしていたとしても、被害者側に過失がついてしまう可能性があります。
また、加害者が居眠り運転を認めず、居眠り運転による過失割合の修正がされないまま示談交渉が進んでしまう可能性もあります。実際、事故直後は居眠り運転を認めていても、後になってから言い訳として「記憶がない」と主張を覆したり、嘘をつく加害者はいるようです。
居眠り運転の罰金と点数
居眠り運転に関する明確な定義はなく、居眠り運転について一律に罰金や点数が規定されているわけではありません。
居眠り運転による罰金や点数は、居眠りをしていた状況に応じて取り締まり方が変わってきます。
(1) 安全運転義務違反
安全運転義務違反は、道路交通法70条に次のように規定されています。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
安全運転義務違反となった場合、点数は2点となります。また、車両に応じて次のような反則金があります。
- 大型車:12,000円
- 普通車:9,000円
- 二輪車:7,000円
- 小型特殊車:6,000円
- 原付:6,000円
居眠り運転の場合も、事故発生後の本人の証言次第で、下記のいずれかで処理をされて安全運転義務違反となる可能性があります。
脇見運転
よそ見をして運転した場合です。
最近では、話題になったポケモンGOをスマホで操作しながら事故を起こしたケースがありました。
漫然運転
「ぼんやりと集中していない状態」で運転した場合です。
居眠り運転だったとしても、ぼんやりしていたと答えれば、漫然運転として処理される可能性はあるでしょう。
動静不注視
周りの動きをよく確認せずに運転した場合です。
通常、運転する際には周りの人や車の動きに注意して運転するのが当たり前です。ところが、「隣の車が発車したから青信号だろうと思って自分も発車したら、前の車に追突してしまった」といった場合、動静不注視となります。
いわゆる「~だろう運転」がわかりやすい例です。
安全不確認
周囲の安全確認を怠った場合です。特に曲がり角などについては、安全不確認による事故が多く発生しています。
安全速度
ここでいう安全速度とは、いわゆる制限速度とは違います。制限速度が60キロの道路だとしても、どんな場合でも60キロで走って良いわけではありません。
例えば、見通しが悪い交差点であれば、減速して安全確認しながら走行するのが当然です。状況に応じた適切な速度で走行していたかどうかがポイントです。
運転操作不適
ハンドル操作やブレーキ操作のミスがこれにあたります。また、最近よく話題になるアクセルとブレーキの踏み間違いについてもこれに該当します。
(2) 過労運転
違反点数も反則金も、安全運転義務違反であれば違反としては比較的軽いほうです。
ところが、一定の場合、居眠り運転が安全運転義務違反ではなく「過労運転」と判断される可能性があります。
過労運転とは
過労運転と聞くと、仕事で疲れて運転していたような状況をイメージするかもしれませんが、実はもう少しその範囲は広くなります。
道路交通法第66条で、過労運転は次のように規定されています。
何人も~中略~、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
このように、過労以外にも病気や薬などによって運転をするのが危険な状態にある場合は、法律で車を運転することが禁止されているのです。
みなさんの記憶に新しいところで言うと、2017年6月にお笑い芸人インパルスの堤下敦さんが、過労運転で書類送検されたのが有名です。このケースでは、睡眠薬を服用した状態で車を運転していたそうです。
これもある種の居眠り運転です。発見された当時、警察の問いかけに対して本人の意識が朦朧としていたため、過労運転として処分されたと考えられます。
過労運転の点数と罰金|一発免許取り消し
万が一、居眠り運転で過労運転として処理されると、違反点数は25点まで一気に跳ね上がります。
25点というと酒気帯び運転0.25以上と同じ点数ですので、過去に違反歴がなくても一発で免許取消しという極めて重い罰則となるのです。
また、点数とは別に道路交通法第117条2項2によって「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑事罰まで規定されています。これは、無免許運転と同等の刑事罰ですので、いかに過労運転が重い罪かがわかるかと思います。
過労運転と会社責任
もしも居眠り運転の原因が、過剰労働によるものだった場合、会社もその責任を問われるのか気になります。
基本的に刑事責任については、罪を犯した本人を罰しますので、当然に会社の社長が責任を負われるわけではありません。
ただ、道路交通法では、過労運転を禁止するとともに、同75条において、使用者が過労運転させることを命じたり、容認したりしてはならない(過労運転下命)とも規定しています。
万が一これに違反すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という、過労運転と全く同じ罰則が適用されます。
最近では、高速バスの運転手の過剰労働が問題になりがちなので、ドライバーを雇用している経営者の方も十分注意しなければなりません。
居眠り運転の事故の被害者は弁護士相談
一方、被害者はどうなるのでしょうか?
保険の観点は被害者の救済のため、被害者の方が、保険で示談金を支払ってもらえないということはありません。
しかし、先述の通り、過失割合などが食い違い、保険会社から提示される「示談金額が納得いかない」ものである可能性についてはありえます。
このような場合は、被害者については、交通事故に強い弁護士に相談して、正しい過失割合を検討し、示談交渉を代行してもらうことをおすすめします。
まとめ
今回は、Yahoo!知恵袋やTwitterでも話題の居眠り運転事故に遭ってしまった場合、記憶がないと嘘をつかれた場合、また、居眠り運転してしまった場合、免許取り消しになるか、などを解説しました。
居眠り運転の定義には明確なものがなく、一般の方がこれらの証拠を集めることは大変困難です。
ただ、例えば、事故現場の状況から、ブレーキ跡などを証拠として居眠り運転を立証できる可能性があります。また、加害者側の主張が一貫していないことなどを指摘するなどして、示談交渉から裁判まで進むこともあります。
被害者は、弁護士に依頼すれば、専門知識を活かして被害者のことを全面的にサポートすることが可能です。
居眠り運転の被害者となってしまった方は、どうぞお早めに弁護士にご相談ください。