交通事故の後遺障害とは|認定されたら?等級をわかりやすく解説【2024年版】
交通事故で後遺障害認定受けるために必要なことをご存知ですか?後遺障害とは何か、後遺障害として認定されるメリットやデメ…[続きを読む]
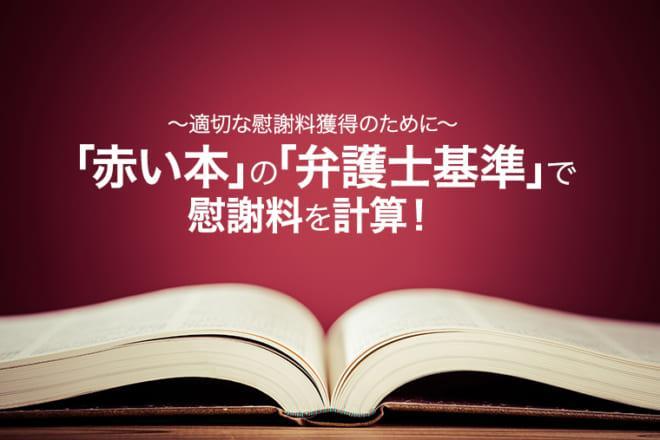
交通事故に巻き込まれ、加害者に対して慰謝料などを請求する際に問題となるのは、どのように賠償金を計算すべきかです。
この場合、役立つのが「赤い本」と呼ばれる資料です。この「赤い本」は、慰謝料などの損害賠償額に関する基準を提供し、裁判所での判断材料となります。
「赤い本」に記載されている慰謝料は、一種の指針である「弁護士基準」として使用されます。
ここでは、「赤い本」と同様に弁護士基準を示した「青い本」についても説明します。さらに、実際に「赤い本」の基準を使用して入院慰謝料を計算する方法と、それに関連する計算機についても詳しく解説します。
自身の入院慰謝料がいくらか、また保険会社が提示した金額が適正かどうかを知りたい方は、ぜひご一読ください。
目次
交通事故の「赤い本」は、損害賠償金の計算方法を掲載している書籍です。
たとえば、治療費、付添看護費用、入院雑費、介護費用、や休業損害、逸失利益、や慰謝料などについての法律的な考え方、相場、計算方法が簡便にまとめられています。
「赤い本」の、正式名称は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」です。「公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部」が編集・発行しています。
装丁の色が赤いので、わかりやすく「赤い本」とか「赤本」と呼ばれるようになり、今では、自ら「赤い本」と名乗っています。
赤い本は、裁判所で採用される交通事故の損害賠償金の計算方法が解説されており、これらは「弁護士基準(裁判基準)」と呼ばれます。
交通事故の損害賠償金の計算基準には、弁護士基準(裁判基準)と任意保険基準、自賠責基準の3種類があります。
弁護士基準は3種類の交通事故損害賠償基準のうち、もっとも高額になります。慰謝料を計算するときなどにも、弁護士基準を適用すると他の基準の2~3倍になるケースもみられます。
赤い本は、先述した通り、日弁連交通事故相談センター東京支部という弁護士の団体が編集発行している書籍ですが、実際には毎年、東京地裁民事交通部と意見交換しながら作成している基準なので「東京地裁の基準」と言って間違いありません。
弁護士が加害者の保険会社と示談交渉を進めるときに、弁護士基準を使用します。
そこで、以降は、赤い本の弁護士基準に従って、実際に入通院慰謝料の計算方法や相場を解説することにします。
下表は、2020年版の赤い本に掲載されている入通院慰謝料を算定する際に使用するチャートです。
別表Ⅰと別表Ⅱとがありますが、通常の怪我の場合は別表Ⅰを使用し、別表Ⅱは、他覚所見のないむちうち症や軽い打撲、軽い挫創の場合に使用します。
使い方は簡単です。通常の怪我で、通院のみ1ヶ月の場合28万円、通院5ヶ月、入院3ヶ月の場合204万円となります。
入通院慰謝料別表Ⅰ(単位万円)
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
入通院慰謝料別表Ⅱ(単位万円)
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
もちろん、これらは、それぞれの期間、入通院した場合のベースとなる基準額であり、実際の慰謝料については、事故態様や被害者の事情など様々な個別要因を勘案して決められます。
例えば、右腕を骨折して3ヶ月入院したケースと、右腕だけでなく同時に左腕も同様に骨折して3ヶ月入院したケースを並べて、同じ3ヶ月の入院期間だから入院慰謝料も同額という結論になるはずがありません。
期間を基準とするのは、おおよその目安が欲しいからであって、この表で機械的に数字が決まるのではないことに注意してください。
赤い本の別表の見方はわかりました。
しかし、普通、入院や通院が1カ月ピッタリで終了するわけではありません。では、端数が出た場合はどのように計算するのでしょう?
実は、入通院慰謝料の端数計算については、赤い本では示されていません。
赤い本で示されているのは、別表Ⅰ及びⅡの入通院慰謝料額が時間の経過ととも増加してゆく様を表す「グラフ」だけです。赤い本の立場は、月数に端数があるケースは、このグラフを使って、目分量で、適切な金額を選んでほしいというものです。
ただ、目安に過ぎなくとも、示談交渉や訴訟のやり易さという面では、はっきりした数字を算出できたほうが好ましいものです。
そこで実務では、ひとつの方法として、日割り計算して算定することが多いと言われています(※)。
※「交通賠償のチェックポイント」(弁護士高中正彦他編著・弘文堂)142頁。なお、同書籍でも、日割り計算が必ずしも正しい方法というわけではないと指摘しています。
例えば、通常の怪我で1ヶ月と24日通院した場合の入通院慰謝料を、この計算方法で計算してみましょう。
通院のみ1ヶ月と通院のみ2ヶ月の各慰謝料基準額は、上記別表Ⅰによれば次の通りです。
別表Ⅰ 慰謝料の基準額
| 通院のみ1ヶ月 | 28万円 |
|---|---|
| 通院のみ2ヶ月 | 52万円 |
2ヶ月めの30日間の金額は、52万円から、1ヶ月分の30日間の28万円を差し引いた金額と考えます。
2ヶ月目30日間の入通院慰謝料額
52万円 ー 28万円 = 24万円
この24万円を日割り計算し、24日間の入通院慰謝料を算出します。
2ヶ月目24日間の入通院慰謝料額
24万円 ÷ 30日 × 24日 = 19万2000円
19万2000円が、2ヶ月めの24日間の入通院慰謝料となります。
そして、1ヶ月を超えた24日分の通院慰謝料額を算出します。
1ヶ月を超えた24日分の慰謝料額
(52万円 - 28万円)× 24日/30日 = 19万2000円
これに、当初の1ヶ月分の入通院慰謝料28万円の基準額を加算して、通院のみ1ヶ月と24日分の入院慰謝料額とします。
通院のみ1ヶ月と24日の慰謝料額
28万円 + 19万2000円 = 47万2000円
では、入院した後に通院した場合は、どのように端数を計算するのでしょうか?
入院が先行した場合は、入院慰謝料の端数分は、前述と同様の日割り計算で求めますが、通院期間に端数がある場合は、通院慰謝料の日割り計算に少々工夫が必要となります。
入院後に通院したときの通院慰謝料の算出は、次の手順によります。
実際にやってみましょう。
「入院期間が1ヶ月15日」後に「通院期間4ヶ月12日」だった場合で、通常の怪我の場合を考えてみます。
慰謝料基準額
| 入院1ヶ月 | 53万円 |
|---|---|
| 入院2ヶ月 | 101万円 |
| 通院5ヶ月 | 105万円 |
| 通院6ヶ月 | 116万円 |
まず、入院1ヶ月15日(45日)分の入院慰謝料額を計算します。
入院1ヶ月15日(45日分)の入院慰謝料額
入院1ヶ月を超過した15日分の入院慰謝料額
(101万円- 53万円)× 15日/30日 = 24万円
入院1ヶ月15日(45日分)の入院慰謝料額
53万円 + 24万円 = 77万円
次に、入院当初から通院終了まで通算5ヶ月27日(177日)分の通算の通院慰謝料額を日割り計算します。
そこから、入院期間中45日分の通院慰謝料額を日割り計算して差し引きます。
177日(入院45日+通院132日)分の通院慰謝料額
105万円 +(116万円 - 105万円)× 27日/30日 = 114万9000円
入院45日分の通院慰謝料額
慰謝料基準額
| 通院のみ1ヶ月 | 28万円 |
|---|---|
| 通院のみ2ヶ月 | 52万円 |
入院45日分の通院慰謝料額
28万円 +(52万円 - 28万円)× 15日/30日 = 40万円
177日分の通院慰謝料額から入院45日分の通院慰謝料額を差し引く
114万9000円 ― 40万円 = 74万9000円
合計すると次の額となります。
入院1月と15日分の入院慰謝料77万円 + 通院4月と12日の通院慰謝料74万9000円 = 151万9000円
以上のように入院・通院期間に端数があっても日割り計算することで、入通院慰謝料の相場計算は可能です。
ただし、上の計算の考え方は、数字の理屈としては筋が通っていますが、慰謝料の金額は、理屈で決まるものではありません。したがって、上に挙げた計算も、あくまでも「このように考える例もある」程度に受け取ってください。
「赤い本」では入通院慰謝料について以下の留意点があります。
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2020年版」P.192より
このように「赤い本」では、入通院慰謝料が増減される例を挙げていますが、増減の要素がこれらに限定される趣旨ではないことはもちろんです。
実際の裁判例では、飲酒運転など加害者の悪質性、事故後の謝罪の有無、加害者の法廷での態度など、様々な要素が加味されるのです。
交通事故で後遺症が残り、治療をしても症状がこれ以上改善しない状態が、「症状固定」です。
症状固定後に残った症状が後遺障害であり、自賠責保険では、その程度によって、1から14級まで等級分けされています(これは自賠責保険から支払われる補償内容を決めるためです)。
最終的な賠償額を決める、赤い本の弁護士基準でも、この自賠責保険の等級を借用してによる後遺障害慰謝料を定めています。以下の通りです。
| 後遺障害の等級 | 赤い本の基準額 |
|---|---|
| 1級 | 2800万 |
| 2級 | 2370万 |
| 3級 | 1990万 |
| 4級 | 1670万 |
| 5級 | 1400万 |
| 6級 | 1180万 |
| 7級 | 1000万 |
| 8級 | 830万 |
| 9級 | 690万 |
| 10級 | 550万 |
| 11級 | 420万 |
| 12級 | 290万 |
| 13級 | 180万 |
| 14級 | 110万 |
例えば、追突事故で多いむち打ちでは、後遺障害等級12級に認定されれば290万円、14級に認定されれば110万円が後遺障害慰謝料の相場ということになります。
赤い本における死亡慰謝料は、以下の通りです。
被害者の家族での役割 赤い本の基準額
| 一家の大黒柱 | 2800万円 |
|---|---|
| 母親、配偶者 | 2500万円 |
| その他(独身者、未成年者など) | 2000万円~2500万円 |
「青本」といわれる本もあります。青本の正式名称は、「交通事故損害額算定基準」です。
こちらは「公益財団法人日弁連交通事故相談センター」の「研究研修委員会」が編集しており、同センターの本部が発行しています。青本は、装丁の色が全体に青いので、わかりやすく「青本」、「青い本」と呼ばれます。
赤い本と青い本の大まかな違いを下表にまとめてみました。
| 赤い本 | 青本 | |
|---|---|---|
| 発行 | 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部 | 公益財団法人日弁連交通事故相談センター本部 |
| 適用される裁判所の地域 | 東京(全国) | 全国 |
| 個別の解説 | 青い本に比べ少ない | 詳細 |
| 裁判例 | 豊富 | 赤い本に比べ少ない |
| 過失割合の基準 | あり | なし |
| 発行頻度 | 年1回 | 2年に1回 |
赤い本がどちらかと言えば法曹界の関係者向けに編集されているのに対して、青本は、どちらかと言えば一般の人も想定して編集されています。
その結果、青本は個別の解説が詳しく、一方で赤い本のほうが取り上げている裁判例が多いということになるわけです。
また、赤い本は、東京支部が発行しているので、東京地方裁判所の運用をまとめた内容になりますし、青い本の場合には、本部が発行しているので、より全国に適用しやすいよう幅をもたせた汎用的な内容になります。
しかし、最近では東京地裁の基準が広く一般で使われるようになってきているので、地方であっても赤本をそのまま使って問題ないケースが多くなっています。
赤い本と青い本では、慰謝料の計算方法が異なります。赤い本と青い本の入通院慰謝料の一部を抜粋すると、以下の通りです。
| 赤い本 (軽傷) |
赤い本 (通常程度の怪我) |
青い本 | |
|---|---|---|---|
| 通院1か月 | 19万円 | 28万円 | 16~29万円 |
| 通院3か月 | 53万円 | 73万円 | 46~84万円 |
| 通院6か月 | 89万円 | 116万円 | 76~139万円 |
| 入院1か月 通院3か月 |
83万円 | 115万円 | 73~136万円 |
| 入院2か月 通院6か月 |
133万円 | 181万円 | 122~225万円 |
上表からお分かりいただける通り、赤い本の場合には、各種の慰謝料の数字について、明確な基準となる1つの数値を定めています。一方、青い本の場合には金額に一定の幅を持たせています。
その理由は、赤い本が東京地方裁判所における運用を前提とするので、東京地方裁判所の基準を記載すれば足りるのに対し、青い本の場合には全国を対象としているので、物価などの地域差や各裁判所の運用状況に応じてある程度幅を持たせる必要があるからです。
青い本では、軽傷の場合は、この上下の幅の低い方、通常の怪我では、高い方の7~8割程度とされています。赤い本より、低めに設定されているといえるでしょう。赤い本は、物価・生活費・収入の高い首都圏を想定した基準だからです。
では、赤い本、青い本どちらを基準として保険会社と交渉すればいいのでしょうか?
どちらでもかまいません。被害者であるご自分に有利な数字が掲載されている方を使えば良いのです。どちらも目安に過ぎませんから、どちらを使わなくてはならないというルールなど一切ないのです。
地方の方が、赤い本を使ったからといって、おかしなことは全くありません。「東京の基準を使うのはおかしい」というのは、弁護士基準の意味を理解していない者の間違った言い分です。保険会社に騙されないようにしてください。
もっとも、被害者個人が、保険会社を相手に弁護士基準で交渉することが可能なのでしょうか?
残念ながら、被害者自身が相手側の保険会社と弁護士基準で交渉を進めようとしても保険会社が応じてくれるとは限りません。その場合、被害者が本気で弁護士基準の慰謝料を請求しようとすれば、裁判を提起するしかないでしょう。
しかし、弁護士に依頼すれば、保険会社に対して弁護士基準での交渉が可能です。弁護士は、交渉の先に訴訟を見据えています。裁判になれば弁護士基準で計算されますから、弁護士がついた以上、保険会社は、どうしても弁護士基準での交渉に応じざるを得なくなります。
赤い本、青本どちらを使って交渉するか以前に、弁護士基準で示談を進めたいのであれば、弁護士に依頼するのが一番の近道です。
ご自分の交通事故で「弁護士基準の慰謝料相場」を調べたい方は、「交通事故慰謝料の自動計算機」をご利用ください。
通院期間や後遺障害等級を入れるだけで、自分の慰謝料相場を弁護士基準で計算することができます。
また、これら慰謝料以外に、自分が加入している任意保険に人身傷害補償保険などが付帯していると受けられる補償があるので、以下の関連記事を併せてお読みください。
交通事故の被害に遭った時に慰謝料をできるだけ多くもらうためのポイントについて解説します。
弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士基準が適用される他にも、適正な過失割合を主張できることなどから、慰謝料を含めた賠償金が2倍や3倍になる可能性もあります。
弁護士が示談に介入しても相手の保険会社との間で合意ができない場合には、裁判によって弁護士基準を適用させることも可能です。
追突事故でむちうちの症状などが出て、慰謝料の計算方法などを知らないまま、被害者が自分で交渉をしてしまうと、適正な慰謝料での示談ができない可能性が高くなります。
交通事故の被害者の方が、加害者の保険会社と示談交渉を進めるときには、自分の判断で示談書に署名押印してしまう前に、交通事故に強い弁護士に相談をしましょう。