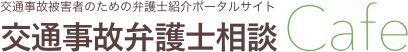免停回避!違反者講習の内容とメリット・デメリットを解説

交通違反を犯すと、運転免許証が一時的または永久に停止される可能性があります。しかし、違反者が運転能力を改善し、再び安全に道路を利用できるようにするために、違反者講習が提供されています。
違反者講習とは、交通違反を行った運転者に対して、交通ルールや安全運転に関する教育を受けさせるプログラムです。違反者講習は、違反行為を改善し、再び同様の違反が繰り返されることを防止することを目的としています。
軽微な違反行為を重ねて運転免許処分を受けてしまった方も、違反者講習を受けることにより免停処分を逃れられる可能性があります。
この記事では、違反者講習の対象者・条件や、違反者講習を受講するメリットとデメリット、点数はリセットされるのか、社会活動参加すべきか、コースはどっちが楽か、車で行くべきか、感想文の例文などについて解説いたします。
違反者講習の対象者・条件とは
違反者講習の内容の前にまず受けるためには次の3つの条件があるので解説します。
① 交通違反による累積点数6点
② 軽微な違反(違反点数3点以下)の累積
③ 過去3年間で違反者講習や停止処分者講習を受けたことがない
これらの条件を一つでも満たしていない場合は「違反者講習」を受講できず、「停止処分者講習(通称:免停講習)」を受けることになります。
ちなみに普通免許や原付免許など、免許の種類にかかわらず受講可能です。
それぞれの条件について具体的に説明いたします。
条件1:交通違反による累積点数6点
例えば、違反行為の例として
「一時停止すべきところで停止しなかった」
「シートベルトを締めなかった」
「夜間にヘッドライトを点灯させなかった」
「割込みを行った」
「信号無視をした」
「追い越し禁止の場所で追い越しをした」
「踏切で停止しなかった」
などがあります。このような比較軽微な違反を重ね、1点+2点+1点+1点+1点、あるいは2点+2点+1点+1点というように累積点数が6点に達すると、通常は30日間の運転免許停止処分の対象となります。
違反者講習の対象となるのは、このように交通違反による累積点数が6点に達した方です。
ただし注意しなければいけないのは、7点以上になってしまうと違反者講習を受けることはできず、免許停止処分者講習の対象となるという点です。
たとえば、1点、2点、2点、2点というように違反を重ねた場合は、累積7点となるので違反者講習を受けることができません。
条件2:軽微な違反の累積
「軽微な違反」とは違反点数3点以下のものをいいます。
たとえば、一般道路で時速30km以上35km未満の速度超過をした場合は違反点数6点となり、一発で免許停止の対象となります。
この場合累積6点で条件1は満たしていますが、「軽微な違反の累積」とはいえませんので、条件2を満たさず、違反者講習を受けることはできません。
条件3:2回目は可能?過去3年間の実績が重要
短期間の間に違反者講習を何度も受けて免停処分を免れるということはできません。
同様に過去3年間に免停処分を受けている場合も、違反者講習を受けることができません。
3年の期間が空けば、2回目の受講も可能となります。
違反者講習のメリット
続いて、違反者講習のメリットについて説明します。違反者講習のメリットは次の4つです。
メリット1:免許停止処分を回避することができる
最も大きなメリットは、言うまでもなく免許停止処分を回避することができる点です。対象者にもかかわらず、受けない場合は、自動的に免停30日となります。
特に仕事で車を運転しなければいけない方や、子どもの送り迎えや買い物などで日常的に車を運転することができる方は、条件を満たしている限り是非違反者講習を受けるべきです。
メリット2:講習後、点数がリセット!0に戻る
違反者講習を受けると、違反点数の累積はリセットされ0に戻ります。
たとえ講習後に違反をしてしまっても特別なペナルティがあるわけではなく、0点から加算されていくことになります。
メリット3:行政処分前歴がカウントされない。
「どうせ車なんてめったに運転しないから、免停になってもいいや」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、免許停止処分を受けると「前歴」が残ります。
講習を受けない場合は、前歴が残り、今後同じ内容の違反でも重い行政処分を受けやすくなります。
たとえば6点の違反をした場合、前歴がなければ30日の免停で済みます。
もしも前歴が1回あると、6点の違反をした場合90日の免停となってしまいます。
■参考記事
あと何点で免停?点数・期間・前歴の仕組みを徹底解説!
違反者講習を受けることにより前歴が残らなくなりますので、メリットは大きいと言えます。
メリット4:講習に車で行くことが可能
違反者講習は各地の免許センターで行われます。
「免許センターまで行くのが億劫」という方もいらっしゃいませんが、違反者講習は免停講習と異なり「車を運転することができない期間」がありません。
つまり、免停対象になったにもかかわらず、「会場まで車で行く」ことができます。
他方の免停講習は、たとえ講習を受けたことにより免停期間が1日に短縮されたとしても、その間は車を運転することができません。したがって、免停講習の会場まで車を運転していくと無免許運転となります。
違反者講習のデメリット・注意点
注意点1:料金がかかる
違反者講習を受けるためには料金がかかります。
料金はコースによって異なり、座学と「社会参加活動コース」の場合は9,950円、座学と「実車指導コース」の場合は14,100円です。
とはいえ、違反者講習を受けない場合でもその後違反を繰り返し、免停講習を受けなければいけなくなった場合には、免停期間によって約14,000円から28,000円の料金がかかりますので、違反者講習を受けた方が時間や費用の節約になるとも言えます。
注意点2:反則金はリセットされない
違反者講習を受けると、違反点数がリセットされます。
しかし違反者講習を受けない場合も、受けた場合も反則金がリセットされるわけではありません。
たとえば普通車で追い越し違反をした場合の反則金は9,000円ですが、この違反の内容に応じた反則金はしっかり納める必要があります。
注意点3:違反の事実は消えない
違反者講習を受けると前歴もつかず、違反点数の累積もなくなります。
しかし違反をしたという事実は消えません。つまり、次回の免許更新時に「優良運転者」の対象者(いわゆる「ゴールド免許」)になるわけではありません。
注意点4:通知書が来ない場合|いつ届く?
まれに対象者に当てはまっているはずなのに「通知書が来ない」方がいらっしゃるようです。
通常の場合は違反の日から2~3週間程度で届くはずですが、他県で違反した場合や祝日・年末年始などを挟む場合、また行政処分の手続きが遅れている場合などにより前後します。
違反者講習の内容
続いて、違反者講習の内容について解説いたします。違反者講習には座学と「社会参加活動コース」と座学と「実車指導コース」の2つがあります。どっちが楽か気になる方も多いようです。
座学は共通ですが、社会参加活動をするか、実車コースを受けるかは選ぶことができます。
座学
内容のまずひとつめとして、交通安全に関する講習が行われます。
運転中に注意すべきことや心構え、過去に実際に発生した事故の事例や、交通事故の発生状況などについて説明が行われます。免許の更新時に聞く講習のようなものをイメージして頂ければ分かりやすいでしょう。
社会参加活動・ボランティア
・交通安全のビラを配る
・歩行者に対する交通誘導
・放置された自転車の撤去作業などのボランティア活動
などの内容が講習にはあります。雨天決行ですので、雨具を持参するようにしましょう。
当然のことながら人目に触れることになりますので、恥ずかしいと感じる方は、少し費用が上がりますがこの後に説明する実車コースを選ぶとよいでしょう。
実車
受講者数名が1つのグループとなり、教習所のコースで教習車を使用して行われる試験です。
坂道発進、S字カーブ、方向転換、一時停止といった基本的な運転技術を有しているか確認が行われます。まった難しくありません。そのため、違反者講習のコースで、どっちが楽か考えることもないでしょう。
違反者講習はテストがあるの?
違反者講習の場合、免停講習とは違いテストのようなものは特にありません。
ただし感想文を書く時間があります。
感想文だけど、その書き方と例文ってある?
違反者講習では、最後に感想文を書く必要があります。これはテストではありませんが、空欄で提出することは認められません。
今回の違反者講習で学んだことや、反省文のように今後車を運転するにあたって気を付けたいことなどを簡潔に書くとよいでしょう。たとえば次のような内容です。
「私はスピード違反や一時停止違反を繰り返してしまい、今回違反者講習を受けることになりました。一つ一つの違反は些細なものだという認識でいましたが、ちょっとした違反が重大な事故に繋がりかねないことを座学を通じて学びました。また、社会参加活動としてビラ配りをすることで、交通社会の一員としての自覚を新たにしました。今後は同じような違反を繰り返すことがないよう、安全運転に十分に注意していきたいと思います。」
普段、文章を書かない人は意外とここにつまずきやすいようです。事前に感想文を家で書く練習をしておいてもよいでしょう。
最後に
違反者講習の内容とメリット・デメリット、感想文の例文についてお分かりいただけたでしょうか。
違反者講習はメリットが非常に大きいため、条件を満たしているのであれば積極的に受講を検討するとよいでしょう。