交通事故と民事裁判|保険会社に訴えられた!流れ・デメリット
交通事故が示談でまとまらない場合には、調停や裁判に移行しなければなりません。民事裁判はどのような手続きで、どのくらい…[続きを読む]
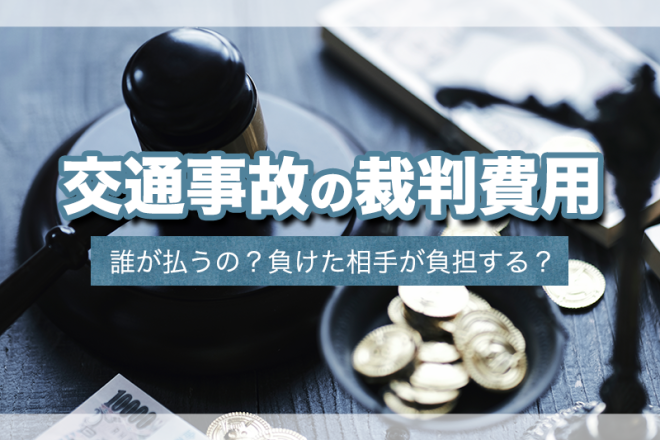
交通事故に巻き込まれ、弁護士に依頼すると、それなりの費用がかかることがあります。訴訟が起こされたり、法廷闘争に巻き込まれれば、裁判費用も発生します。
経済的な理由や家庭の事情から、裁判費用を支払う余裕がない場合、特に懸念されるでしょう。
ここでは、交通事故に関連する「裁判費用」と「弁護士費用」に焦点を当て、これらの費用を相手方に請求する方法、負ける場合と負けない場合、支払い責任が誰にあるのか、敗訴した場合の事態などについて説明します。
目次
交通事故における裁判費用は、どちらがどれだけ負担するのでしょうか?負けるほうが払うのでしょうか?
裁判をするには、利用者が「手数料」や「予納郵券」(原告・被告・証人等に裁判所から郵便を送る際の料金)を納めなければなりません。
なお、この費用は、弁護士に裁判を依頼する場合、弁護士にまず支払うことになります。
上述した印紙代や予納郵券は、そのまま原告が全額負担するわけではありません。
「判決」になった場合、裁判所が当事者の訴訟費用の負担割合を、たとえば、原告2割、被告8割などと指定します。
基本的に、負けた側の負担割合が高くなります。
そして判決後、原告と被告の当事者同士が、訴訟費用の精算をすることになります。
たとえば、5万円の印紙代が必要になった事案で、訴訟費用の負担割合が原告2割、被告8割とされた場合、原告は被告に対し裁判後に、印紙代5万円の8割、つまり4万円の支払を請求することができます。
ただし、裁判所が「訴訟費用は全面的に被告の負担とする」という判断をしたとしても、その「訴訟費用」とは、先に説明した印紙代や予納郵券のことであって、弁護士費用のことではありません。
「裁判費用」と「弁護士費用」は別扱いになります。このことについては、次節で詳しく解説致します。
裁判費用より高額になるのが「弁護士費用」です。
実際のところ、弁護士費用は誰が払うかといったら、訴訟費用と異なり、そのまま加害者に請求することは、難しいと言えます。
被害者の主張が正しく、裁判所が加害者の全面的な支払いを命じたケースでも、加害者に「弁護士費用」をそのまま請求することはできません。
弁護士費用を敗訴した側が負担する制度のことを、「敗訴者負担制度」と言います。
海外では敗訴者負担制度が導入されているところがありますが、日本ではこの制度は導入されていません。「自分で依頼した弁護士の費用は、裁判で負けた側ではなく、自分で負担すべき」という考え方になっているからです。
交通事故では訴訟はもちろん、調停、ADRなどの対応を弁護士に依頼しても、基本的には「弁護士費用は被害者自身が負担」しなければなならないのです。
ただし、例外的に、弁護士費用を加害者に請求できることがあります。
まず弁護士費用が加害者の負担となるケースは「不法行為に基づく損害賠償請求をする場合」です。
不法行為に基づく損害賠償請求をしたが、加害者が応じなかったため、やむを得ず裁判を行うために弁護士に依頼する必要があったとして、弁護士費用も損害として請求するわけです。
裁判所が判決を下した際に、判決で認められた「損害額の1割程度」を弁護士費用相当の損害金として認めてもらえることが実務上多いです。
具体的に言うと、2500万円の賠償額が認定された場合、1割の250万円が、弁護士費用として認められ、最終的な被害者への賠償額は、2500万円+250万円=2750万円となります。
つまり、もし被害者が支払った弁護士費用が、この賠償額の1割程度を超える場合には、超える部分は、被害者の自己負担となります。
一方で、被害者が支払った弁護士費用が賠償額の1割程度を下回れば、実質全額受け取ることができるというわけです。
また、事故相手に弁護士費用を負担させる可能性がある場合として「刑事事件が処分がされる前に示談」をするケースが挙げられます。
人身事故は、過失によって人を死傷させるものであり、「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」に該当し、刑事事件となります。
加害者の起訴前に示談が成立すれば、起訴を避けられる可能性が高くなり、起訴後であっても、刑事処分の前に示談が成立すれば、減刑される望みがあるため、多くの加害者は、被害者と示談をしたいと考えます。
このとき、被害者が「弁護士費用を支払わなければ、示談はしない」と言えば、加害者は、弁護士費用を上乗せしてでも示談したいと考える可能性があります。
交通事故が刑事事件となっている場合、加害者の減刑をお願いする「嘆願書」の作成を被害者に求めることがあります。
被害者が嘆願書を提出すると、加害者は不起訴や略式起訴になる公算が高くなるからです。
ただ、被害者にしてみれば、加害者の罪を軽くしてほしいとお願いしなければならない理由はありません。
そこで、「弁護士費用を支払ってくれるなら、嘆願書を書きます」という交渉が可能となり、加害者側も弁護士費用を支払う可能性は高くなります。
なお、交通事故などの場合、裁判に勝つ負けるとか、費用がどうなるかなどの悩みを防止するために、弁護士費用の軽減に有効な制度として「弁護士費用特約」があります。
弁護士費用特約とは、被害者が加入する自動車保険会社が、弁護士費用を負担してくれる制度です。
裁判をするときの印紙代、郵便切手代、日当など、裁判関連費用はすべて保険会社が負担します。
また、訴訟だけではなく、示談交渉や調停、ADRといった手続きでも、弁護士費用は、すべて補償の対象となります。
通常、弁護士特約は、300万円までの弁護士費用を保険会社が負担します。ほとんどのケースで、弁護士費用の負担なしに弁護士に依頼することができるでしょう。
一般的に、弁護士費用を加害者に負担させることは、基本的に難しいと言えます。
交通事故の損害賠償請求訴訟をする場合などは、弁護士費用の支払いを受けることができます。
弁護士に依頼すると、費用対効果は大きく、弁護士費用特約を利用すると、費用の負担も小さくなります。交通事故の被害に遭ったら、まずは弁護士に相談してみましょう。