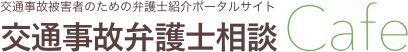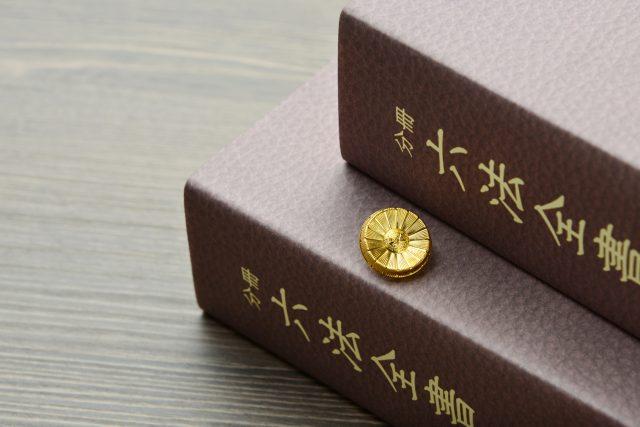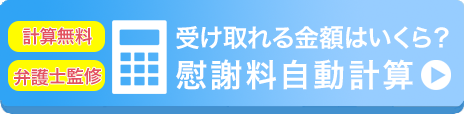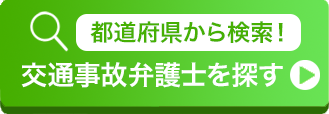交通事故の慰謝料は税金・確定申告が必要なの?

交通事故の被害者となり、加害者側の保険会社から示談金(損害賠償金)を請求して、それを受け取ると、ひょっとして税金がかかるのではないか?と心配する方は少なくありません。
もちろん、万一、課税されれば、賠償金は目減りしてしまいます。
この記事では、交通事故の損害賠償金(示談金、慰謝料、休業損害など)には税金がかかるのか?確定申告をする必要があるのか?という問題について、詳細に解説します。
目次
交通事故の人的損害に対する損害賠償金は所得税が原則非課税
ここでのポイント
「交通事故の人身損害賠償金であれば、その内容を問わず、所得税は非課税が原則」
まず最初に、交通事故の被害者の方に、喜ばしい結論を申し上げます。
交通事故でケガをした場合に、加害者側(加害者が加入している自賠責保険会社と任意保険会社を含む)から受け取る損害賠償金・示談金は、所得税の対象外とされており、非課税となるのが原則です。
これを定めているのが、次の法律です。
所得税法第9条(非課税所得)
第1項柱書
「次に掲げる所得については、所得税を課さない。」
第1項17号
「損害賠償金(中略)で、心身に加えられた損害(中略)に基因して取得するもの」
その内容については、政令で次のとおりとされています。
所得税法施行令・第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
第30条1号
「心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)」
第30条3号
「心身(中略)に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」
すなわち、例えば次のような交通事故の損賠賠償であれば、すべて所得税は非課税です。
- 慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料)
- 休業損害
- 逸失利益(後遺障害逸失利益・死亡逸失利益)
- その他の損害賠償金(治療費・付添看護費・通院交通費・入院雑費など)
- 見舞金、香典、葬祭料(※)
※ただし、見舞金、香典、葬祭料については、儀礼として社会通念上相当な金額に限られます(所得税法基本通達9-23)。
必要経費を補てんする損害賠償金は所得税が課税される!
ところが、損害賠償金に対する所得税の非課税には例外があります。それが必要経費を補てんする賠償金です。
次の事例で説明しましょう。
事例
個人商店を経営しているAさんは、事故のケガで店を2ヶ月間、休業しなくてはなりませんでした。
- Aさんは、この2ヶ月で、自分の収入が100万円減った
- しかし、店舗の家賃60万円と店員の給与30万円は今まで通り支払った
この場合、Aさんは、自分の減収分100万円だけでなく、店舗の家賃60万円と店員の人件費30万円という事業を維持するために支出を余儀なくされた固定経費も、休業損害の一内容として、加害者側に請求することができます。
そこで、Aさんは、賠償金として合計190万円を受け取りました。その後、確定申告などもしませんでした。
しかし、ここで190万円が損害賠償金ですが、その全額が非課税となるものではありません。
店舗の家賃60万円と店員の人件費30万円の合計90万円にだけは所得税が課税されるのです。
必要費を補てんする損害賠償金に所得税が課税される理由
その理由は次のとおりです。
店舗家賃と人件費の合計90万円は、Aさんが所得税の確定申告をする際に、必要経費として計上し、売上額から差し引いて申告するものであって、もともと課税対象ではありません。
仮に、Aさんが、賠償金として190万円を受け取りながら、店舗家賃と人件費の合計90万円を必要経費として、その年の売り上げから差し引いて申告するならば、その90万円の分だけ、税金を安くできてしまいます。
つまり損害賠償金の中に経費を補償する部分が含まれているときに、その部分まで非課税としてしまうと、二重の控除となってしまうのです。
そこで、二重控除を防止するため、損害賠償金のうち経費補てん分は課税対象とされているのです(※)。
※立命館大学・山名隆男教授「損害金額の必要経費算入と損害賠償金の課税・非課税」立命館法学2014年1号(353号)
これを定めているのが次の政令・通達です。
所得税法施行令・第30条柱書(概要)
(損害賠償金に)「損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分」を非課税とする。
所得税基本通達9-19
「『必要経費に算入される金額を補てんするための金額』とは、例えば、心身の損害に基因して休業する場合にその休業期間中における使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の維持管理に要する費用を補てんするものとして計算された金額」
ここでのポイント
「賠償金のうち、被害者の仕事の必要経費を補てんする部分の金額には、所得税が課税される」
示談金の中でも治療費は、医療費控除の対象外
また、交通事故によるケガの治療費を補てんする損害賠償金も所得税は非課税です。
ただし、被害者が確定申告の際に「医療費控除」を受けるときは要注意です。
「医療費控除」を受けるには、その年度に支払った医療費の総額を申告しますが、このときに、損害賠償金で補てん対象となった治療部分の金額を差し引かなくてはなりません(所得税法73条1項)。
損害賠償金の治療費部分は、医療費を補てんするのですから、その部分についても医療費控除を受けることになると、これも二重控除となるからです。
所得税法・第73条(医療費控除)概要
第1項 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額の100分の5に相当する金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額(中略)から控除する
ここでのポイント
「損害賠償で補てんされた治療費は、医療費控除の対象外」
死亡事故の損害賠償金などは、相続税が課税される場合がある!
死亡事故でも損害賠償金の所得税は非課税です(所得税法9条1項17号)。これは、即死事故でも、ケガを負った後に時間をおいて死亡した事故でもかわりません。
しかし、被害者の死亡により、金銭や債権を遺族が「相続」をすれば「相続税を課税」することが相続税の一般ルールです。
ややこしいので、以下で4つのケースをあげて損害賠償金・示談金と相続税の関係について説明しましょう。いずれも被害者Aさん、相続人妻Bとします。
損害賠償請求権の確定前に被害者が死亡した場合は、相続税の対象外
ケース1
Aさんは、交通事故で即死しました。その後、妻Bと加害者との間で示談が成立し、妻Bは加害者から損害賠償金を受け取りました。
ケース2
Aさんは、交通事故で重傷を負い、3ヶ月間の入院もむなしく死亡しました。その後、妻Bと加害者との間で示談が成立し、妻Bは加害者から損害賠償金を受け取りました。
ケース1のような即死事故の場合、古くからの民法判例では、死亡時に被害者本人が損害賠償請求権という債権を取得し、かつ、遺族がその権利を相続すると考えます(※)。
※大審院大正15年2月16日判決・大審院民事判例集5巻150頁
ケース2の場合も同様に、事故発生時に被害者が取得した損害賠償請求権を死亡によって遺族が相続しています。したがって、一般ルールからは相続税の対象となるはずです。
ところが現実には、上のケース1と2では、妻Bは相続税が課税されません。
ケース1及び2の場合、税務上の取扱いとしては、「遺族が直接に加害者に対して損害賠償請求権を取得したものであって相続ではない」と取扱って相続税の対象外とするのです。
相続ではないとすると、遺族の「所得」となりますが、賠償金の所得税は非課税ですから、結局、課税しないとするのが国税庁の扱いです(※)。
※「新訂法律家のための税法」(東京弁護士会編著・第一法規)251頁
これは、ケース1及び2の場合、まだ加害者の法的責任の有無や損害額といった、債権の存否や金額を含めた内容が未確定な状態で、死亡により発生した損賠賠償請求権を相続するといっても、抽象的・観念的なものに過ぎない段階だからと考えられます(※)。
※例えば、所得税法では現実の収入がなくても、「権利の確定した金額」であれば、その年度の収入とする権利確定主義を採用しており(所得税法36条1項)、これと軌を一にしていると言えます(「租税法・第23版」金子宏・弘文堂・310頁参照)。
損害賠償請求権の確定後に被害者が死亡した場合は、相続税の対象
ケース3
Aさんは、交通事故で重傷を負い、3ヶ月間の入院後、退院しました。その後、Aさんと加害者の間で示談が成立し、Aさんは示談で合意した損害賠償金を受け取りました。ところが、その6ヶ月後、Aさんはガンで死亡してしまいました。妻Bが損害賠償金を含む遺産を相続しました。
ケース4
上のケース3で、Aさんと加害者の間で示談が成立しましたが、損害賠償金が振り込まれる前にAさんが心臓発作で死亡してしまいました。死後、Aさん名義の口座に振り込まれた損害賠償金は、妻Bが相続しました。
他方、ケース3や4のように、すでに被害者の損害賠償請求権が示談の成立や判決により確定した後に被害者が死亡した場合は、遺族は確定した損賠賠償請求権という債権を相続するので、相続税の対象となるのです。
ケース3においてAさんが損害賠償金を受け取った時点、ケース4 においてAさんが示談を成立させて賠償請求権を確定させた時点では、所得税法9条1項17号により、Aさんに所得税がかかることはないわけですが、ケース3でも4でも、相続した時点で妻Bの相続税が発生するのです。
ここでのポイント
「損害賠償請求権が確定する前に被害者が死亡した場合、その権利を遺族が相続しても相続税は非課税。示談や判決等で権利が確定した後に被害者が死亡した場合は相続税がかかる」
交通事故被害者の死亡保険金に対する税金は?
さて、交通事故での被害者の死亡を原因として支払われる金銭には、損害賠償金だけでなく、死亡保険金もあります。これには税金はかからないのでしょうか?
被害者の死亡保険金の課税関係
死亡保険金は、保険金を「支払った者」と保険金の「受取人」が誰かで課税される税金が異なります。
被保険者以外が保険料負担者兼受取人の場合所得税の対象
被保険者以外の者が保険料負担者で、かつ、その者が受取人の場合は、所得税の課税対象です。受取人は、自分で対価を支払って、保険契約に基づく権利を得たもので所得にあたるからです(所得税法34条)。
被保険者と保険料負担者が同一人の場合相続税の対象
被保険者と保険料負担者が同一人の場合は、相続税の対象となります。被保険者の相続人が受取人の場合は、相続によって取得したものとして、相続税の課税対象となり、第三者が受取人の場合は、遺贈によって取得したものとして、やはり相続税の課税対象となります(相続税法3条1項1号)。
被保険者、保険料負担者、受取人が異なる場合贈与税の対象
被保険者、保険料負担者、受取人が全部異なる場合は、贈与税の課税対象となります(相続税法5条1項)。
これを表にすると次のとおりです。
死亡保険金の課税関係
| 被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| 被害者A | B | B | 所得税 |
| 被害者A | 被害者A | B | 相続税 |
| 被害者A | B | C | 贈与税 |
ここでのポイント
「被害者の死亡保険金は、所得税・相続税・贈与税の対象となり、どの税金がかかるのかは、保険料を支払っていた者と受取人が誰かによって変わる」
人身傷害補償保険の死亡保険金は、非課税となる場合がある!
ただし、死亡保険金といっても、被害者が加入していた人身傷害補償保険から支払われる保険金は、異なる取扱いとなります。
人身傷害補償保険は、被保険者(被害者)が交通事故で死傷した場合に、被保険者の過失割合にかかわりなく契約金額の範囲内で実損害額を補償する保険です。
損害金を支払った保険会社は、被害者に代わって、被害者が加害者に対して有していた損害賠償請求権を取得し、加害者に請求します。
例をあげましょう。
- 死亡事故の被害者:A
- 相続人:妻B
- 加害者:C
- 人身傷害補償保険:D損保(保険金限度額は無制限とします)
- 死亡による損害額:1億円
- 過失割合 A20%:C80%
人身傷害補償保険では、Aに20%の過失割合があっても、D損保は妻Bに対し、実損害額1億円の保険金を支払います。
本来、妻Bは加害者Cに対して、8000万円の損害賠償請求権を有していましたので、保険金1億円のうち8000万円は、D損保が加害者Cの責任を肩代わりしたことになります。
そこで、D損保は妻Bが加害者Cに対して有していた8000万円の損害賠償請求権を、妻Bに代わって取得し、加害者Cに請求することができます。これを代位請求と呼びます。
このように、人身傷害補償保険から支払われる保険金は、本来、加害者が支払う賠償金を肩代わりしたものに過ぎないので、実質的な損害賠償金です。
そうであれば、加害者が、その過失割合に基づいて支払うべき損害賠償額に相当する金額については、税務上も、損害賠償金と同様の扱いを受けることになります。
人身傷害補償保険については原則非課税
そこで、まず所得税については、所得税法9条1項17号により非課税となります。
次に、相続税についても、相続または遺贈によって取得した保険金とは扱われず、非課税となります(※)
※ここは少々説明が必要です。人身傷害補償保険と同様に、被害者が加入している保険から保険金を受け取ることができるものに「無保険車傷害保険契約」があります。これは、加害者が任意保険に加入しておらず、損害に見合う賠償金の支払を受けることができない場合などに、死亡や後遺障害の損害を補償してくれる保険であり、保険金といっても、その実質は加害者が支払うべき損害賠償金なので、相続税法基本通達によって、相続税の対象外とされています(相続税法基本通達3-10「無保険車傷害保険契約に係る保険金」)。人身傷害補償保険も、この通達と同様に取り扱われるということになります。
さらに、贈与税についても、贈与により取得したものとは取り扱われず、非課税となります(相続税法基本通達5-1による、同通達3-10の準用)。
加害者負担の賠償額を超えた部分は課税対象
ただし、非課税となるのは、あくまでも、本来は加害者が負担するべき賠償額の部分に限定されますので、その金額を超えた部分は、原則にもどって、所得税、相続税、贈与税が課税されます(※)。
※以上の取扱いについては、1999(平成11)年10月4日付け、東京火災海上保険株式会社から国税庁に対する照会「人身傷害補償保険金に係る所得税、相続税及び贈与税の取り扱い等について」と、これに対する同年10月18日付け国税庁の回答に明記されています。
【出典】国税庁サイト:人身傷害補償保険金に係る所得税、相続税及び贈与税の取扱い等について(法令解釈通達)
ここでのポイント
「人身傷害補償保険のように、死亡保険金が加害者の支払うべき賠償金の肩代わりの性格をもつ場合は、加害者がその過失割合に応じて負担するべき賠償額の部分は所得税・相続税・贈与税は非課税」
よくある質問
交通事故の人身損害賠償金に税金はかかる?
交通事故の人身損害賠償金であれば、その内容を問わず、所得税は非課税が原則です。
損害賠償で補てんされた治療費は、医療費控除の対象外になるの?
損害賠償で補てんされた治療費は、医療費控除の対象外になります。
まとめ
交通事故の損害賠償金・示談金などに関する税金と確定申告について説明しました。
税金をめぐる問題は複雑であり、せっかく損害賠償金を手にしても、予期せぬ課税で十分な補償とならない事態もあり得ます。
示談交渉に際しては、交通事故に強い弁護士に相談して、税金についても確実な予測を得ておくことをお勧めします。