自賠責保険の支払基準が改定|最新の基準を解説【2024年版】
自賠責保険の支払基準が改定されました。交通事故の被害に遭ってしまった方にとっては、自賠責保険からどのような補償を受け…[続きを読む]
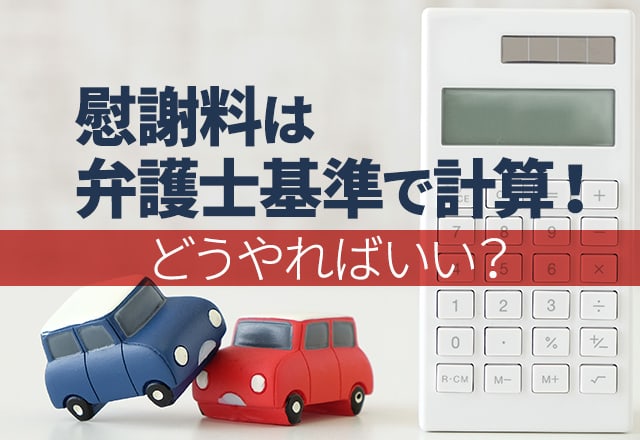
人身事故に遭ったら、入通院慰謝料を請求することができます。
慰謝料を計算する上で、一番重要な計算基準が「弁護士基準」です。
今回は、Yahoo!知恵袋やブログで話題の、交通事故の慰謝料を弁護士基準に合わせる方法や、弁護士基準表の内容(日額や通院日数との関係など)、金額を低く抑えるための計算方法、どの基準で請求するべきか、弁護士基準にするにはどうするか、自分で交渉、自分で弁護士基準で計算できるかどうか、そして後遺障害14級慰謝料や追突事故慰謝料の具体例を交えて、詳しく説明します。
目次
弁護士基準にするにはどうするかの前に、まずメリットから解説すると「弁護士基準」で計算すると、圧倒的に慰謝料が高額になります。
言い換えれば、他の基準で計算すると、慰謝料の金額が相当減額されてしまうのです。例えば、自賠責保険の基準や任意保険基準で計算すると、慰謝料の金額が2分の1や3分の1程度になってしまうことも、珍しくありません。
自賠責保険は、被害者を救済するために最低限の補償を目的とした制度であり、その負担額を計算する際に用いられる基準が自賠責基準です。そのため、自賠責基準は最も低額なものとなります。
また、2020年4月1日から自賠責保険の支払基準が改定されており、入通院慰謝料が日額5,700円から日額6,100円に引き上げられるなどの変更点があります。詳細については、興味のある方は別の記事も参照してください。
任意保険基準は通院日数で計算するというより、各保険会社が独自の社内基準として定めたのが任意保険基準です。
詳しい内容は公表はされていませんが、各社大きな金額の差はないようです。
自賠責基準より低いと言われるケースもあるですが、原則、自賠責同様と考えましょう。
弁護士基準と比較すると低額になります。
弁護士基準は、裁判所と弁護士団体が過去の事例の積み重ねに基づき協議して作成した、裁判に用いられる法的に正当な唯一の基準です。
交通事故で損害賠償金を弁護士基準で計算するときには、弁護士に示談交渉を依頼して、弁護士基準を適用して賠償金全体を計算してもらう必要があります。
3つの基準のうちで一番高額な示談金算定基準である弁護士基準は、次に挙げる刊行物等に示されており、これを参考に示談金(損害賠償金)を算出します。
これらの本に示された基準は、通院日数で計算するような日額の計算式ではなく表が記載されています。
新刊が出る際に基準金額が改定される場合があるので、自分が確認したものが古い情報でないかチェックが必要です。
これらの本は、一般の方が購入することも可能です(※)。
それでは、実際に、上記で確認した弁護士基準・裁判基準で、自分で慰謝料の計算をしてみましょう。
なお、一発で弁護士基準の金額を計算するには、下記ページの慰謝料自動算定計算機をご利用ください。ご自分の交通事故の条件を入力するだけで相場がわかります。また、次に自分で対応可能か、弁護士基準にするにはどうするかを解説しましょう。
以上の他にも弁護士基準にするはどうすればいいか、また自分で交渉、慰謝料を請求する際に知っておいたほうが良いことがあります。
被害者ご自身で、弁護士基準にするにはと考える場合もあると思いますが、その場合、弁護士基準の慰謝料を獲得することは厳しいでしょう。
「赤い本」に書いてあると言ってみても、その通りに物事はすすみません。最近では、弁護士が介入しても、裁判にならなければ、自社の基準で算定する保険会社もあります。
ご自分で交渉し、難しいと感じたら、そして、弁護士基準にするには、まず弁護士に相談するほかありません。
その他に、弁護士基準で損害賠償を請求するのであれば、交通事故紛争処理センターの和解あっせんを利用するという手段があります。交通事故紛争処理センターは、被害者と加害者・加害者の保険会社との和解のあっせんと審査手続きをするADR機関です。
利用方法などについては、以下の交通事故紛争処理センターのHPをご覧ください。
【関連外部サイト】公益法人 交通事故紛争処理センター
多くの保険会社では、弁護士が示談交渉することで弁護士基準の適用を受け入れます。
しかし、保険会社によっては、弁護士が介入しても、弁護士基準の適用を拒否する場合があります。
しかし、示談交渉で弁護士基準の適用を頑なに拒否する保険会社でも、提訴されれば弁護士基準に従うしかありませんから、弁護士に訴訟を依頼すれば良いだけです。
個別の事案について弁護士基準にするには、交通事故に詳しい弁護士にご相談することをお勧めします。
自賠責保険では、傷害部分についての補償が「上限120万円」と決まっています。
傷害に関する限り、治療費、入通院慰謝料、通院交通費、休業損害といった各損害項目のすべてを合計した損害総額に対し、120万円の補償が上限なのです(もちろん、死亡や後遺障害については別途の上限額があります)。
しかし、そのことと慰謝料を弁護士基準で請求することは、関係ありません。自賠責保険は損害賠償額の一部を補償する制度に過ぎないからです。
損害賠償額の総額全部を算定するのが弁護士基準であり、自賠責保険の限度額を超えた損害を補償するのが任意保険です。
したがって、損害額が自賠責保険の限度額を超えていても、加害者の任意保険会社に対する弁護士基準での請求は可能です。
最初に、交通事故の「入通院慰謝料」を弁護士基準表を使用して計算します。
入通院慰謝料は、事故による身体的な損傷に対する慰謝料であり、文字通り、入院期間と通院期間に基づいて、機械的に自己計算が可能です。
入院や通院が長期化すれば、慰謝料の請求額も増加する可能性があります。
以下が基本の表です。赤く表示された数字の欄を御覧ください。
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
表の見方を簡単に解説すると、入院した期間と通院した期間を確認して、ぶつかる点の数字を基準にします。たとえば、
となります。ただし下記で説明する通り、別表Ⅰ以外で計算するケースもあります。
例えば、むちうち症状など、他覚症状がなく、被害者の自覚症状しかないことがよくあります。この場合には、上とは異なる表(別表Ⅱ)を使います。
他覚症状の有無は医師が医学的観点から判断します。たとえば、むちうちでレントゲン画像を撮って異常が写っていたら、そこには他覚症状があるとされます。
また、軽度の打撲や軽度の挫傷のケースでも、別表Ⅱを自分で使って計算できます。
むちうちなどの自覚症状のみや軽傷のケースにおける入通院慰謝料の金額は、以下の表の通りです。赤く表示された数字の欄を御覧ください。
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
表の読み方自体は、通常のケースと全く同じです。
たとえば、
となります。別表Iと比較すると、金額が3分の2程度下がることが分かります。
上記の通り、弁護士基準の場合は「治療期間」が重要であって、実通院日数はあまり問題になりません。
しかし、あまりに実通院日数・実通院回数が少なくなると、慰謝料金額を下げられる可能性があります。
詳しくは下記記事で解説するので併せてご参照ください。
具体的なケースを使って、弁護士基準の慰謝料がどのくらいになるのか、見てみましょう。
まずは、事故で軽度の打撲の傷害を負い、1ヶ月通院したケースです。後遺障害は残りませんでした。
この場合、発生する慰謝料は入通院慰謝料のみです。軽度の打撲傷ですから、軽傷の場合の入通院慰謝料の別表Ⅱを参照すると、弁護士基準の入通院慰謝料の金額は、19万円となります。
追突事故でむちうちとなり、3ヶ月間通院したとしましょう。後遺障害は認定されなかったとします。この場合には、入通院慰謝料のみが認められます。
入通院慰謝料については、自覚症状しかないむちうちのケースとした場合、軽傷の場合の別表Ⅱを利用します。
すると、弁護士基準の入通院慰謝料の金額は、53万円となります。
同じ他覚症状のないむちうちでも、6ヶ月程度の通院が必要になったら、どのくらいの慰謝料が認められるのでしょうか?
この場合、別表Ⅱの通院6ヶ月の項目を参照すると、金額は89万円となります。
むちうちになると「後遺障害14級9号」が認定されることがあります。そこで、通院6ヶ月後、14級の後遺障害が残ったら、どのくらいの慰謝料が認められるのかを見てみましょう。
この場合、別表Ⅱでは入通院慰謝料の金額は、89万円です。そして、弁護士基準では、14級の後遺障害慰謝料の金額は110万円です。
したがって、慰謝料の合計は、次の額となります(後遺障害慰謝料の計算については後述します)。
入通院慰謝料89万円 + 後遺障害慰謝料110万円 = 199万円
同じむちうちでも、レントゲンやMRIといった他覚症状があると、後遺障害12級13号に認定されることがあります。通院6ヶ月後に12級の後遺障害が残ったときの慰謝料を考えてみます。
入通院慰謝料は、別表Ⅰによって116万円、弁護士基準の12級の後遺障害慰謝料額は、290万円となります。
慰謝料の合計額は、406万円です。
入通院慰謝料116万円 + 後遺障害慰謝料290万円 = 406万円
先述したとおり、入通院慰謝料以外に請求できる慰謝料に、「後遺障害慰謝料」があります。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級によって決まっています。
| 1級 | 2800万円 |
|---|---|
| 2級 | 2370万円 |
| 3級 | 1990万円 |
| 4級 | 1670万円 |
| 5級 | 1400万円 |
| 6級 | 1180万円 |
| 7級 | 1000万円 |
| 8級 | 830万円 |
| 9級 | 690万円 |
| 10級 | 550万円 |
| 11級 | 420万円 |
| 12級 | 290万円 |
| 13級 | 180万円 |
| 14級 | 110万円 |
なお、後遺障害認定された場合は「逸失利益」の金額も考慮する必要があります。
別途ページで詳しく解説していますので、併せてご参考ください。
最後に死亡慰謝料についてです。
死亡慰謝料の金額は、被害者の家庭での立場などによって決まります。
具体的には、以下の通りとなります(「赤い本」の基準によります)。
| 被害者が一家の支柱であった場合 | 2800万円程度 |
|---|---|
| 被害者が母親や配偶者の場合 | 2500万円程度 |
| 被害者が独身者の場合 | 2000万円~2500万円 |
| 被害者が高齢者の場合 | |
| 被害者が子どもの場合 |
なお、死亡慰謝料は、被害者が即死した事案を思い浮かべるかもしれませんが、死亡事故は、即死事案ばかりとは限りません。
事故後すぐに病院に運ばれて、しばらく治療を続けたけれども、治療の甲斐なく死亡してしまったケースでも、死亡慰謝料が支払われます。

交通事故の被害に遭った時に慰謝料をできるだけ多くもらうためのポイントについて解説します。
示談金に納得できない時に、まず大事なことは安易に応じないことを覚えておく必要があるでしょう。
「これだけしかもらえないの?」と疑問に思ったのに、「こんなもんなのかな」と諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。
しかし、保険会社はできる限り示談金額を低くおさえようとしているため、示談金が適正な価格でないケースがあります。
しっかりと適正な額が支払われているのかについて弁護士基準で確かめる必要があります。
もっとも、自分で適正額かどうかにつき判断できないこともあると思います。もちろん自分で交渉はしにくいです。そんなときは、専門家である弁護士に相談をしましょう。
最近では、初回は無料で相談できる法律事務所もあります。
保険会社が提示する示談金に納得できないときは、お近くの弁護士事務所に相談してみてください。
今回は、Yahoo!知恵袋やブログで話題の、交通事故の弁護士基準表、弁護士基準の慰謝料相場、自分で交渉、弁護士基準にするには、日額や通院日数の関係までご紹介しました。
なるべく高額な慰謝料を獲得するには、弁護士に示談交渉を依頼して、手続を進めてもらうことが大切です。
交通事故でけがをした場合には、まずは交通事故問題に強い弁護士に相談をして、損害賠償請求を依頼する事をおすすめします。