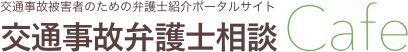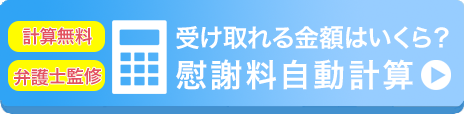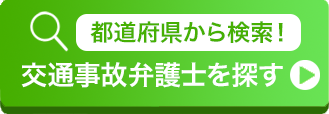派遣社員が交通事故被害に遭った場合の注意点

サラリーマンや個人事業者など、仕事をして収入がある人が交通事故に遭ったら、加害者に対し、賠償金を請求することができます。
ただ、派遣社員の場合には、収入が不安定なので、休業損害を請求する際の基礎収入がいくらにすべきか問題となりますし、交通事故後に派遣期間が終了してしまうケースもあります。
そこで今回は、派遣社員の方が交通事故の被害に遭った場合の休業損害の考え方について、ご説明します。
目次
サラリーマンの場合の休業損害
以下では、具体的にどのようにして休業損害を計算するのか、見ていきましょう。
派遣社員の場合の計算方法を検討する前に、まずは「オーソドックスなサラリーマンの場合の計算方法」を理解しておくとわかりやすくなります。
サラリーマンの基礎収入
まずは、基礎収入を計算する必要があります。
サラリーマンの場合、事故前の3ヶ月分の給料を基準にして計算することが多いです。
たとえば事故前の給料が、28万円と30万円と32万円だったとします。すると、合計は90万円です。これを、3ヶ月間の土日祝日も含めた日数である90日で割り算します。すると、1日あたりの基礎収入は、1万円となります。これを3ヶ月間の「期間平均日額」と呼びます。
サラリーマンの基礎収入額
事故前の給料
事故の3ヶ月前 事故の2ヶ月前 事故の1ヶ月前 合計 28万円 30万円 32万円 90万円 期間平均日額 = 90万円 ÷ 3ヶ月 = 1万円
サラリーマンの休業日数
1日あたりの基礎収入を計算できたら、休業日数をかけ算します。
休業日数は、実際に仕事を休んだ期間の日数です(期間で算定するので、土日祝日も休業期間に含めることに注意してください)。
たとえば、先ほど計算したサラリーマンの休業期間が、令和2年7月1日(水)から7月10日(金)までならば、土日を含めた日数である10日を休業日数とします。
こうして、「1万円 × 10日 = 10万円」の休業損害が発生することになります。
上に示した計算方法は、通常の保険実務でとられている方法です。ただし、示談交渉では、保険会社が、「期間平均日額」に「実休業日数(実際に休んだ日の数)」を掛け算した金額を提示することがあります。「期間平均日額」は土日祝日を含めた単価ですから、「実休業日数」で計算すると休業損害が低額となり、被害者に不利な場合があるので、要注意です。
派遣社員特有の問題は?
それでは、派遣社員の場合、サラリーマンと何が違うのでしょうか?
「派遣社員でも、給料をもらっているのだから、サラリーマンと同じように計算できるのではないか?」と考える方がいるかもしれません。
しかし、派遣社員には、特有の問題が2つあるので、以下でご説明します。
問題点その1 派遣社員の収入が不安定
サラリーマンの場合、時期によって大きく給料の額が異なることは普通はありません。
これに対し、派遣社員は、時期によって異なる派遣先会社に働きに行っています。仕事がまったくない時期もあります。このため、同じ期間の勤務でも給与額が一定しません。
たとえば、事故前3ヶ月間に、たまたま収入が少なかった場合、正社員のサラリーマンと同じ計算方法を採用すると、偶然の事情で基礎収入が少なくなってしまいます。
つまり、派遣社員の場合は、収入の金額が安定しないケースが多く、事故前3ヶ月の収入をベースとすると妥当性を欠く事案が珍しくないのです。
そこで、このような場合は、事故前3ヶ月の収入ではなく、事故前12ヶ月間の収入や事故の前年度の年間収入をベースとして基礎収入を計算する必要があります。
なお、以上の説明は、派遣元会社に登録された労働者が派遣先会社に派遣される都度、労働者と派遣元会社との間で、派遣期間かぎりの雇傭契約を締結する「登録型」派遣を前提としています。
これに対し、労働者が派遣元会社に常時雇用され、派遣されていない期間中も給与が支払われる「常用型」の場合は、毎月の収入は安定しているので、登録型のような問題は生じません。
問題点その2 派遣社員の休業期間
派遣社員の休業損害を計算するときには、休業期間も問題になります。
正社員のサラリーマンの場合には、期間の定めのない雇傭契約なので、特別な事情がなければ定年まで勤務を続けます。
契約期間と休業損害
しかし、派遣社員(登録型)の場合には、派遣元会社との「契約期間」があります。期間が切れると、その日からは働くことがなくなり、収入が入ってこなくなります。すると、派遣の期間が切れた後は、怪我で働けなくとも、休業損害が発生しないことになるのです。
それでは、交通事故前に派遣の期間が切れて、たまたま働いていなかった場合や、事故後に期間が切れて収入がなくなった場合には、その後の期間については、派遣社員に休業損害が発生しないのでしょうか?
この場合の考え方は、個別のケースによって異なります。
具体的には、契約の更新が行われたり、定職に就いたりする蓋然性があったかどうかで決まります。
休業損害の請求には定職への就職の蓋然性が必要
事故後の契約更新や、定職への就職の蓋然性が高かったことを立証できれば、一定の休業期間を認定してもらえる場合があります。
事故に遭うまでは何度も契約更新さてきたのに、事故で休業したために、契約更新されなかったという「雇い止め」のケースなどは、事故後の契約更新の蓋然性が認められやすいでしょう。
しかし、一定の休業期間が認められても、実際には、契約は更新されておらず、定職にもついていないので、現実の収入を基礎収入とすることはできません。
そこで、厚労省の賃金統計(賃金センサス)による平均賃金を利用して基礎収入を認定します。
ただし、現実には就労していないことを考慮して、控えめな算定とならざるを得ず、平均賃金の金額から何割か減額した金額で算定する裁判例が多くあります。
裁判例1
京都地裁平成23年12月13日判決
派遣社員の被害者(女性36歳)は、事故のために契約を更新できず、契約が終了してしまいました。しかし、裁判所は、もともと事故前に契約の更新が予定されていたことから、事故日から契約期間満了までの75日間の休業損害だけでなく、契約期間満了後から再就職の日まで142日間の休業損害も認めました。この事案で認められた休業損害の総額は約140万円でした。
(交通事故民事裁判例集44巻6号1584頁
裁判例2
大阪高裁平成20年11月5日判決
派遣社員の被害者(男性29歳)は、事故後の休業期間中に契約期間の満了を迎えてしまいました。しかし、裁判所は、被害者が派遣社員として4年間以上勤務した実績があること、派遣会社には契約更新の制度があることなどから、事故がなければ契約が更新されていた蓋然性が高いとして、契約期間満了後の休業損害を認めました。
(自保ジャーナル1770号2頁)
裁判例3
大阪高裁平成21年9月10日判決
オペレーター等の派遣社員として登録していた被害者(25歳女性)は、事故の前年は喫茶店従業員として年収105万円でした。しかし、裁判所は、近い将来に定職に就く可能性は相当程度認められるとして、症状固定まで159日間の休業期間を認定し、女子平均賃金(学歴計、全年齢)の80%である約280万円を基礎収入とした約121万円の休業損害を認めました。
(自保ジャーナル1818号99頁)
裁判例4
大阪高裁平成21年11月17日判決
事故前に派遣社員をしていた被害者(28歳女性)は、事故時には収入がありませんでした。しかし、裁判所は、被害者が大学卒で、将来的には就職を希望していたことなどから、休業損害を認め、女子平均賃金(学歴計、全年齢)の50%を基礎収入と認定しました。
(自保ジャーナル1818号144頁)
なお、派遣元会社に常時雇用される「常用型」では、通常、期限の定めのない雇傭契約となっているので、この問題は生じません(但し、期限を定めている場合は別です)。
交通事故で派遣社員が解雇されてしまったときの休業損害は?
事故の怪我で休業を余儀なくされた結果、派遣元会社から解雇されてしまった場合、休業損害の賠償金を受け取ることができるでしょうか?
派遣社員は、派遣元会社と労働契約を結んでいますが、怪我で仕事に就くことができず、労働する義務を果たせなければ、解雇によって契約を解消されてしまいます(なお、交通事故が業務上災害の場合は、労働者の療養期間中及びその後30日間は解雇が禁止されています(労働基準法19条1項))。
解雇したのは派遣元会社ですが、交通事故で怪我をしなければ解雇されなかったのですから、解雇で仕事を失って収入が減少した損害は、交通事故と因果関係のある損害です。
したがって、解雇による減収も休業損害の対象となります。
具体的には、事故がなければ派遣元会社との契約期間満了まで働けたのですから、少なくとも契約期間満了までの期間分の休業損害を加害者側に請求することができます。
また、契約更新の蓋然性があったのであれば、契約期間経過後、少なくとも症状固定までを休業期間として休業損害を請求することが可能です(前記裁判例3を参照)。
さらに、再就職が難しいなどの事情があれば、再就職の日までを休業期間として補償する場合もあります(前記裁判例1を参照)。
予想される相手からの反論
以上、派遣社員の休業損害の計算方法をご紹介してきましたが、派遣社員が自分で保険会社と示談交渉をすることにより、上記の基準での休業損害を受けられるのでしょうか?
答えはNOです。
それは、被害者が自分で交渉をすると、相手の保険会社がさまざまな理由をつけて、休業損害を減額してくるからです。
以下で、具体的にご説明します。
保険会社は低額な金額しか提示してこない
派遣社員が相手の保険会社に休業損害を請求したら、相手は、派遣社員の基礎収入について、自賠責基準の1日6,100円を当てはめてくる場合があります。
派遣社員としての、実際の収入実績が、日額6,100円を下回っているならば、この自賠責基準による提案を承諾することも一考に値します。それ以上の収入をあげることができた蓋然性が立証できなければ、それ以上の休業損害を受け取ることはできないからです。
他方、契約更新や定職につくことで、日額6,100円を上回る収入を得る蓋然性があったと立証できるならば、この提案は拒否するべきです。
派遣社員の契約期間が切れた後の休業損害の支払を拒絶される
保険会社が、派遣社員の契約期間が切れた後の休業損害を進んで認めることは、まずないと考えましょう。
示談交渉をしていたら「実際に派遣期間が終了しているのだから、それ以後の休業損害は発生しない」と言ってきます。
しかし、契約期間が切れた後も、契約更新の蓋然性、就労の蓋然性が高ければ休業損害が認められますから、保険会社の対応は不当と言わざるを得ません。
経済的に余裕がなくても弁護士に依頼する
最後に、弁護士に相談するメリットと方法を簡単に解説します。
無料法律相談サービス
- 多くの交通事故に強い法律事務所が無料法律相談を実施している
- インターネットで検索すれば、無料相談可能な事務所がたくさん見つかる
弁護士費用特約
- 自動車保険に「弁護士費用特約」がついていれば、無料で弁護士に相談・依頼ができる
- 自分だけでなく、家族(配偶者、親、子ども)が契約者の場合も多くは利用可能
- まずは自動車保険会社に弁護士費用特約の有無を確認する
- 利用できる場合は、早めに弁護士に無料相談することが重要
つまり、無料法律相談サービスや自動車保険の弁護士費用特約を活用することができれば、経済的理由で弁護士相談を遠慮する必要はありません。弁護士に早めに相談することがおすすめです。