人身事故と物損事故では大違い!人身切り替えで知っておくべき事を解説
交通事故における人身事故と物損事故の違い、物損事故から人身事故への切り替える方法や切り替えメリットとデメリット、弁護…[続きを読む]
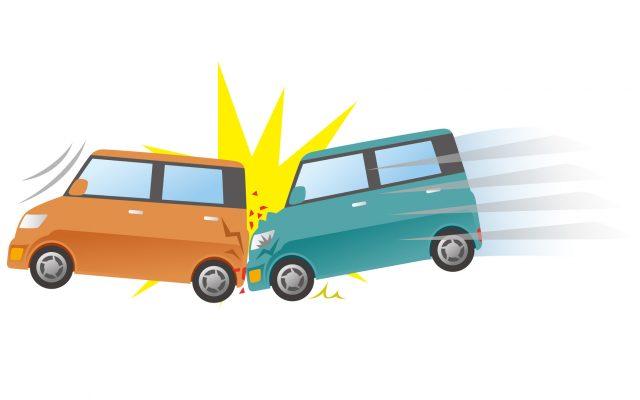
加害者側が「無免許運転」であることも、少なくありません。
加害者側は、無免許運転を知られたら困るため、逃走を図ったりするケースもあります。
また、無免許運転の車に同乗していた場合は、罰則を受けるケースもあります。
今回は、無免許事故の被害者が知っておくべきこと、初期対応や過失割合、保険や加害者側の同乗者に関することを説明します。
目次
では、無免許運転で被害者になってしまった場合、初期対応ですべきことはどんなことでしょうか。
基本的には、通常の交通事故後のフローと同じです。ただし、無免許運転の場合は、逃走の可能性があるため、相手方の連絡先を確認することや、証拠をおさえておくことが重要となります。
まず、事故が起きたら、被害の状態を確認し、警察に連絡します。
また、負傷者が入る場合は救急車にも連絡しましょう。
警察に報告する際、少しでも体が痛む場合は、その旨もしっかりと伝えるようにしましょう。
先にお伝えした通り、無免許事故の場合は、逃走の可能性が高くなってしまいます。したがって、相手方からの情報をしっかりと得ておくことが重要です。
警察や救急車に連絡後、到着までの間は、加害者の連絡先を確認します。
具体的には、住所・氏名・電話番号・保険会社の名前(自賠責・任意保険)などを確認しましょう。
これ以外にも、事故車の状態を確認しておくことも大事です。メモを取ることができない状態の場合は、スマホのカメラで損傷部分などをおさめておけば良いでしょう。
また、どのように被害に遭ったのかについて、思い出しておくことも大切です。
どこでブレーキを踏んだのか、どのあたりでぶつかったのかなどを、メモなどに書いておくと現場検証をスムーズに行うことができます。
最後に、余裕があれば、目撃者を確保することも重要です。
目撃者を確保しておくことで、交通事故における加害行為の態様が明らかになり、過失割合を計算する際に有力な証拠となるケースもあります。
可能であれば、目撃者の連絡先を聞いておくのもよいでしょう。もっとも、交通事故後は気が動転していることが多く、たくさんのことを考えられなくなってしまいます。ですので、絶対ではなく「できる範囲」で証拠を確保しておくことが重要です。
このように、まずは警察に連絡することが大切です。警察が到着するまでの数分間の間は、できる範囲で行動を起こすようにしましょう。
後々で体に痛みが発生した場合には、手続き上人身事故として処理をし直さなければいけません。
なぜなら、物損事故の場合は、保険会社から医療費や損害賠償などをもらえなくなってしまいます。
このような自体を防ぐためにも、少しでも体に変化を感じる場合は、人身事故として処理してもらいましょう。
無免許運転と過失割合について考える必要があります。
例えば被害者がうっかり信号無視をした場合など、単に無免許運転の加害者側だけが全ての責任を負うわけではないことに注意すべきです。
無免許運転を相手がしたからといって、過失割合10対0になるとは限りません。
ただ、以下の記事になるように無免許運転は修正要素として、減算要素、重過失になる事が考えられます。
ただ、無免許運転者に対して責任の増加を考慮する必要はもちろんありますが、結果的には事案の全体像を総合的に判断し、過失割合を正確に定める必要がありますので、単に無免許運転者だけが一方的に悪いとはならないことを念頭においておきましょう。
無免許運転と一言でいいますが、実はいくつか種類があります。以下、理解しておきましょう。
まず、一度も免許を取得したことがない場合は、「純無免許運転」と判断されます。
未成年で運転できる年齢に達していないケースなどは、こちらの分類となります。
次に、「取り消し無免許」です。
こちらは、その名の通り、交通違反などで免許取り消しの認定を受けたのにも関わらず、運転してしまった場合を指します。
これと似たケースでは、「停止中無免許」があります。
免許を有効に取得したものの、違反の累積などにより免許の効力が停止しているケースです。
最後に、「免許外運転」です。これは、車種に対応した免許を取得していなかった場合を指します。
オートマ限定の場合に、ミッション車を運転した場合や普通自動車免許で大型バイクを運転した場合などが当てはまります。
次に、被害の賠償について見ていきます。自賠責や任意保険で、医療費や損害賠償はカバーしてもらえるのでしょうか。
無免許運転の事故の被害者になってしまった場合、相手方の保険は保障してくれるのでしょうか?
被害者には、被害者保護の観点から保険がきちんとおります。
具体的には、自賠責保険や対人・対物賠償保険が適用されます。ですので、無免許運転の被害者になってしまったからといって、相手方の保険会社への請求は諦めないでください。
事故の際は、相手方の連絡先と一緒に保険会社の名前も聞いておきましょう。
加害者に保険はおりません。これは自らの落ち度が大きいため仕方ありませんが、加害者側の同乗者にも保険は適用されないのでしょうか。
同乗者が怪我をしても保険による救済は得られない可能性があります。
具体的には、無免許での運転を知っていた場合は、保険適用外または減額となります。これは、運転者の無免許運転を知っている場合、止めるべき義務や同乗しないという選択肢もあったと考えられるため、運転者と同様に過失ありと判断されるからです。
次に、無免許運転における種類や罰則をみていきましょう。
無免許運転の罰則について、加害者と同乗者を順に見ていきましょう。刑事罰と行政罰の両方が課せられることになります。
まず、通常の過失運転致死傷罪が適用される場合は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」(自動車運転処罰法5条)が課せられる可能性があり、無免許の場合は、罰則が過重され、「十年以下の懲役に処する。」と規定されています。
次に、純無免許などで、そもそも運転する技能を持ち合わせていないケースでは、危険運転致死傷罪が適用されます。
この場合、「技能を有しないで自動車を走行させる行為」にあてはまり、人を負傷または死亡させてしまった場合には、「1年以上の有期懲役」(自動車運転処罰法2条2項)が課せられる可能性があります。
また、飲酒運転かつ無免許運転であった場合は、罰則が過重されており、最大で「15年以下の懲役」が課せられる可能性があります(同法6条参照)。
道路交通法上は、無免許運転のみで、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」(同法117条の2の2第1項)が科せられる可能性があります。
同乗者に関しても、道路交通法条の罰則が規定されています。
具体的には、無免許であることを知りながら、同乗した場合、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」(117条の3の2第1項)が科せられる可能性があります。
同乗だけでなく、送迎の依頼をした場合にも罰せられます。この他には、運転車両の提供をした場合に、「3年以下の懲役または50万年以下の罰金」が科せられる可能性があります。
このように、加害者だけでなく、加害者側と考えられる同乗者にも罰則が規定されています。仮に、被害者になった場合は、同乗者に対する損害賠償請求も想定できます。同乗者にも過失があると考える場合は、弁護士に相談してみましょう。
最終的に、保険会社から損害賠償額については相談があります。損害賠償額について納得できる金額を提示してくれた場合は、そのまま交渉に応じ早期の解決を図るべきでしょう。
しかし、損害賠償額について納得できない場合は、一度専門家に相談することも大事です。任意保険の場合、交渉相手は保険会社でプロです。何度も示談をまとめています。また、できるだけ損害賠償額を安く抑えようとしている場合もあります。そのため、実際にもらうべき損害賠償額よりも低い額で納得させられてしまうこともあるのです。
このような事態を防ぐためにも、「何かおかしいな?」と思った時は、専門家である弁護士に相談する選択肢があることを心に留めておいてください。最近では、初回相談は無料の法律事務所もあります。相談することは決して損にはなりませんので、専門家の助言をもらうようにしてください。