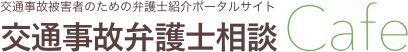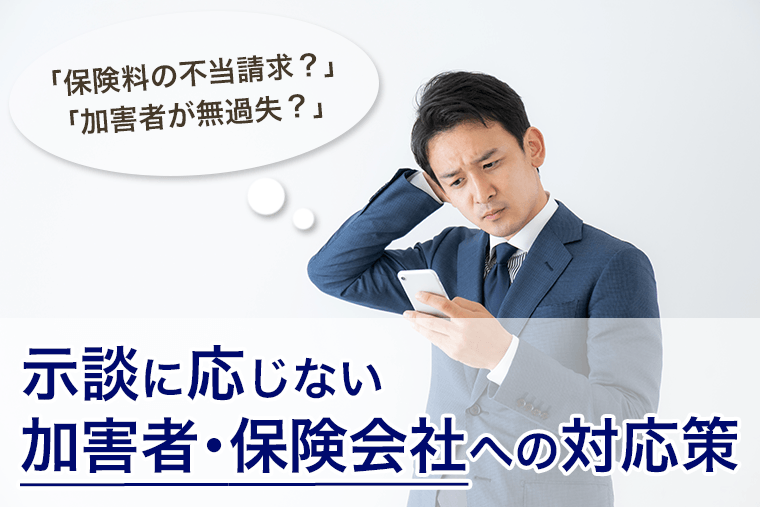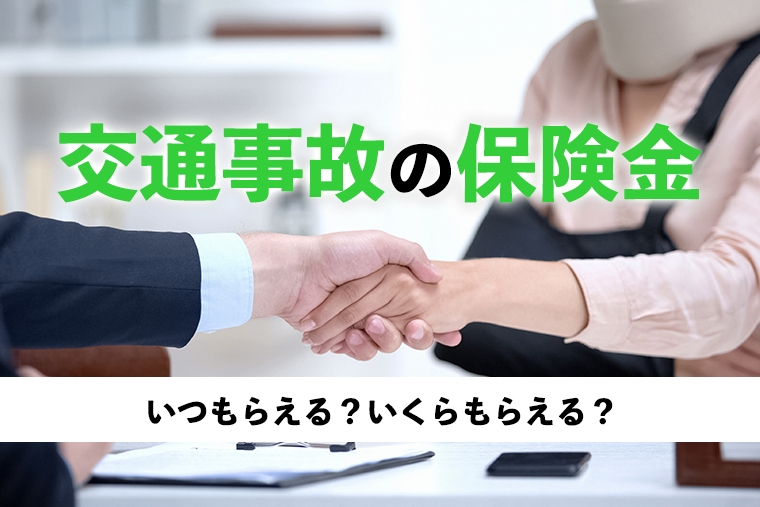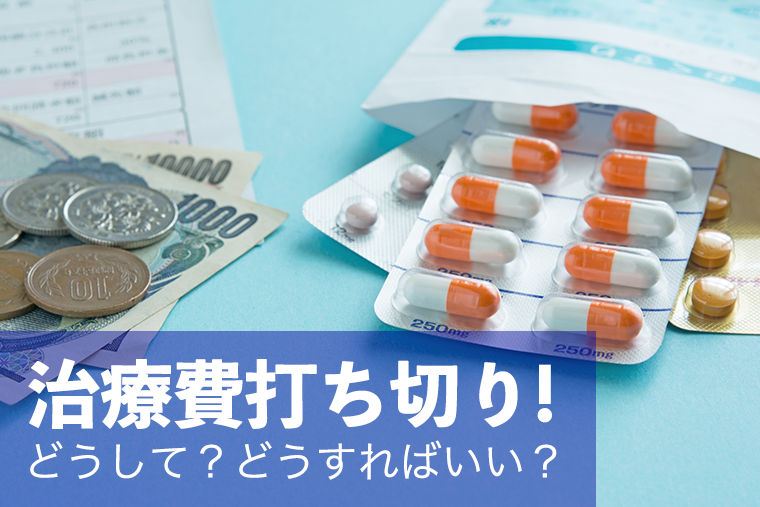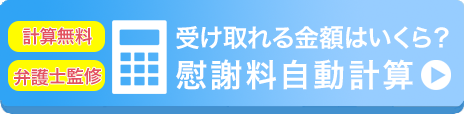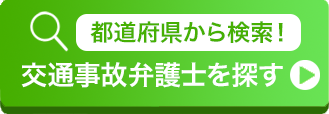過失割合の修正要素とは何?保険会社に任せてはいけない訳

ヘルメットを着用していなかったために大怪我をしてしまった、歩行者で信号を無視していたなど、被害者にも落ち度があるケースもあります。
このように被害者にも落ち度がある場合にも、加害者が被害者の被った損害をすべて賠償する責任を負うとするならば、不公平な結果がもたらされることになります。
そこで、被害者の過失割合に相当する金額を減額するというのが、民法に定められている過失相殺(722条2項)の考え方です。
この記事では、過失割合の修正要素とは何か?加算要素や減算要素などについて、保険会社に任せてはいけない訳を解説します。
過失割合の修正要素とは
過失割合の修正要素とは、実際の交通事故では、被害者の年齢、事故が発生した時刻、道路状況、道路の見通しといった付近の状況、など個別の事故状況を考慮し、基本割合に5~20%程度の修正を加えることを言います。
この、過失割合の修正要素を入れて、最終的な過失割合を算定することになります。
例えば、事故の一方当事者の居眠り運転があった場合など、事故状況に応じた修正をしなければいけない場合があります。
過失割合の基本はあくまで、典型的な交通事故の類型を前提としたものです。
修正要素には、加算要素や減算要素があります。
加算要素とは?
加算要素(事故の一方当事者にとって過失割合の増える修正要素):夜間、幹線道路、横断禁止場所、ふらつきなど
これらは、歩行者にとっての加算要素となります。
「夜間」では、見通しの悪さなどから、車の方からは歩行者を発見しにくいのが通常です。しかし、車は普通ヘッドライトを点灯しながら走行しているわけで、歩行者の方からは早くから車の存在に気付くことが可能です。
このため、夜間の交通事故については、歩行者に5%の過失割合が加算されることになります。車がヘッドライトを点灯していない場合には、逆に減算要素になります。
事故発生の場所が「幹線道路」である場合には、車の通行が頻繁なため、歩行者としては通行や横断をするときに特に注意する必要があるといえます。そのため、幹線道路で起こった事故の場合、歩行者の過失割合が加算されます。具体的には、横断歩道上の事故については5%、横断歩道外の事故については10%が加算されることになります。
この場合の「幹線道路」とは、車道と歩道の区別がある片側二車線以上の道路で、通行量の多い国道や一部の県道のことが想定されており、車の通行状況などから具体的に判断されることになります。
さらに、歩行者が、禁止されている行為である車両の直前直後を横断したような場合も、歩行者にとっての加算要素となります。
減算要素とは?
減算要素(事故の一方当事者にとって過失割合の減る修正要素):幼児・児童・老人、集団横断、著しい過失、重過失など
「幼児」とは6歳未満の者を、「児童」とは6歳以上13歳未満の者を指し、「老人」とは65歳以上の者を想定しています。
「集団横断」とは、集団登校のように、数人が同様な行動をとっていると見られる状態にあることをいいます。このような場合には、車の方から見て歩行者を発見しやすいはずなので、歩行者の過失割合は減ることになります。
*「重過失」とは、以下の悪質な違反を伴う過失態様をいいます。
- 居眠り運転
- 無免許運転
- 酒酔い運転
- 時速30キロ以上の速度違反
- 嫌がらせ運転など故意に準ずる加害
*「著しい過失」とは、重過失よりは程度の低い以下のような過失態様をいいます。
- 脇見運転など前方不注視が著しい場合。
- 酒気帯び運転。
- 時速15キロ以上30キロ未満の速度違反。
- 著しいハンドルまたはブレーキの操作ミス。
以上、いくつかの代表的な修正要素について検討しましたが、こうした修正要素に該当する事実関係について、必ずしも機械的に適用の有無が判明するものではない、という点にも注意が必要です。
例えば、「夜間」という修正要素を採りあげてみた場合に、深夜でも街灯が十分に明るいような場合はどうなるのか、また,日没直後でまだ十分明るかったような場合はどうか,このような場合には色々な解釈があり得そうです。
事故類型ごとの修正要素の適用の有無を判断する場面においては、その定義や趣旨を踏まえた検討が必要になることも多く、これらの判断が必要な事案もまた、専門家である弁護士の助力なしでは適切な解決が難しいものといえます。
特異性のある修正要素
バイクの場合
ヘルメットの不装着、禁止されている車体での二人乗り
ヘルメットの不装着により、頭部の外傷などの損害に繋がったケースの場合、著しい過失が認められます。この場合、ヘルメット不装着した人側の過失割合が10%増加した裁判例があります。これは、単車の運転者や便乗者には、ヘルメットを被る義務が課されていることから導かれるものです。
また、禁止されている50ccスクーターや、免許を取得してから1年未満の方の二人乗りの場合も、これらが事故を引き起こす危険性のある行為であることから、過失割合が増加する可能性があります。
自転車の場合
無灯火運転、傘差し運転、ヘッドホンの使用、ベルの不装着、サイズの合っていない自転車に乗っていた、など
これらの場合も、それぞれ「著しい過失」として、過失割合が増加する可能性があります。
交通事故の過失割合とは
過失割合とは、加害者、被害品双方の過失の度合いを割合で示したものです。
交通事故では,過失割合は非常に重要な問題となります。
被害者であっても、その過失割合が高いと,その分相手方に請求できる額が減ってしまうためです。
損害賠償額が1,000万円の事故の場合に、事故の発生について、加害者の過失70%に対して被害者の過失が30%あると認められた場合、被害者が請求できる賠償額は、過失相殺によって、700万円に減額されることになります。
実際に起こる交通事故の過失割合を最終的に判断するのは裁判所です。そして、過去に裁判所で争われた事故の状況を集めると、ある程度の類型化が可能で、当然ながらこれらの過失割合は類似することになります。
現在、弁護士や保険会社は、交通事故の裁判例が集積した別冊判例タイムズの『民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準』(通称『緑の本』)などの過失相殺基準表を用いて、交通事故の当事者間の過失割合を判断しています。
過失相殺基準表では、「歩行者と車の事故」「歩行者と自転車の事故」「車同士の事故」「バイクと車の事故」「自転車と車の事故」「高速道路上の事故」「駐車場内の事故」など、類型(基本要素)ごとに基本的過失割合が定められており、これに事故時の具体的な状況(修正要素)を加味して修正がなされるようになっています。
このように、基準表において、過失割合は、基本要素と修正要素とに分けて定められています。
基本要素
基本要素は、まず、道路交通法の優先関係によって判断されています(左方車優先、広路車優先、非停止規制車優先、優先道路走行車優先など)。道路交通法に違反した側が、大きな過失割合を負うことになります。次に、弱者保護の観点が加味されます(車両よりも歩行者、成人より老人、幼児を保護など)。
これらを併せて考慮して、基本的過失割合が定められています。
しかしながら、実際に起こる交通事故の態様は千差万別ですから、なかには明確に該当する類型がない特殊な交通事故も存在します。
このような事故に関しては、類似の事故態様に対して判断がなされた裁判例を参考にするか、『緑の本』に含まれる類型のうち類似のものを参考にして基本的過失割合を判断するしかありません。
このような場合、そもそもどの裁判例、類型が類似しているといえるのか,類似するとしてもそれをどう修正して基本的過失割合を決めるのか、の点は当然大きな争いになりやすいところです。こういった判断が必要な事案は、特に専門家である弁護士の助力なしでは適切な解決が難しいものといえます。
まとめ
このように、交通事故の過失割合や修正要素の解釈や適用に関しては、専門家以外には分かりづらく、複雑な側面が数多く存在します。それゆえ被害者の方が、裁判になった場合の過失割合の具体的な見通しを得たい場合には、保険会社にまかせきりにせず、弁護士による助言を得ることが最良の方策といえます。
また、被害者の方が、保険会社から提示された過失割合に納得できずこれを争いたいと考えている場合には、裁判所に過失割合を適切に認定してもらうことを見据えて証拠を確保する必要があります。しかしながら、事故の客観的な状況を把握するための必須の資料といえる刑事記録の入手にあたっては、たとえば刑事手続の進行状況など複雑な考慮が必要となります。
このような場合にも、交通事故に強い弁護士に相談して助力を得ることが、問題の解決に大きく近づく一歩となるはずです。
なお、参考までに、以下の緑のボタンを押して損害額と過失割合を入力するだけで、過失相殺後の示談金の額を知ることができます。是非、お試しください。