保険会社が治療費打ち切りを一方的に通達してくる理由と対処方法
治療費打ち切りが打診される理由やタイミングや期間などを紹介と、むちうち治療の打ち切り後の治療継続のポイント・自費なの…[続きを読む]
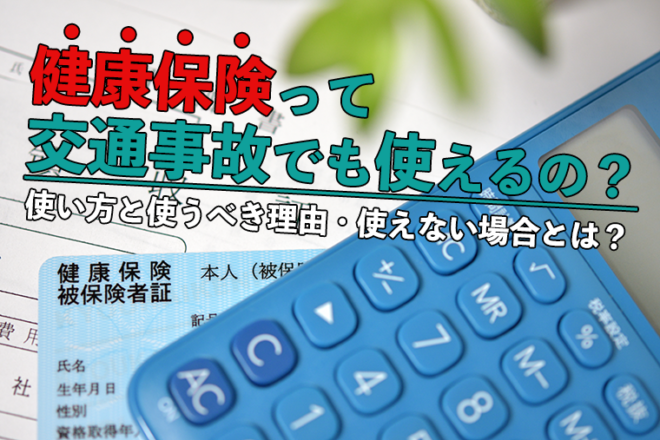
交通事故による怪我の治療の際に「病院では保険証が使えないと言われた」「拒否された」という方もいるかもしれせん。また「健康保険を使わないと損」と言われたかもいるかも知れません。
しかし結局のところ、健康保険を使えない理由がわからず、使用することができるのかできないのかお悩みの方が多いようです。
結論から申し上げると、交通事故の治療であっても健康保険は使えることは使えるのですが、交通事故で健康保険を使うことはメリット、デメリットの両面があり、使うべきではないケース、使うべきケースがあるのです。
交通事故で健康保険を利用するとはどういうことか理解したうえで、使用するべきか切り替えるべきか否かを判断する必要があります。
今回は、交通事故の怪我の治療に健康保険、国民健康保険を使用すべきか否か、交通事故で健康保険を使うデメリット、健康保険が使えない理由があるのか、過失割合との関係、使用すべきケースとはどのような場合なのかについて解説します。
目次
日本医師会は、次の通り指摘しています。
病院によっては健康保険の利用を拒否してくる可能性もあり、これが健康保険が使えない病院がある理由となっています。
交通事故診療を担う医療の現場では、不幸にも事故の被害に遭ってしまった患者に対して、できる限り早期に、かつ、事故に遭う前と変わらない状態で社会復帰させることが求められている。そのため、医療機関に搬送直後から患者の全身状態を素早く確認するとともに、あらゆる可能性を考慮しながら、早期に集中的な治療を行う必要があるのである。
こうした患者の治療に対し、法律、療担規則(※2)などの縛りの多い、いわゆる制限診療につながる現行の健康保険を適用するということは、結果的に十分な治療を提供できず、被害者の不利益につながる可能性があるという問題がある(*1)。
また、病院による拒否だけではなく、交通事故では、原則、健康保険を利用するメリットが少ないという点もあります。
なぜなら、健康保険で治療すると「医療費の窓口負担の支払いが必要」になり、これは大きなデメリットです。
また「治療に制約」があり、十分な治療を受けられないデメリットもあります。なぜなら、健康保険を利用する保険診療にすると、厚労省が認めた治療内容にのみ保険が適用されるからです。
※1「労災・自賠責委員会答申 諮問:地域医療再生における労災保険、自賠責保険の役割」19頁(平成24(2012)年2月、日本医師会労災・自賠責委員会)より
※2 療担規則:正式名称を「保険医療機関及び保険医療養担当規則」といい、健康保険法等に基づいて定められた政令で、保険診療を行う医療機関と医師の遵守ルールを定めたもの
しかし、一方で、任意保険会社が、被害者に健康保険の使用を勧めるケースがあります。Yahoo!知恵袋やブロクなどでもそのことがたまに話題になるようです。
結論から申し上げますと、任意保険が会社がすすめてくる理由は、安い治療費で自賠責保険の限度額内に収めさせ、任意保険会社が支払いを免れるためです。
このような要求には、次の通り大きな問題があります。
参考サイト外部サイト:「自賠責診療のこれからについて」(平成28(2016)年2月、日本医師会労災・自賠責委員会答申)32頁
以上のことから、原則は交通事故で健康保険を利用すべきではありません。

上記のようにデメリットはありますが、交通事故で健康保険を使うべきケースがあるのも事実です。
交通事故で被害者が健康保険を使用すべきは下記の5つのケースです。
それぞれに関して、解説致します。
加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社は、通常、自賠責保険の負担部分も含めた治療費を直接に医療機関に支払ってくれます。
これが「一括払い」という保険会社の事実上のサービスです。
ところが、治療費が自賠責保険の限度額を超えそうになったり、治療期間が長引くと、任意保険会社は自社の支出を抑えるため、「一括払い」打ち切りを通告し、もう使えないよと言ってきて、治療の終了を促します。
その際、本当に打ち切られてしまった場合、被害者はいったん自分で費用を支払って治療を継続することはできますし、また後に自賠責保険及び任意保険会社にその治療費を請求することもできます
治療を継続する際に一時的でも経済的負担に耐えることが困難ならば、健康保険の診療に切り替えて負担を軽くするべきでしょう。
自賠責保険は加害者が加入している保険から被害者が賠償を受け取る制度ですから、ひき逃げ等で加害者不明の場合は自賠責保険を使えないです。
この点では、加害者が自賠責保険に未加入の場合と同様に、政府保障事業を利用する前提として、必ず健康保険を利用しておくべきケースです。
被害者にも落ち度が認められる場合、過失相殺として損害賠償額の一定割合が減額されてしまいます。
もちろん受け取れることができる治療費も減額されるので、過失割合が大きいほど、治療費の自己負担額が増えてしまいます。
そこで、被害者側の過失割合が大きくなると予想される場合には健康保険での診療利用を検討するべきです。
というこで、過失割合が大きい場合に健康保険を利用すると、以下2つのメリットがあります。
上記の第2の効果については少々説明が必要なので、例を挙げましょう。
事例2.:被害者の過失割合が2割
治療費:100万円
治療費の内訳:患者自己負担30万円、健康保険負担70万円
上記のように、被害者の過失割合が0ではないケースもありますが、このケースで損害賠償として請求できる治療費は幾らでしょうか?
健康保険負担70万円は過失相殺の対象とならないので、過失相殺前に治療費100万円から差し引き、残額の30万円だけが過失相殺の対象となり、被害者の過失割合を乗じると損害賠償として請求できる治療費の額は、24万円となります。
一方でもしも、健康保険の負担も過失相殺の対象となるとしたら、どうでしょう?
治療費100万円のうち、20%すなわち20万円が過失相殺で減額されてから保険負担部分の70万円を差し引くことになります。そうなると請求できる治療費は、10万円となってしまいます。
被害者が請求できる治療費の額
| 健康保険の負担が過失相殺の対象外 | 健康保険の負担が過失相殺の対象 |
|---|---|
| 30万円 ×(100% - 20% )= 24万円 | 100万円 ー 20万円 ー 70万円 =10万円 |
このように健康保険を使用することで、過失相殺される金額も少なくできることになります。
以上の健康保険負担部分を過失相殺の対象から外す考え方(控除後相殺説、相殺前控除説、先相殺説ともいいます)は、多くの裁判例で採用されています(東京地裁平成28年5月20日等)。
実は、健康保険ではなく労災保険の給付があった場合については、逆に、労災保険給付の金額も過失相殺の対象とするのが最高裁の判例です(※1)。
この点、健康保険に関しては未だ最高裁判決がなく、仮に判決が出されると労災保険と同じ扱いとなる可能性もあります。
しかし、健康保険は「法律実務家の中では、健康保険は一応A説(過失相殺の対象としない考え方)だという暗黙の了解がありますから、今の段階ではあまり先を心配しなくてもいい」と弁護士向けの研修講義でも説明されています(※2)。
※1 最高裁平成元年4月11日判決
※2「弁護士専門研修講座・民事交通事故訴訟の実務-保険実務と損害額の算定-」東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編235頁
加害者が任意保険に加入していない場合は、賠償額が自賠責保険の限度額(傷害は総額120万円が上限)を超えた部分は、加害者本人に請求することになります。
しかし、任意保険に未加入の加害者に支払能力はないことが通常で、超過部分は被害者の自己負担となる危険性が高いのです。
そこで、健康保険を使って治療費を安くする必要があります。これはやむを得ない防衛策です。
健康保険が負担した治療費は、健康保険組合等から自賠責保険に対して求償権が発生し、一種の立替金として支払請求することができます(被害者に代わる請求なので代位請求と言います)。
せっかく健康保険で治療費を安く抑えても、健康保険側も自賠責保険に代位請求するなら、結局、限度額を超えてしまい、被害者が自己負担することになってしまうように思われます。
次の事例を使って考えてみましょう。
事例1.:交通事故の怪我の治療費が200万円
被害者の自己負担額:60万円
健康保険の負担額:140万円
傷害の自賠責保険限度額:120万円
被害者が治療費60万円を自賠責保険に被害者請求したところ、健康保険組合も自賠責に140万円代位請求していた場合、自賠責保険の限度額120万円を超えてしまいます。
では、被害者は60万円全額の支払いを受けることができないのでしょうか。
かつて、このケースでは、被害者請求の60万円と保険組合の140万円という各金額に按分させ、被害者は120万円の3割である36万円、保険組合は120万円の7割である84万円しか受け取れないという扱いでした。
しかし、最高裁は一連の判例で、被害者請求と保険組合の代位請求が競合した場合は、自賠責保険の被害者保護の趣旨などから、被害者請求を優先して認めるとしました(※)。
※老人保健法に関する最高裁平成20年2月19日判決
※労災保険法に関する最高裁平30年9月27日判決
※参考文献:「損害賠償額算定基準」平成21年版下巻107頁、同平成31年版下巻199頁
したがって、被害者は健康保険側の代位請求を気にせず、安心して健康保険を利用できます。
なお自賠責保険は、この判例にしたがい、健康保険組合から代位請求を受けたときには、被害者が被害者請求しないことを確認してから支払う扱いとしています。
例えば傷害の場合、自賠責保険の限度額120万円は、治療費だけでなく休業損害や慰謝料などの全損害項目を含むものなので、治療費が高くなれば、休業損害や慰謝料など他の損害賠償が受けられなくなる可能性が生じます。
そこで、治療費を安くし、余った限度枠を他の損害賠償金として受け取る目的で、健康保険を利用するケースもあります。
たしかに被害者の事情により、現金での賠償金が必要であれば、やむを得ない選択と言えます。
ただし、それは現金のために治療・健康を犠牲にしている面があることを十分認識して選択するべきでしょう。
加害者が任意保険だけでなく、自賠責保険にすら加入していない場合は、賠償額の全額を加害者本人に請求することになりますが、やはり加害者に支払能力がないことが通常です。
この場合は、国の「政府保障事業」による補償を受けることができますが、健康保険からの給付を受けることができる場合は、健康保険からの給付額は差し引かれます。つまり被害者が健康保険を利用しているいないに関わらず、補償額から治療費の7割は差し引かれてしまうので、この場合必ず健康保険を利用するべきといえます。
参考外部サイト:「政府の保障事業のご案内」損害保険料算出機構

ここまでの解説の通り、健康保険が使えないことはありませんし、使うべきケースがあるのも事実です。
それでは、交通事故で健康保険をどのように「切り替え」て使用すればいいのでしょう。
交通事故の怪我の治療に健康保険を使用するには、まずは「健康保険を使いたい」という意志を「病院」に明確に伝えることです。
その際に、健康保険に「第三者行為による傷病届」という書類を提出します。
手続きについて詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
交通事故で健康保険が使えないことはなく、普通い使えます。ただし、健康保険を使うと、制限診療につながり、結果的に十分な治療を提供できず、被害者の不利益につながる可能性があるという問題があることは覚えておきましょう。
「労災事故」つまり、通勤中・業務中の交通事故の場合は、「労災保険」が優先的に適用されるため、健康保険は基本的に使えません。
交通事故と健康保険について切り替えが可能か、また健康保険が使えない病院(拒否する病院)がある理由などについて解説しました。
交通事故に健康保険、国民健康保険を使うことができることと、被害に遭われたあなたやご家族が使うべきケースかどうかは別の問題です。
ここで説明した通り、様々な場面がありますので、判断に先だって弁護士に相談されることをお勧めします。