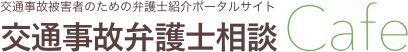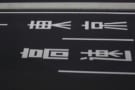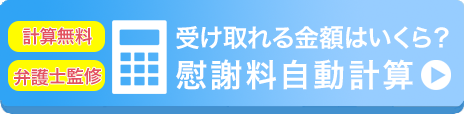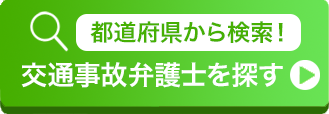右側走行違反の自転車が交通事故の被害に!過失割合の考え方とは?

自転車で、仕方がなく右側走行をしていた時に、左側走行している自動車やバイクと衝突してしまった場合、過失割合はどうなるのでしょうか。
道路交通法自転車は原則として道路の左側を走行しなければいけないとされていますので、右側走行をしていた被害者の自転車は違反を犯していることになります。
この記事では、右側通行の自転車と衝突したときの過失割合について、自動車の場合、バイクの場合、自転車同士の場合の3つに分けて解説いたします。
目次
自転車に左側通行が義務付けられている理由
そもそも、なぜ自転車は左側を走行しなければいけないとされているのでしょうか。
出合い頭の衝突を回避できる可能性が高くなる
自動車で見通しの悪い交差点に進入しようとするところを想像してみてください。
日本では自動車は左側を通行することになっていますので、自転車が右側通行であなたの左側から交差点に進入しようとする場合、自転車が死角となってお互いの発見が遅れます。また、車と自転車の距離が短くなることから、出合い頭に衝突してしまう危険が高くなります。
左側通行をしていればお互いを目視で確認することができますし、万が一発見が遅れたとしても、自動車と自転車の間に距離があるので急ブレーキやハンドル操作によって衝突を回避できる可能性が高くなります。
これが、道路交通法が自転車も左側通行を定めている理由です。
自動車対自転車の過失割合は8対2
では、自転車が右側走行していて、対向してくることとなる自動車と衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合、基本過失割合は自動車が80%、自転車が20%となります。つまり、自転車が被害者となります。
これには「自転車が違反をしているのに、どうして自転車の過失が小さいのか?」と驚く方が多いと思います。
自動車の過失が大きい理由① 自転車は「交通弱者」「弱者救済の論理」
自転車側の過失が小さくなるのは、自転車という乗り物が自動車と比べて弱い立場にあり、いわゆる「交通弱者」であることが理由です。
もしもスピードを出している自動車と自転車が正面衝突をしたとしても、自動車のドライバーが怪我をする可能性は低いでしょう。一方、自転車は間違いなく大破し、自転車を運転していた人は即死してしまう可能性もあります。
このように、自転車は交通事故が発生したときに受けるダメージが大きいので、自動車のドライバーは、弱い立場にある自転車との交通事故を回避するため十分に注意しながら運転しなければいけないとされているのです。
たしかに最近では、自転車が加害者となる事故が増加していることから、自転車の交通違反を取り締まる道路交通法の規定が強化されるなど自転車も交通ルールを順守するべきだという風潮が強まっています。ですが、自動車との関係では相対的に弱い立場であることには変わりはないのです。
自動車の過失が大きい理由② 自転車の乗り物としての特性
自転車の乗り物としての特性も過失割合に影響します。
自転車を自動車と違って運転するにあたって運転免許が不要で、幼児、小中学生から高齢者まで気軽に運転することができるため、自動車と比べて突発的な動きをする可能性が高いといえます。そのため、「強者」である自動車のドライバーは、自転車が突発的な動きをすることまで想定し、事故を回避するための措置をとらなければいけないのです。
自動車の過失が大きい理由③ 自転車の発見が容易
自動車側に大きな過失が認定されるもう一つの理由は、自動車が自転車を容易に発見できるからです。
すでに説明したとおり、自転車に左側通行が義務付けられているのは、自転車の右側から交差点に進入してくる車の死角に入ってしまうためです。
しかし、自転車が道路の反対側を右側走行してきた場合、自動車の目の前を自転車は走行してくることになります。自動車のドライバー自転車を発見し、自転車との衝突を避けるために徐行などの措置をとることは難しいことではありません。
自転車が右側走行の違反を犯していたとしても自動車側に大きな過失が認められるのはこれらの理由からです。
過失割合の修正要素
では、被害者である自転車側の過失を増えることはないのか?というと、そうではありません。
過失が増える理由の一つは、加害者側のドライバーが修正要素を主張するからです。
交通事故の過失割合は、個別の事故状況に応じた修正要素を基本過失割合に加算または減算することで算出されます。
自転車に過失が加算される場合
自転車が右に左とフラフラ動きながら不安定に走行していた場合には、自動車は衝突を回避することが困難になります。そこで、自転車側に10%の過失が加算され、自動車と自転車の過失割合は7対3となります。
自転車に酒酔い運転、脇見運転、二人乗り、制動装置不良、夜間の無灯火運転といった著しい過失があった場合には、やはり自転車側に10%の過失が加算され、自動車と自転車の過失割合は7対3となります。
自動車に過失が加算される場合
逆に、修正要素により自動車側に過失が加算されることもあります。
自転車の運転手が児童や高齢者だった場合には、自動車のドライバーはいつも以上に注意して走行する義務があります。そこで、自動車に10%の過失が加算され、過失割合は9対1となります。
自動車のドライバーに居眠り運転、無免許運転、時速30キロ以上の速度違反、道交法上の酒酔い運転などの重過失があった場合には、過失の重さに応じて自動車に10%から20%の過失が加算されます。20%の過失が加算された場合には、自転車の過失は0となり、完全に自動車側に過失のある事故となります。
さらに、自動車が前方不注意をしていた場合には15%の過失が、見通しがよいにもかかわらずわき見運転をしていたなど著しい前方不注意が認められる場合には30%の過失が加算されます。30%の過失が加算された場合は、仮に自転車側に10%の過失を加算する修正要素があったとしても、自動車側の過失が100%とされます。
バイク対右側走行の自転車の過失割合も8対2
次に、バイクを運転していて道路の反対側を右側走行してきた自転車と衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合も、自転車がバイクと比べて弱い立場にあるという点では自動車の場合と同様です。バイクは自動車との関係では交通弱者ですが、自転車との関係では強者ということになるのです。したがって、基本過失割合は自動車の場合と同様にバイクの過失が80%、自転車の過失が20%となります。
修正要素があるときに基本過失割合に加算または減算される点も自動車と自転車の事故の場合と同様です。
過失割合を争ってきた場合
自転車の右側走行は、厳密にいえば交通違反であることはたしかです。しかし、必ずしも違反をした方に大きな過失が認定されるわけではないということがおわかりいただけたかと思います。
加害者側の保険会社が、被害者側の自転車の過失を大きくしようと、過失割合を争ってくることががあります。対抗するにはどうすればよいのでしょうか?
交渉の手段
加害者側は、一修正要素を主張してきます。特に相手方の自転車がフラフラ運転、傘さし運転、スマホを見ながらのわき見運転など、右側通行以外にも交通違反を犯していた場合には、過失割合が修正されることが多いでしょう。これらの事実を主張するためには、ドライブレコーダーによる映像など客観的な証拠を元に主張されることがあります。
また、自転車同士の事故の場合には判例の蓄積による基準が乏しいため、交渉によって過失割合が大きく変わる余地が大きいでしょう。
保険会社との交渉を弁護士に依頼するメリットとは?
ここで問題になるのは、過失割合を交渉する相手は、何百件もの交通事故を取り扱ってきた保険会社の担当者だという点です。知識や経験に大きな差があるなか、交渉を有利に進めることは容易なことではありません。
そこで、被害者の自転車側は、交通事故に精通した弁護士に保険会社との交渉を依頼することが、過失割合を変更するための有効な手段となります。
過失割合の交渉は、「双方の当事者にどのような注意義務があったのか」、「注意義務を怠ったことが事故に繋がったのか」、「注意義務を怠ったことに対する証拠があるのか」といった法律的な議論になります。
弁護士費用は?
弁護士に依頼するためには、当然のことながら費用がかかります。しかし、交通事故の相談は無料で受けている弁護士も多いため、まずは相談してみるというのは一つの手です。
任意保険に弁護士費用特約が付いている場合には費用を負担することなく弁護士に依頼できます。弁護士費用特約を使うことによるデメリットはほとんどありませんので、これを利用しない手はありません。弁護士費用保険は自分の保険に付いている場合はもちろん、家族や同乗者の保険に付いているものを利用できることもあります。ただし、自転車同士の事故の場合には利用できませんので注意が必要です。
さいごに
弁護士は法律と交渉事のプロですので、保険会社の担当者と対等に交渉を進めることができますし、代理人として交渉や手続を全て行ってくれますので、煩わしさからも解放されます。
自転車で右側通行してしまった自動車・バイクとの事故で、自動車側の保険会社側の主張する過失割合に納得がいかないときには、被害者である自転車は、一度交通事故事件に強い弁護士に相談してみることをお勧めいたします。