後遺症の異議申し立てで12級になった例|後遺障害14級9号から12級へ
例えば、交通事故によってむちうちやヘルニアなどの後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受ける際、その等級が異議申し…[続きを読む]
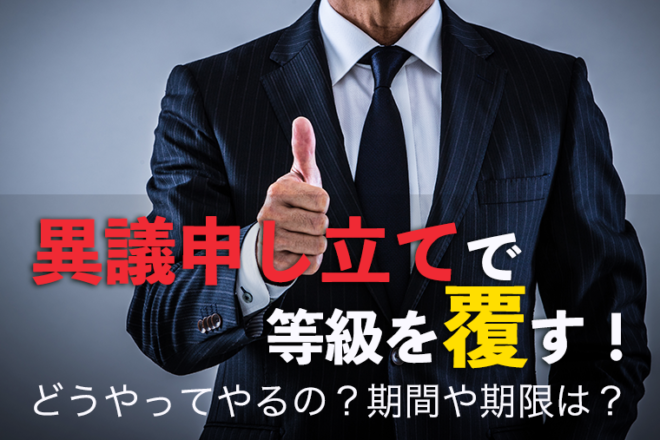
後遺障害の異議申し立てをすることで「非該当から14級」「14級から12級」と、認定結果を覆すことができる場合があることをご存知ですか?
交通事故における後遺障害の異議申し立てについて、下記のような悩み・疑問を持つ方が数多くいらっしゃいます。
後遺症が認定で、一度出た結果を覆すことが厳しくとも、正しいポイントを抑えて申請すれば、異議申し立てが成功する確率は上がります。
この記事では、正しい異議申し立ての方法とポイント、異議申し立て書の書き方や必要書類、例文、書き方、期間や日数、弁護士への依頼や弁護士費用について、医療照会などについて解説します。
なお、実際に後遺症の異議申し立てで12級になった例は下記の記事で解説します。
目次
異議申し立てをする前に、なぜ自分の希望に沿うような認定結果が出なかったのか、失敗するのかを充分に分析する必要があります。
そこで、思うように自賠責の後遺障害が認定されない主な理由について説明しましょう。
まず考えられるのが、後遺障害診断書の記載が不十分だったというケースで失敗しがちです。
具体的には、下記のように判断されるケースが多いようです。
特に、他覚所見が認められにくい「頚椎捻挫(俗称:むちうち)」や「腰椎や頚椎の椎間板ヘルニア」では、上記のような理由で非該当になる可能性が高いと言われています。
しかし、CTやMRIなどの画像所見がない場合でも、神経症状があり、それがしっかりと後遺障害診断書に記載されている場合、後遺障害が認定される可能性もあることから、最後まで決して諦めてはいけません。
医師は普段から業務量が多く、医療行為ではない後遺障害認定に必要な検査・診断書の作成などに積極的ではないケースがあり、失敗しがちです。
そのために、後遺障害認定を得るために必要で正しい検査を行えていないのが実情です。
「検査結果の画像がない」「画像があっても不十分」といった場合には、認定は得られません。
また、医師が後遺障害認定手続きに関わることに慣れていないケースもあるため、異議申し立てをする際には、その点を見直す必要があります。
交通事故と受傷の因果関係が証明できないことがあります。下記のような場合です。
ただし、交通事故と受傷の因果関係が一度否定された場合も、訴訟などを行い認められる例もあります(*訴訟内容については、後述致します)。
すぐに、あきらめずに交通事故解決の実績がある弁護士など法律の専門家と相談しながら、粘り強く認定作業を進めていくことが大切です。
これは、むちうちの症状などに多い理由です。
後遺障害認定は、完治せずに残ってしまった症状について適切な補償を受けるためのものなので、将来的に症状の回復の見込みがないことが認定の要件となります。
むちうちの事案によっても異なりますが、特別な事情で認定条件を達成できていない可能性もあります。
条件をクリアできるかどうかは、医師や弁護士とよく相談する必要があるでしょう。
後遺障害認定の異議申し立てで大切なのは、上記のような不十分な点を解決して再申請することです。
前回と同じ資料を送り直すだけでは、成功率は高まりません。
まず、新たな「後遺障害診断書」や「検査」を充実させることが重要です。
まず、自身の現在の症状(残存している障害)を後遺障害診断書に明瞭に記載してもらう必要があります。
医師が「交通事故と残存症状との間に因果関係が認められる」または「将来的にも回復が難しいと見込まれる」と診断している場合、その診断内容が適切に反映されるよう、後遺障害診断書の作成方法について工夫を依頼しましょう。
ただし、医師にも独自の判断や立場があるため、明確な断定を避けたり、患者の希望通りに診断書を記載できないこともあります。
このような場合でも、自分の要望を無理に押し付けるのではなく、医師とのコミュニケーションを丁寧に行い、どのような表現が許容されるかなどを柔軟に話し合う姿勢が大切です。
さらに、医学的証拠を充実させる手段として、新たな検査を実施し、併せて、医師に意見書(※)を書いてもらうのも良いでしょう。
※医師による「意見書」とは、診断書の内容を補完するため、認定されるべき後遺障害等級が何級かについて根拠や意見を記載したものです。事故と後遺症の因果関係や、症状が回復困難であることを詳細に示します。高次脳機能障害など重度・複雑な後遺障害の場合に作成することが比較的多いですが、むちうちなど軽度の後遺障害でも添付する場合があります。
むち打ち症の場合など、CTやMRIの画像で、他覚症状を証明するのが困難なことがあります。
そんな時に弁護士が利用するのが「医療照会」です。
弁護士が用意した質問事項を記した書面について担当医に回答してもらい、異議申立書の添付書類として提出します。
異議申立書に添付することで、等級を覆す確率がアップする可能性があります。
異議申し立てを成功させる確率をアップさせるために、先述した新たな資料を元にして「現在の認定は適切ではない」ことを主張する反論文を書く必要があります。
例えば「事故の状況との整合性」や「事故直後から症状固定に至るまでの症状の整合性」などをしっかり説明する必要があるでしょう。
特に、交通事故と残存症状との間に因果関係が認められないという理由だったのであれば、事故の状況をしっかりと説明する必要があります。
このような説明は「異議申立書」により主張することになります。
後遺障害の異議申立書には、決まった書式や書き方はありませんが、以下の事項を記載する必要があります。
後遺障害の異議申立書の例文を次に挙げておきますが、記述内容については個別の事案によって大きく異なります。
詳しくは、交通事故解決の実績がある弁護士に相談すると良いでしょう。
異議申立書は、加害者が加入している自賠責保険会社に頼めば送ってもらえます。
申立書の理由を記載する欄は非常にせまいので、別紙をつけるなど詳細に書く必要があります。
事故の相手方である任意保険会社に手続きを任せてしまう「事前認定」によっての申請では、手続きの透明性が保たれているとはいえません。
相手の保険会社の顧問医が、「通院は不要だった。2週間程度で十分だった」など、被害者が不利になりやすい意見書を添付している可能性もあります。
そこで「被害者請求」の方法で手続をする必要があります。
被害者請求の場合、自分自身で提出書類を準備します。つまり、提出する書類の記載を自分でしっかりと確かめ、書類をきちんと揃えた上で提出することができるのです。
後遺障害認定の異議申し立ての回数に制限はあるという疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。
後遺障害認定の異議申し立ては、何回でも行うことができます。
ただ、新しい証拠を添付して申し立てを行わないと、判断が覆る可能性は非常に薄いことは念頭においておきましょう。
実際の後遺障害の異議申し立ての流れは、以下の「6ステップ」になります。
- 通知書をもらう
- 必要書類(新たな医学的資料・証拠)を集める
- 被害者請求へ切り替える
- 書類の提出
- 審査
- 再度の通知
まず「後遺障害等級認定票(後遺障害認定通知書)」「事前認定結果のご連絡」を入手する必要があります。
すでに被害者請求をしている方は、手元に原本が送られてきていると思います。
事前認定だった方で、通知書が手元にない場合は、保険会社からコピーをもらいましょう。
次に、新たな必要書類を集める必要があります。具体的には、先述した以下のようなものです。
なお、上から4つ目の「陳述書」とは、事故の当事者の記憶に基づいて作成する書類のことで、主に自分の現在の状況(どのような症状があり、どのように生活や仕事に影響しているかなど)を記載します。作成は弁護士に依頼することができます。
また、事故の状況と症状との整合性を説明するために、実況見分調書を取り寄せて、事故の状況を説明するような陳述書を作成することも有効です。
「新たな診断書や医師の意見書が必要なのに、医師に協力を断られた」という場合にも、あきらめずに交通事故解決の実績がある弁護士に相談してみましょう。
後遺障害等級認定手続きには、被害者請求と事前認定があります。
初回に、事前認定で手続きを行った人は、異議申し立てをする際に被害者請求に切り替えましょう。
方法としては、任意保険会社と加害者の加入する自賠責保険会社に「被害者請求で異議申し立てをする」ということを伝えます。
そうすると、任意保険会社が所持していた後遺障害認定のための資料は自賠責保険会社に引き渡されますので、その後は自賠責保険会社に直接請求をすることになります。
なお、加害者が加入している自賠責保険は、交通事故証明書に記載されています。
被害者請求に切り替えると、自分が直接、加害者の自賠責保険に必要書類を送ることになります。
異議申し立てがあると、一般的には、初回に後遺障害の判定をした、損害保険料率算出機構の調査事務所の属する地区本部または本部で審査がされます。
また、本部の審査に対する異議申し立ては、専門医の参加する自賠責保険後遺障害審査会で審査されます。
被害者請求をした場合、異議申し立ての審査結果は、自賠責保険を通じて被害者のところに送られてきます。
後遺障害認定の異議申し立ては、何回でも行うことができます。
もしも、異議申し立てが却下されたら、訴訟により争うことや、紛争処理申請を行うことも考えられます。
後遺障害の非該当を巡る異議申し立ては、手続きや書類作成は比較的単純で、被害者自身でも進めることが可能です。
ただし、異議申し立てが受理されるためには、追加の書類が必要であり、それを収集するにも時間や手間がかかります。また、成功する保証はありません。
さらに、適切な異議申立書の作成や医師に新たな診断書を依頼することは、素人にとって難しい場合があります。
このような場合には、交通事故解決の経験が豊富な弁護士に相談することが重要です。
成功の可能性が高まれば、弁護士に依頼する価値があります。成功すれば、弁護士費用がかかっても経済的にはプラスになることもありますので、決してすぐにあきらめないことが大切です。
特に異議申し立てで却下されやすいと考えられる神経症状などで、後遺障害等級12級・14級になることを目指す際は、後遺障害非該当に詳しい弁護士に一度ご相談することをおすすめします。