警察で事故証明(物損・交通事故証明書)の発行方法|後日どこでもらえる?
交通事故証明書とは何か、内容、取得方法、使い方、取得期限などについて、わかりやすく解説します。交通事故被害者の方で、…[続きを読む]
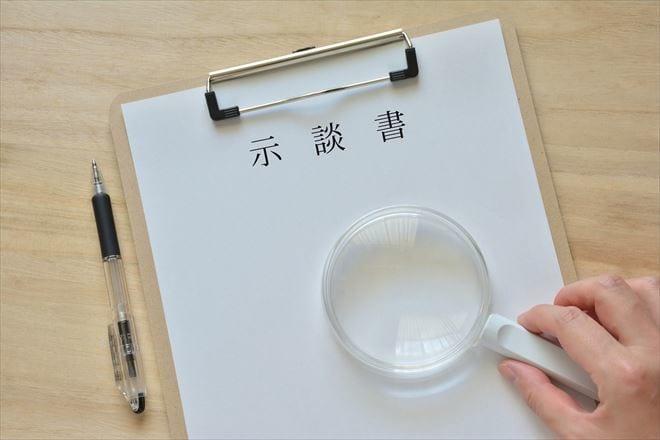
交通事故で示談交渉を始めるにあたり、準備しておくべき書類には何があるでしょうか。
この記事では、人身事故、後遺障害事故、死亡事故、物損事故に分けて、交通事故の示談交渉の準備方法と必要書類について説明致します。
なお、この記事は、示談交渉のための書類についての解説ですので、自賠責保険の被害者請求に必要な書類については解説しておりません。自賠責保険に必要な書類につきましては、別の記事をご参照ください。
では、被害の種類別に解説してゆきます。
目次
事故証明書は事故の事実を簡潔に示す基本的書類として入手しておくべきです。
事故を警察に届けていると、各都道府県の自動車安全運転センターから発行されます。
保険会社が事故に介入する場合は、保険会社が取り寄せていますので、そのコピーをもらうことが可能です。
診断書は、事故による受傷の事実を証明するものとして必要です。
事故後は時間をおかずに受診しましょう。
警察に人身事故として届出する場合の必要書類でもありますし、事故から間があいてからの診断書だと困ることが生じます。
示談交渉においてケガと事故の因果関係を否定されるリスクがあります。
診療報酬明細書には、受けた治療の内容と、その費用がすべて記録されています。
この書類は、事故による怪我やケガの治療費や、入院・通院に伴う精神的苦痛(慰謝料)を算出する際に必要不可欠な資料となります。
源泉徴収票などは、被害者の収入を明らかにするものです。
人身事故の場合、怪我をしているので仕事を休むことになり、「休業損害の算定」をする必要があります。
当然ですが、被害者が取得して提出するものです。提出の際はコピーを残しましょう。
休業した日数(遅刻や早退含め)を明らかにするものです。
各保険会社が用意している定型の書式が休業損害証明書でサラリーマンの場合などはこちらを利用します。
休業損害証明書は勤務先が加害者側に対して休業損害の内容を証明する書類ですから、被害者が勤務先に依頼して発行してもらい、相手方に渡すものです。もちろんコピーを残しましょう。
自営業などの場合は、休業日数を記入した休業証明書を被害者が作成して相手に渡すことになります。
通院交通費や雑貨費(寝具、衣類、洗面具、タオルなど)の金額を明らかにするため必要です。
これも被害者が取得して提出するものです。提出の際はコピーを残しましょう。
傷害事故で必要な(a)~(f)に加えて下記の書類が必要です。
後遺障害の有無とその内容を明らかにするために医師に記載・発行してもらうものです。
自賠責保険に被害者請求する際には、後遺障害診断書を提出することで、後遺障害等級の審査が行われることになります。
自賠責保険により認定された後遺障害の等級を明らかにするものです。
自賠責保険からの後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益は、認定された等級を基準として算定されるので必要になります。
加害者側の任意保険会社が一括対応をしているケースでは、等級認定は加害者の任意保険会社が行い、等級認定票も自賠責保険から任意保険会社を経由して被害者に送付されます。
後遺障害で車イス、松葉杖や、義手、義足など装身具が不可欠となった場合は、その費用も請求できますので領収書を提出します。
将来にわたって装身具を買い換える必要があるときなどは、将来費用の見積書も提出します。
自宅のバリアフリー改装費やエレベター設置費、車両の改造費などを支出した場合や将来の支出が必要な場合は、その領収書、見積書も提出します。
なお、傷害事故での「(d)給与明細書・源泉徴収票・確定申告書の控え」は、後遺障害事故では、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を算定するための資料にもなることに留意しましょう。
次に「物損だけの事故」と「人身事故のうち物損の部分」の示談交渉で必要な書類について主なものを説明します。
事故車両の写真は、必須ではありません。
ただ、事故状況を理解できる資料として準備しておくのが良いでしょう。
修理代金明細書などは、修理工場から入手します。
保険会社が介入する場合は、アジャスターとの修理費協定の前提として各書類は保険会社が入手しています。
全損の場合は車両の時価を明らかにする資料を用意する必要があります。通常、使われるのは以下の資料です。
なお、全損のときは、車両買替えにかかる諸費用(税金、登録等手数料、リサイクル関連費用、廃車費用等)についても資料をそろえて請求を忘れないようにしましょう。
死亡の事実とその原因を明らかにするものです。
検案書は死因・死期などを医学的に確認した結果を記載した文書、死亡診断書は患者を生前から診療していた医師が死亡を確認して作成する診断書です。
いずれも病院に書式が備えられており、医師から発行してもらいます。
被害者の相続人であること、親族であることを明らかとする資料として、本人の戸籍謄本類が必要となります。
具体的には、死亡した本人の出生から死亡時点までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)及び相続人の戸籍謄本です。
これらは被害者側で取り寄せる必要があります。
葬儀費用、墓石費用なども領収書を提出します。
僧侶へのお布施など領収書を発行しない費用については正確に記録した明細一覧表を作成して提出します。
また、事故から死亡まで期間がある場合は、その間の損害については傷害事故と同内容の賠償請求が可能です。
傷害事故の必要書類である(a)交通事故証明書、(b)診断書、(c)診療報酬明細書、(d)給与明細書・源泉徴収票・確定申告書の控え、(e)休業損害証明書・休業証明書、(f)交通費や日用雑貨品などの領収書が同様に必要となります。
そして、(d)給与明細書・源泉徴収票・確定申告書の控えが、死亡慰謝料及び死亡逸失利益を算定する資料となります。
即死の場合は、(a)交通事故証明書、(d)給与明細書・源泉徴収票・確定申告書の控え、が必要となります。
当事者同士で示談交渉をするケースでは、次のようにチェックしてください。
賠償金はすべて金額、すなわち数字の問題ですので、1円単位まで、いかなる名目なのかをハッキリとさせてください。
「諸費用」などという項目や「概算」などという損害額は存在しません。
(最終的な段階で丸めた数字で妥協するという場合は格別ですが)、そのような内容不明な請求をするべきではありません。
各内訳(項目)の数字が1円単位で明らかになったら、次はその金額が正しいかどうかを裏付けている証拠資料はどれかを探してください。
何も証拠資料がない金額を請求すること、受け入れることは厳禁です。
なお、慰謝料のように領収書などで裏付けられない金額については、弁護士基準(裁判所基準)に基づいて算定します。
以下のような資料が参考となります。