むちうちは週1?週4?治療期間と通院頻度を保つべき理由は慰謝料!
追突事故などによる「むちうち」は、後遺障害で一番多い傷病と言われています。治療に疑問を抱く方も多い傷病です。通院期間…[続きを読む]
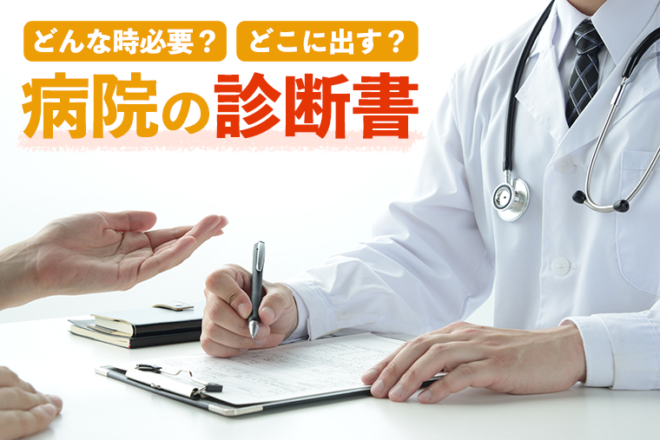
交通事故の被害に遭って、むちうち等になると、病院が発行する「診断書」を、関係各所に提出する必要があります。
そして、診断書を提出しようとしている皆様の中には、出さないのか、またもらい方やすぐもらえるのかなどの疑問など、下記のような疑問を感じている方もいるでしょう。
この記事では、Twitter、ブログやYahoo!知恵袋でも話題の
について、解説します。
目次
まず、出す出さないの前に、診断書には具体的にどのような内容が記載されているのか確認してみましょう。
交通事故における診断書の主な内容は次の通りです。
ここに、傷病者や受診した病院名、診断した医師の署名・押印がされます。
人身事故の診断書の中で、最も重要な項目といっても過言ではないのは「治療日数」です。
「治療日数」や「全治」と聞くと、怪我や症状が治るまでの期間はそのくらいかかると考えがちです。
しかし、診断書に書いてある治療期間は、あくまでも目安であることを覚えておきましょう。
例えば、「事故直後に医師からもらった診断書では、全治2週間だったが、2週間を過ぎても治らない」といった不満をよく聞きます。
実際のところ、診断書の治療日数よりも、治療に要する期間が伸び、むちうちや骨折の完治まで時間がかかるケースが多いです。
また、診断書の治療日数は、被害者の問題だけにとどまらず、交通事故の加害者になってしまった場合も、とても深刻な問題の一つとなります。
なぜなら、被害者が提出する診断書によって、加害者が受ける処分(点数、刑事責任等)に大きな違いがあるからです。
交通事故のケガで診断書を取得する際には、文書料という費用がかかります。
相場としては、自賠責保険請求用のもので3,000円程度、後遺障害診断書で5,000円から10,000円程度が相場です。
しかし、ご安心ください。
いったん立替が必要なケースもあるにはありますが、文書料は損害賠償金の項目に含まれるので「相手の保険会社」が費用を負担し、支払いを受けることが可能ですので、安易に診断書出さないでいいのではと考えないでください。
診断書は何枚必要になるかというと、主に下記の3箇所に提出する枚数が必要になります。
それぞれ目的、用途、期限などは異なります。
どんな目的でどこに診断書を提出するのか、またよくある疑問などを、それぞれ下記確認しましょう。
交通事故で「ケガをした場合」、まずは警察に診断書を提出します。
警察に診断書を提出することで、人身事故として扱ってもらうことができ、加害者の保険会社に「慰謝料など請求」することができます。
提出しない場合は、単なる物損事故扱いになり、出さないとデメリットが大きく、加害者に治療費・慰謝料などは原則的には請求できなくなります。
また、交通事故センターから人身事故としての事故証明書を発行してもらうことができます。これは事故の事実を証明する証拠のひとつとなり、加害者の保険会社などに賠償金を請求する際の提出書類として利用できます。
①と本質的には同じメリットではありますが、中でも特に強調したいテーマとして「切り替え」があります。
交通事故当初に怪我の自覚症状がなく、数日後~2週間後に、怪我の症状が出てくるケースがたまにあります。その場合は、最初は出さない状態だと思いますが、必ず出す必要が生じます。
その際に、警察で物損事故から人身事故に切り替える際に、診断書を追加提出する必要があります。
そして切り替えがあって診断書を出されると、加害者にとってはデメリットがありますが、点数や免停などの行政処分など、これは致し方ないと言えるでしょう。
人身事故届のために警察に診断書を提出すべき時期については、法律上や制度上の提出期限はありません。
また、まれに、警察が診断書を受け取ろうとしないケースが有り、出さない人がいるそうです。
警察は民事不介入という立場です。ケガが軽微で悪質性がなければ、刑事罰の対象となることは多くはないので、受け取ろうとしないのです。
しかし、被害者には、診断書を提出して人身事故とする権利があります。
もし、どうしても受け取らないのであれば、交通事故に強い弁護士に相談するのが良いでしょう。

直接「相手が加入している自賠責保険会社」に診断書を提出する場合があります。
被害者自身が直接自賠責保険の請求をする「被害者請求」を行う場合です。
通常、自賠責保険への請求については、相手の任意保険会社が一括対応することが通常ですので、その場合は提出は不要です。
自賠責保険の請求のための診断書は自賠責保険会社にて書式があるので、それを取り寄せて医師に渡し、記入して作成してもらいます。
会社務めの場合、交通事故のケガが原因で仕事を休む際に、勤務先の会社に提出するための診断書が必要となります。
診断書には通常の内容の他に、事故のケガにより職場で「就労ができない」旨を記載してもらう必要があります。
また、診断書は原則的には「原本」を提出することになりますが、職場の場合はコピーでも許される場合もあります。
事前に会社に確認するのが面倒な場合は、出さないとなるのではなく、原本を提出するのが無難でしょう。
なお、会社を休業した場合は、休業損害なども請求できるので、その旨を留意しておきましょう。
交通事故後、むちうちになった場合など、診断書は、診察した病院の医師に依頼して作成してもらいます。
ただ、追突事故でむちうちになると、病院で医師に全治2週間などと言われたが、なかなか症状が改善せず「整骨院」にかかるケースがあります。
しかし、診断はあくまで病院の医師が行うものなので、まずは整形外科に行って医師に診断書を書いてもらいましょう。
むちうちなどで整骨院などに通いたい場合には、まず整形外科に通院治療をした後、医師に相談して、その指示を受けてからにすべきです。これを怠ると、保険会社や裁判所に、整骨院などでの施術の有効性、相当性を認めてもらえず、治療費などの賠償を受け取れなくなる危険があります。
先述のとおり、追突事故で打撲やむちうちとなった場合などは、診断書には「頚椎捻挫」「胸部打撲」「全治2週間」といった記載がなされます。
しかし、提出した診断書よりも「実際の治療期間が長くなった場合」は、追加の診断書を提出する必要はないのでしょうか?
警察に提出した診断書の場合は、記載された治療期間より、治療に時間がかかっても診断書を書き直し、再提出する必要はありません。
一方、自賠責保険への被害者請求では、追加の診断書を作成し、自賠責保険に提出したほうがよいでしょう。
事故との因果関係が明らかになれば、治療費を受け取ることができるようになります。
加害者と事故の診断書を出す出さない、出されたやつ取り下げてほしいといったことで揉めることがあります。
それは加害者が警察に人身事故として扱ってほしくないという理由によります。
物損事故扱いになりさえすれば、ケガの治療費や慰謝料を支払う必要はないですし、免許の点数も加点されません。
ただ、被害者がその要求を飲んでしまうと、治療費は支払われず、最終的な賠償金の額も大きく変わり、特に示談交渉でもめたときに困るケースも多いです。
もし、加害者の対応に問題があると感じたら、弁護士に相談してみましょう。
先述の通り、職場に提出する診断書の場合は、コピーでも認めてくれる場合がありますが、警察などには原則的に「原本」を提出することになります。
また、コピーを取る場合に、診断書を開封して中を確認すること自体も特に問題は有りません。
交通事故の診断書はすぐもらえるのでしょうか。もらい方はどうなるのでしょう。
医師によっては診断書の作成を依頼されたときに、あまりいい顔をしないことがあるかもしれません。
医師は、患者から診断書の作成を求められたら、正当な理由がなければ、応じなくてはならない医師法上の義務があり、断ることができません。
ただし、もらい方などを研究すると、すぐもらえるのではないかと考え、診断書の書き方などを細かく指摘したりすると、医師と患者でコミュニケーションがうまくもらえないケースも見られます。
伝え方やもらい方には十分な配慮と戦略が必要です。
このような場合は、交通事故に強い弁護士に一度相談すると良いでしょう。

診断書の提出先の説明は以上になりますが、提出先として加害者の任意保険会社が含まれておらず疑問に感じた方もいるかもしれません。
実は、損保ジャパンやSBI損保など加害者側の任意保険会社から届く「同意書」に署名をして返送している方が多いかと思いますが、この場合、診断書の送付が不要になるのです。
それはなぜなのか、同意書と診断書の関係を最後にチェックしておきましょう。
交通事故の治療のために通院をすると、その都度窓口で、かかった治療費を被害者が立て替えて支払わなければなりません。
病院によっては健康保険ではなく自由診療扱いとなる場合もあり、一度に支払う金額も非常に大きくなりこれが被害者への大きな負担となります。
そこで、実務上は、病院側から加害者の任意保険会社宛に請求してもらい、被害者が窓口で治療費を立て替えなくても済むようにしています。
これを一般的には「一括対応」または「一括払い」等と呼びます。
上記の仕組みを利用する際に、相手の任意保険会社に対して、治療内容や治療費の明細を伝える必要があります。
しかし、被害者の既往症などの医療情報はプライバシー保護の必要性が高いため、通常はこれらの情報を病院が保険会社に対して直接開示することはありません。
そこで、「自分の既往症などの医療情報を病院から保険会社に対して教えることに同意する」という内容の同意書を得ておく必要があるのです。
したがって、同意書にサインをした場合は、任意保険会社に診断書の提出が不要になるわけです。
同意書の書面は、保険会社によっても書式がさまざまで、「医療照会に対する回答同意書」とか「承諾書」という名称の場合もあります。記載事項の例は下記の通りです。
同意書を出すことで、被害者は病院の窓口で治療費の料金をたて替える必要がなくなりますので、早いタイミングで同意書を提出することには注意点よりもメリットの方が大きく、同意書にサインをしたからといって、即座に被害者に不利益をもたらすことはないでしょう。
ただし、後遺障害等級認定の申請を事前認定でする場合に、事故態様やケガの程度などについて、認識にずれがあるときは、医療照会といった方法をとることも考えられます。
もし、同意書の提出や治療の進め方やタイミングに関して、不安がある場合は、気軽に交通事故に強い弁護士に無料相談してみるとよいでしょう。

診断書の中でも特に「後遺障害診断書」作成の際には、弁護士のサポートも重要です。
適切な内容で作成してもらわないと、後遺障害が残った場合でも適切に後遺障害等級認定を受けることができなくなり、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れなくなってしまうおそれがあります。
特に弁護士の中でも、交通事故問題に強い弁護士であれば、後遺障害についての知識を持っています。
そのような弁護士に相談をすれば、具体的にどのような方法で医師に後遺障害診断書の作成を依頼すれば良いか、アドバイスしてもらえます。
後遺障害等級認定の場面以外でも、交渉をすべて弁護士に任せるのも良いでしょう。交通事故問題に強い弁護士に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。
今回は、Twitter、ブログやYahoo!知恵袋でも話題の交通事故で必要になる診断書の内容や治療日数、書き直しや追加提出の疑問、むちうちとの関係などについて解説しました。
診断書作成の場合には、目的を考えながら、その目的に従った記載をしてもらうように注意しましょう。
交通事故で診断書が必要になった場合には、交通事故問題に強い弁護士に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。