交通事故の後遺障害とは|認定されたら?等級をわかりやすく解説【2024年版】
交通事故で後遺障害認定受けるために必要なことをご存知ですか?後遺障害とは何か、後遺障害として認定されるメリットやデメ…[続きを読む]
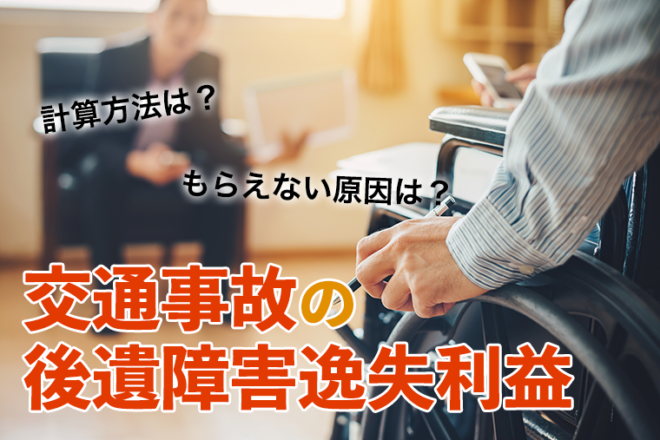
交通事故で後遺症が残ったとき、損害賠償金の大きな部分を占めるのが、「後遺障害逸失利益」です(「後遺症逸失利益」、「後遺症による逸失利益」とも呼ばれます)。
ただ、「逸失利益」という法律用語は、「慰謝料」のように、よく耳にする言葉ではなく、自分が交通事故の被害者となり、この問題に直面しても、理解は容易ではありません。
この記事では、後遺障害逸失利益の基本的な知識を整理し、できるだけわかりやすく解説してゆきます。
また、後遺障害認定の基本については下記記事を併せてご参照ください。
目次
交通事故が原因で、身体の活動等に制約をうけると、健康なときに比べ十分に働くことができず、事故前と同じ収入を得るのが困難となることが予想されます。
このとき、得られなくなった将来の経済的な利益が、「後遺障害逸失利益」です。
交通事故で賠償請求できる損害の項目は、大きく次の3つに分けられます。
積極損害とは、被害者が支出を余儀なくされた経済的な利益であり「治療費、入院雑費、付添看護費、通院交通費」などです。
消極損害とは、被害者が受けとれなくなった経済的な利益であり「休業損害、後遺障害逸失利益・死亡逸失利益」がこれにあたります。
慰謝料とは、ケガ、後遺障害、死亡による精神的・肉体的な苦痛をひとつの損害ととらえるもので「入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料」があります。
後遺障害逸失利益と休業損害は、どちらも交通事故で受けとれなくなった利益であり、消極損害という点で共通します。
しかし、後遺障害逸失利益は、事故のために失うことが予想される「将来の収入」であり、休業損害は、事故のために休んで失った「過去の収入」という違いがあります。
後遺障害逸失利益を計算するためには、次の計算式で計算します。
後遺障害逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間
上記、各項目を簡単にわかりやすく解説すると次のとおりです。
なお、後遺障害逸失利益を一括払いで受け取るとき(これを「一時金賠償」といいます)には、上の計算式の結果から、さらに「中間利息」を差引く必要がありますが、それについては後述します。
また、下記に細かい注意点やポイントなどを解説して参りますが、すぐに自分の場合の逸失利益の金額を知りたいという方は、下記の慰謝料・逸失利益の自動計算機(シミュレーション)をご利用ください。
例えば、サラリーマンなど給与所得者は、事故の前年度の「源泉徴収票」が証拠となり、基礎収入を決定します。
注意点としては、給与所得者の基礎収入を立証することは難しくありませんが「自営業者」においては複雑な問題が生じることが珍しくありません。
例えば家族経営の店舗など、収入が事業主である被害者一人の名義であっても、家族の協力・貢献の成果部分が含まれている場合は、その収入に対する被害者の実質的な寄与度を検討して基礎収入を算定する必要があります。
現実の収入が基礎収入という原則を貫くと、被害者保護を十分に図れず不都合な場合があります。
この場合は「統計上の平均賃金」を利用して基礎収入を算定することがあります。
平均賃金とは、厚労省の「賃金構造基本統計調査」通称「賃金センサス」の数字です。
下記、ケース別にわかりやすく解説して参ります。
例えば、たまたま事故前年に転職したばかりで、年収が平均賃金よりも低い場合、その年収を基礎収入としてしまうのでは、逸失利益を正しく評価したことになりません。
そこで「転職前の実績」などから、今後、平均賃金額を得られる蓋然性があれば、その金額を基礎収入とします。
一般に、若年労働者は低賃金なので、その年収を基礎収入としたのでは逸失利益が低くなりすぎます。
そこで、事故時点でおおむね30歳未満の場合は、全年齢平均賃金(年齢で区別しない平均賃金)をもって基礎収入とします。
家政婦を雇えば賃金を支払うように、家事労働にも経済的な価値があるので、主婦(主夫)にも逸失利益が認められます。現実の収入はないので、女子の全年齢平均賃金を基礎収入とします。
また、主婦(主夫)については、パート等で収入がある場合の基礎収入はどうなるか、高齢者のように他の家族と家事を分担している者をどう取り扱うかなどの細かい問題があります。
子ども、学生は、現実の収入はないものの、将来的には収入を得られることが通常ですから、男女別の全年齢平均賃金を基礎収入とします。
ただ、子ども、学生については、女子年少者の基礎収入に女子の全年齢平均賃金を利用すると、男子年少者との賃金格差が大きくなりすぎる点をどう是正するか、大学未入学の者に大卒者の学歴別平均賃金を適用できるか否かなどの細かい問題があります。
現実の収入はありませんが、労働能力と労働意欲があり、就労する蓋然性が認められれば、男女別の平均賃金を基礎収入として逸失利益が認められます。
失業して求職活動中だった場合には、原則として失業前の収入を基礎収入とします。
なお、無職者、ニートの場合には、逸失利益が認められても、平均賃金よりも低い金額を基礎収入とされてしまう傾向があるなどの問題があります。
また先述した式の中に基礎収入以外にも「労働能力喪失率」がありました。
こちらは、健康なときの働く力を100%として、後遺障害で失われた働く力を割合(%)で表した数値です。
後遺障害は、その内容と程度に応じ、1級から14級までの等級付けがなされており、それが後遺障害等級と呼ばれます。
この等級に応じて、100%から5%までの労働能力喪失率が定められています。
労働能力喪失率表(※)
| 等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
| 喪失率 | 100% | 100% | 100% | 92% | 79% | 67% | 56% | 45% | 35% | 27% | 20% | 14% | 9% | 5% |
※「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」の「別表Ⅰ」・平成13年金融庁・国土交通省告示第1号・令和2年4月1日施行
労働能力喪失期間とは、後遺障害で喪失・低下した力で働き続ける期間(年数)のことです。
実務では「人が働いて収入を得る期間(就労可能期間)を18歳から67歳」と取り扱います。
そのため、18歳以降の症状固定の時点から67歳までが「労働能力喪失期間」となります。
さて、以上のように労働能力喪失期間の終期は常に67歳となるはずですが、裁判例では「むち打ち症」などの末梢神経障害の場合、就労可能期間にかかわらず、労働能力喪失期間を「5年から10年に制限」して後遺障害逸失利益を計算することが通例なので注意すべきと言えるでしょう。
逸失利益は、将来的に稼げたはずの収入であるため、10年後の収入は10年後に稼げたはずですし、67歳時の収入は67歳時に稼げたはずです。
つまり逸失利益は、本来なら、その時々に受け取るべき利益なのです。
ところが、現時点で、その全額をまとまった一時金賠償で受け取り、被害者が投資などで利殖するならば、年々、被害者は利息を受け取ることが可能となり、被害者には損害の補てんを超える利益が与えられることになって不公平です。
そこで、この利息に相当する金額(中間利息)を、あらかじめ差し引いて支払う必要があるのです。
中間利息は毎年発生しますので、労働能力喪失期間中の毎年の利息を算出して合計する必要があり、これをひとつひとつ計算するのは手間がかかります。
そこで、この計算を一発で済ませる計算式を使います。それが「ライプニッツ係数」です。別名、中間利息の控除係数と言います。
中間利息を控除した逸失利益を計算するためには、下記の計算式を利用します。
本来の計算方法
=(基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間)- 中間利息
ライプニッツ係数を使った計算方法
=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数
また、逸失利益を一時金ではなく、毎月の「定期金賠償」として受け取ることができれば、中間利息を控除される必要はなく、被害者に非常に有利です。
2020(令和2)年7月、最高裁は新判例で後遺障害逸失利益の定期金賠償を認めました。その詳細は、次の記事をお読みください。
後遺症が残ったのに、後遺障害逸失利益をもらうことができない場合、原因として、次のものが考えられます。
症状が固定しても、必ず「後遺障害」と認定されるわけではありません。自賠責保険の等級認定基準をクリアする必要があります。
例えば、むち打ち症のような末梢神経障害で後遺障害等級が認定されるには、もっとも低い等級の14級であっても、交通事故に基づく症状「医学的に説明がつく」ことが要求されます。
自覚症状しかなく、しかも事故から相当の日数を経て現れた症状などについては、事故によるものと医学的に説明できないとして、「非該当」即ち、後遺障害ではないと判断されてしまいます。
「非該当」となると、自賠責保険から後遺障害逸失利益を受け取ることはできません。
また損害賠償問題の最終決定権を持つ「裁判所」は、自賠責保険の等級判断に従う義務はないものの、多くの場合、自賠責保険の等級認定を尊重しますので、自賠責保険に非該当とされてしまうと、訴訟においても後遺障害と認められない可能性が高くなります。
したがって、後遺障害逸失利益を得るためには、自賠責保険の審査の段階で後遺障害等級認定を獲得しておくことが重要です。
もっとも、限られた医療記録に基づく書面審査である自賠責保険とは異なり、訴訟ではあらゆる資料が証拠となり、裁判官が直接に被害者と会って、その供述を聴くため、自賠責保険で「非該当」となったものが、裁判所では後遺障害と認定され、後遺障害逸失利益が認められる場合も少なくはありません。
したがって、「非該当」とされたときや、認定等級に不満があるときは、弁護士に訴訟提起を依頼することを検討されるべきでしょう。
不動産の家賃収入等で生活する不労所得者や年金生活者の場合、後遺障害となっても収入が減少しないケースがあり、何らの損害もない以上、逸失利益は認められません。
他方、働いている場合でも、事務職の公務員の場合など、後遺障害等級が認定されても、職場に復帰した後に、事故前と同じ給与を得て、現実の収入減がないケースがあります。この場合にも、逸失利益を受け取ることはできないのでしょうか?
判例は、以下の場合は、特段の事情がない限り、逸失利益を認めないとしています(※)。
特段の事情とは、次のようなケースです。
このような特段の事情を検討し、事故後の減収がない場合でも、逸失利益を認める裁判例は数多くあります。
示談交渉において、保険会社が、被害者が働いておらず現実の収入がないことを理由に、逸失利益を支払わないと主張することがあります。
しかし、前述したとおり、事故前に現実の収入がなくとも、主婦(主夫)、子ども・学生、将来的に就労する蓋然性がある無職者には、平均賃金を用いた逸失利益が認められます。
後遺障害等級が認定されても、加害者側から、具体的な労働能力の低下がないと主張されるケースがあります。
外貌醜状、歯牙障害、生殖器障害、変形障害などが典型です。
例えば、容貌に著しい醜状が残った場合でも、外見が重要となる特殊な職業(俳優・女優・モデルなど)を除いて、身体能力、体力、知力に影響せず、ただちに働く力が低下したとは言えないと主張されるのです。
しかし、醜状障害のゆえの、次のようなリスクは否定できません。
したがって、醜状障害でも労働能力の低下を認める裁判例が増えています。
他方、生殖器障害は、性行為を行う能力が失われても、働く力には影響がないとして、労働能力喪失を否定し、後遺障害逸失利益を認めないのが裁判例です。
ただ、子孫を残す能力を失うことの重大性から、多くの裁判例では、後遺障害慰謝料を増額することで埋め合わせはなされます。
症状が残ってしまっても、それが事故に基づくものではなく、事故と症状との因果関係が認められない場合には、後遺障害逸失利益は認められません。
例えば、椎間板ヘルニアによる腰痛の症状が残ったケースで、事故前から同じく椎間板ヘルニアの既往症があったことが明らかであれば、事故との因果関係が否定される場合もあります。
ただし、事故によって症状が悪化したことなどを主張、立証することで、因果関係を認めてもらえる可能性はあります。
他方、「後遺障害は既往症も寄与している」として素因減額により、後遺障害逸失利益を含めた賠償額を減額される場合もあります。
被害者自らが加入してる任意保険のうち、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険などは損害を補償してくれます。
ただ、これらの保険で後遺障害逸失利益が補償対象となっていても、補償される金額の限度額(上限額)が低いケースがあります。
また、限度額が無制限や高額に設定されていても、保険会社側が、次のような対応をすることで後遺障害逸失利益を安く抑えようとする場合があります。
その場合には、保険会社との交渉で、弁護士を利用し、適正な基礎収入・労働能力喪失率・労働能力喪失期間などを主張して、正しい後遺障害逸失利益を認めさせる必要があります。
なお、後遺障害逸失利益は、事故前の現実収入を基礎収入とすることが原則なので、現実の収入に男女間格差がある以上、それがそのまま反映されます。
基礎収入の認定に賃金センサスを用いる場合でも、男女別の平均賃金を利用するならば、当然に男女間格差が生じます。
逸失利益は将来の予測数値なので、男女の不平等を当然の前提とすべきではないという意見がある一方、現実の損害を補てんするという損害賠償制度の目的からして、実際に社会に存在する収入格差を無視できないという意見もあり、男女間格差をどう取り扱うかは難しい問題です。
ただ、実務では、男女間格差をなくす方向で平均賃金を利用する場合は珍しくありません。
例えば、家事労働者については、男性の「主夫」であっても、女子平均賃金を基礎収入とします。
女子年少者については、女子の全年齢平均賃金を利用すると、男子年少者との格差が開きすぎることから、男女を区別しない全労働者の平均賃金を基礎収入とする場合があります。
後遺障害逸失利益の基本的な知識をわかりやすく解説しました。さらに詳しい内容については、記事中にあげた参考記事をお読みください。
そのうえで、個別の具体的な疑問は、交通事故に強い弁護士に相談されることをお勧め致します。